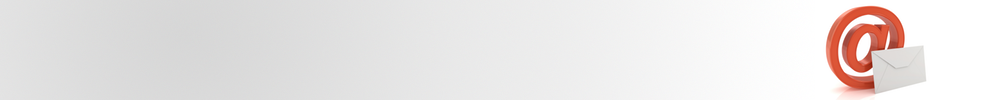
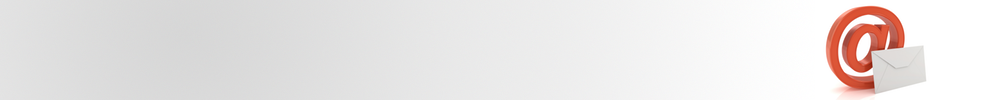
月1回発行のメールマガジンを毎月初に配信しています。保険に関する情報や身近な時事情報をお届けしています。
ご登録いただいた配信先は、当メールマガジンの配信のみに使用いたします。また配信が不要になった際の解除も簡単に行えますのでご安心してお試しください。
前月までに配信したメールマガジンの記事のみをバックナンバーとして公開しています。
実際のメールマガジンには、記事以外に、保険レポートが含まれます。月初での配信や保険レポートの送付もご希望の場合は、是非メールマガジンへのご登録をお願い致します。
10月に入りました。
東京も朝晩は涼しくなり秋の訪れを感じられる季節になりました。
スポーツもしやすい天候となり、先日9月23日には私が監督を務める小学5年生の野球チームで公式戦初勝利をすることができました。
5年生は13名在籍していますがそのほとんどが野球をはじめて1年未満の経験の浅い子供たちです。
そのため今まで練習試合でも公式戦でも勝つことができませんでした。
私は選手たちに勝つ喜びと負ける悔しさの両方を経験して欲しかったですが、今までは勝とうと思わずに試合をしていたため負けても悔しくもなく、もちろん勝てないので勝つ喜びも経験させることができませんでした。
ところが先日の試合で8-7の接戦に勝つと、選手たちの目の色が変わりやる気と意欲が満ち溢れるようになりました。
その後の練習でも互いに声を掛け合い意欲的に練習に取り組み、平日も自主的に素振りをしたり、全く別の選手、チームに生まれ変わったかのようでした。
たった1つの勝利がこんなにも人を変えるということを体現しています。
選手たちを見ていて私たち大人も同じだと思いました。
やはり成功体験と失敗体験の両方が必要なのだと思います。
何かに一生懸命に取り組み成果を挙げようと頑張っても不本意な結果に終わってしまった。
悔しい思いをする。
そして反省し次こそ成果を出そうと頑張り、ついに自分の思うような結果を出し成功体験を積む。
その1つの成功体験が自信につながり、よりモチベーションが上がり、さらに成長を加速させていく。
こうした大きくても小さくても成功体験と失敗体験を積み重ね繰り返すことで人は成長していくのだと思います。
大切なことは、どんなときも明るく前向きに、そして「きっとうまくいく」と自分を信じることだと思います。
子供たちとの野球を通じて、私自身もまだまだ伸びしろがあると信じ、これからも挑戦していきたいと改めて感じています。
これからスポーツの秋です。
子供たちと一緒に野球を楽しみ一緒に汗を流したいと思います。
今月もよろしくお願いいたします。
本日は9月1日です。
子供たちは長い夏休みが終わり今日から学校がはじまります。
今年の夏は本当に暑かったですね。
まだまだ暑い日が続くようなので体調管理にお気をつけください。
今回は「だ液によるがん検査」について情報提供させていただきます。
個人や法人のお客様へご案内をすると高い関心を持って聞いていただいており利用者も増えています。
だ液中に含まれる代謝物を分析し、がんリスクを評価してがんの早期発見・早期治療が期待できる新しい検査です。
この検査のメリットは、1回のだ液採取で、肺がん・膵がん・胃がん・大腸がん・口腔がん・乳がん(女性のみ)の6種類のがんリスクを検査できることです。
従来は、胃がんの検査であれば胃内視鏡検査、大腸がんの検査であれば大腸内視鏡検査やCT検査、女性の乳がんの検査であればマンモグラフィ検査や超音波検査など各部位を個別に検査する必要があり、検査には身体への負担もありました。
私も毎年の人間ドックで胃カメラ検査をしていますが、慣れることもなく毎回苦痛です。
しかしこのだ液検査であれば、1回のだ液採取で6種類の部位のがんリスクを検査することができます。
当社のお客様で過去にがんに罹患してがん保険の給付を受けていらっしゃる方が多くいらっしゃいますが、治療によって完治してその後は元気に過ごされているお客様がほとんどです。
医療技術の進化によってがんは昔ほど恐れる病気ではなくなってきていますが、がん罹患後の生存率を見ると、やはり早期発見・早期治療がポイントです。
早期に治療すれば治る確率が高くなり、ステージが進行してからの治療だと死亡率が高くなってしまいます。
こうした新しい検査を通じて早期発見が期待できることは将来を健康に過ごすうえで大きなメリットがあると考えています。
だ液検査の信頼性は70%程度と言われています。
だ液検査でがんリスクが高いと判定された場合には、専門医を通じて詳細の検査をし、早期発見できれば早期治療につなげていきます。
保険会社によっては保険契約者やご家族がこの検査を受ける場合、検査費用を割り引く特典サービスを実施しています。
ご関心のある方はお気軽にお問合せください。
以下が「だ液検査」の詳細です。
今月もよろしくお願いいたします。
8月に入りました。
毎日暑い日が続きますね。
先日、高校野球の甲子園出場校49校がすべて決まりました。
東京は東東京が関東一高(2年連続10回目)、西東京が日大三高(2年ぶり20回目)となりました。
私の母校である佼成学園は甲子園を目指して戦いましたが惜しくもベスト8で今夏を終えました。
それでも130校が参加する西東京の予選トーナメントでベスト8まで勝ち進んだことは立派だと思っています。
甲子園出場を決めた関東一高と日大三高は、私が高校生だった頃、今から35年前から強豪校で甲子園にも何度も出ていました。
選手も指導者も入れ替わっているなかで30年40年ずっと強いというのは本当にすごいと思います。
日大三高はなぜずっと強いのか。
日大三高にあって佼成学園にないものは何か。
そんなことを考えたりしています。
今は引退されている日大三高の小倉全由前監督のインタビュー記事のなかに以下のような言葉があります。
「選手のやる気がでる叱り方が大切」
「熱く高校野球をやる」
「ベンチに入れなかった選手にも三高で野球をやれてよかったと思ってもらいたい」
「一生懸命の大切さを伝える」
このなかに強い理由、勝てる理由の一端があると感じます。
これは高校野球だけでなく私たち社会人にとってビジネスでも会社経営にも生かせる言葉だと思います。
京セラ創業者の稲盛和夫氏は、
仕事(人生)の成果=考え方×熱意×能力
と説いています。
小倉監督の言葉に通じるものだと感じます。
時代や環境が変わっても、変わらない原理原則ってありますね。
高校野球をみながら私自身も学びました。
佼成学園の野球部はすでに新チームでの活動がスタートしています。
OBの一人としてこれからも応援していきます。
今月もよろしくお願いいたします。
7月に入りました。
東京は梅雨がどうなったのか分からないまま真夏に突入したかのように連日の猛暑が続いています。
そんななか当社は去る6月6日に事務所を移転しました。
新住所は文末の署名欄の通りです。
当社は現在19期目を迎えておりコロナ禍が収束した2024年以降の業績は順調に推移しています。
これはひとえにお客様をはじめ日ごろから当社を応援してくださるみなさまのおかげ様であると感謝しています。
ありがとうございます。
事務所の移転を機に当社の経営理念も更新しました。
新たな経営理念は、「人と会社に安心を提供する」です。
設立当初からの経営理念も「安心」をキーワードにしていましたが、それをよりシンプルに改めました。
本日は経営理念に込めた私の思いをお伝えさせていただきます。
当社、株式会社ロムルスは生命保険の販売会社です。
当社が代理店委託契約を締結している生命保険会社は9社です。
その各生命保険会社が販売している商品ラインナップは数多くありますが、商品カテゴリーは大きく分けると以下の3つに集約できます。
1.一般生命保険
2.医療・介護保険
3.個人年金保険
これら3つはそれぞれ契約する目的や動機は異なりますが、1つだけ共通する要素があると考えています。
それはどれもお客様が「安心」を求めて契約することです。
もし世帯主が志し道半ばで亡くなってしまったとき、遺された家族の経済的な安心を得るための保険契約。
病気やケガで入院や手術をしたり働けなくなった場合の経済的な安心を得るための保険契約。
現役を引退したあとの老後を豊かに安心して生活していくための保険契約。
このように種類は違っても生命保険を契約するということは最終的には安心を得るという目的があると思います。
そのため当社も私もこの「安心」を提供することこそ仕事の本質であり使命であると考えています。
これが経営理念に込めた私の思いです。
人と会社に安心を提供する。
この経営理念を実現するためにこれからもお客様本位の業務運営方針を徹底し業務に取り組んでいきます。
今月もよろしくお願いいたします。
6月に入りました。
小泉農林水産大臣のリーダーシップとスピード感により近くのスーパーでも備蓄米が売られるようになりました。
私は現状の米問題を打破した小泉大臣の行動は立派だと思います。
本日は少しネガティブな話題ですが生命保険契約と自殺免責について情報を共有させていただきます。
このメルマガは約1,300人の方に配信していますがそのなかには当社のお客様も多数いらっしゃり、また日本人の生命保険の加入率は90%ということを考えると今回の情報発信は多くの方に知っておいていただきたいと考えるからです。
今年1月にお客様の奥様からご主人が亡くなったとの一報をいただきました。
お客様は60歳の男性で会社経営者です。
私とは20年以上のお付き合いになるお客様でした。
奥様に亡くなったときの状況を聞くと自殺でした。
すぐに契約内容を確認すると、保険契約の責任開始日(=保険契約の申込み日)から数えて3年まで9日間足りない状況でした。
生命保険契約は責任開始日から3年以内の自殺は免責事由に該当し保険金は支払われません。
保険金は1億円です。
金額も大きいので私は何とか保険金を支払えるような可能性はないかと思い、お客様宅を訪ねました。
亡くなる前の状況を聞くと数か月前から躁うつ病の症状があり家族も会社の従業員からも病院での診察を勧めていたが病院の受診はしていなかったこと、また2年前くらいから耳鳴りがするとのことで耳鼻科に通院していたことを聞きました。
生命保険契約の約款では3年以内の自殺でも精神疾患による自殺の場合には免責されない場合があるという但し書きがあります。
私はこの精神疾患による自殺に該当するのではないかと考え、保険請求書類の状況報告欄に奥様の自署で躁うつ病の症状と耳鳴りによる耳鼻科通院について詳細に記入していただき、その他の書類を揃えて保険会社へ保険金請求をしました。
同時に保険に詳しい弁護士さんに相談しました。
保険請求をしてからしばらく経って保険会社から連絡があり、保険金担当の部署から奥様へ再度ヒアリングの連絡があり、病院や警察へ調査が入りました。
こうしたプロセスがあるということは保険金が支払われる可能性もあるのではないかと希望を持って時が経つのを待ちました。
しかし5月初旬、保険会社から正式な回答があり、自殺免責に該当し保険金は支払われませんでした。
私も担当者として出来うる限りのことをしましたが保険金をご家族に届けることはできませんでした。
ご家族もやりきれない思いだったでしょうし私自身も無念です。
何よりも亡くなったお客様はもっと無念だったと思います。
私は生命保険業界に入って24年が経ちます。
この長い期間で自殺されたお客様も他にいますが契約から3年以上経過していたので契約通りの保険金が支払われています。
自殺免責で保険金が支払われなかったのは今回がはじめてです。
生命保険を契約するとき、お客様はみなさんご家族のためを思います。
自分にもし万が一があった場合、残された奥様やお子様が経済的に困らないように少しでも残してあげたい。
家族に対する気持ちを表したい。
そんな思いが保険証券には詰まっていると思います。
だからこそもし本当に亡くなったときには保険金が支払われその保険金がいち早く大切なご家族へ届けられるべきだと思っています。
自殺免責に該当し保険金が支払われないということは避けなければいけません。
契約から3年以内の自殺は保険金が支払われない。
このことは生命保険を契約するときには知っておいてもらいたいと思っています。
お客様のご冥福を心からお祈りするとともにご家族のみなさまの日常が戻り心穏やかに過ごされるようになることを願っております。
今月もよろしくお願いいたします。
連休谷間の5月1日ですがいかがお過ごしでしょうか。
当社はカレンダー通りに営業しています。
本日はがん保険について解説させていただきます。
がん保険の給付請求をご対応させていただくなかで思うことがあったためです。
日本人の死因第1位はがんであり、一生のうちがんに罹患する人は2人に1人と言われています。
そのためがん保険に加入する人も多く、当社でも過去に多くのお客様からがん保険のご請求をいただいています。
私は生命保険業界に24年間いますが、ご請求いただいたお客様から治療方法や期間などをお聞きするなかで、がん治療の状況が大きく変わってきていると感じます。
まず1点目は入院期間が短期化していることです。
そして抗がん剤治療の方法が、入院による点滴⇒外来通院による点滴⇒飲み薬(経口投与)に変わってきていることです。
以前は点滴による抗がん剤治療は入院することが一般的でした。
抗がん剤の治療クールが6回だとすると、1クール5日間程度の入院を6回繰り返すようなイメージです。
それが入院しないで抗がん剤治療期間のたびに外来で通院するというケースが増えています。
最近も50代のお客様が抗がん剤治療期間は入院せずに外来通院で6クール治療をされていました。
年齢が若い患者さんには入院より通院を進められるケースが多いイメージです。
さらに錠剤やカプセルの飲み薬(経口投与)での抗がん剤治療も増えています。
経口投与の場合、月1回、薬をもらいにいって自宅で薬を飲むので通院日数はさらに減ります。
このようにがん治療の方法が大きく変わってきています。
そのためがん治療を保障するためのがん保険の内容も現在のがん治療の実態に合っている商品である必要があります。
昔のがん保険は入院すると1日あたり10,000円が給付されるという内容で通院では保障されない内容のものも多くありました。
このタイプだと入院日数が短期化し通院が治療の中心になっている現在のがん治療には適合されないため十分な保障を受けることができません。
その後通院でも保障されるがん保険が出てきましたが、経口投与になると通院日数も極端に減るためやはり十分な保障を受けられない可能性が出てきます。
こうした実情を考えると現在のがん治療の実態を合っているがん保険というのは以下の条件を満たしている必要があると考えます。
1.通院保障があること。
2.入院や通院の日数にかかわらずがん治療が継続されている間は十分な保障を受けられること。
医療の進歩は日進月歩です。
がん治療の方法も日々進歩しています。
こうした医療の進歩にがん保険も対応していく必要があるのだと思います。
とはいえ現在契約しているがん保険を解約して新たながん保険に入り直すと年齢も上がっていたりして保険料が大幅に高くなってしまうことも考えられます。
なので現在契約しているがん保険をそのまま継続しながら、一部の特約のみを新しい保障に入れ替えたり、少しだけ追加で契約するという方法もあります。
保険会社各社も切磋琢磨しながらがん保険をバージョンアップしています。
まずはご自身のがん保険の内容を確認していただき、現在のがん治療に合っている内容になっているかをチェックすることをお勧めします。
ご質問などあればいつでもお問合せください。
今月もよろしくお願いいたします。
4月に入りました。
東京は先週暖かい日が続き桜が咲き始めましたが、今朝は冷たい雨が降っています。
桜が散らないことを願いつつ晴れて暖かくなったらお花見をしたいと思っています。
お米の価格高騰が止まりません。
私たち家族もお米が好きで主食にしていますが、昨年に比べて値段が1.4倍くらいになっています。
高いだけでなくすでに品薄になっています。
その原因についていろいろ言われていますが、私なりにしらべてみたのでお知らせしたいと思います。
まず「投機目的の業者がいる」という風説ですが、これは実際に米業界で玄米の転売で利ザヤを稼ぐ業者はいるようですが、その影響は微々たるもので、もっと構造的な原因があるようです。
それは主に以下の通りです。
1.農林水産省が過剰生産による米価格の低下を懸念するあまり需給計画を意図的に締め過ぎたこと。
2.猛暑による高温障害とカメムシによる被害で品質のよい米の収穫量が減ったこと。
3.昨夏の品薄で米不足への警戒から集荷業者や卸売業者が米を多く確保したこと。
これらが複合的に重なった結果が現在の「令和の米騒動」につながっていると感じます。
そもそも米政策を巡っては、政府は2018年に減反(生産調整)政策を廃止しています。
しかし、米余りによる値下がりを懸念する各産地では、農家ごとに上限目標(目安)を設定し、目安に強制力はないものの、減反時代の慣習を引き継ぐ農家も多く、事実上の生産調整は続いているようです。
このような状況下で余裕のない需給計画を立てれば、天候不良など不測の事態によってすぐに現在のような供給不足に陥ることは避けられません。
今後は備蓄米の放出など場当たり的な対応ではなくもっと抜本的な改革が必要だと感じます。
もっと自由に米をつくれる環境を整えるべきではないでしょうか。
自由につくればどこかの点で需要と供給のバランスが取れて価格も安定していきます。
私たち消費者は、「いつでも美味しいお米が適正な価格で買える」という状態を希望しています。
世の中はITの進展とともに非常に早いスピードで変化し続けています。
農業も変化・変革が必要な時期に来ていると思います。
まだ4月なので今年の新米の時期までまだ半年もあります。
私たち家族の間では、これ以上お米の値段が上がった場合には無理にお米に固執しないで、パンや麺類で代替えしようと話しています。
そういう家庭も多いのではないでしょうか。
今は高くても売れる状態が続いていますが、これが続くとお米離れが進んでいくと思います。
美味しいお米がいつでも適正価格で食べられるように、お米の生産と流通について関係各所におかれては構造改革をしてもらいたいと願っています。
今月もよろしくお願いいたします。
3月に入りました。
東京は昨日まで暖かく過ごしやすい陽気が続きましたが、今日から天気が一変して寒い日が続くようです。
体調管理に努めたいと思います。
2月28日にトランプ米大統領とゼレンスキーウクライナ大統領が会談しました。
しかし報道でもある通り両大統領は激しい口論の末、首脳会談は決裂し、予定していたウクライナの資源権益に関する協定への署名を見送りました。
会談の一部を動画やテキストで見ましたが、決裂の大きな要因は安全保障だっと思われます。
ゼレンスキー大統領は停戦後に武器在庫を立て直したロシアが再び侵略しないように米国が安全保障支援の継続するように求めました。
ウクライナの主張としてはロシアが過去に何度も停戦を破った経験があるためです。
それに対しトランプ大統領は、それよりも資源権益に関する協定へ署名してまずは停戦することが先だと主張しました。
ゼレンスキー大統領は安全保障なしには停戦を受け入れられないと妥協せず会談は決裂しました。
私は今回の会談をみて私たちの安全について不安を感じました。
日本に危機が訪れたとき、米国が守ってくれるかは疑問だということです。
守ってもらうためにはその見返りとして大きな犠牲を払わなければいけなくなるのではないかと。
例えば沖縄が攻撃されたとき沖縄を守るからその変わり沖縄を米国領土にさせろとか。
北海道が占領されたあとで東北以南は守るからトヨタを米国資本にさせろとか。
自分の身を自前のヒト・モノ・カネで守れないと、弱っているときこそ弱みに付け込まれ、妥協せざるを得なくなってしまうと思います。
無理難題を押し付けられても受け入れるしかない状況に陥ってしまうリスクがあります。
現在の日本の防衛体制は、日米安保と自衛隊の2つで成り立っていますが、その抑止力としての比重は日米安保の方が高いと考えています。
そして自衛隊は憲法に明記されていないいわば令外官のような扱いになっています。
ロシア・ウクライナ戦争と米国の停戦への仲介のプロセスを見ると、日本は、自分の国は自分で守るという気概と体制強化が必要になってきているのではないでしょうか。
日米安保のより一層の強化と自衛隊の防衛力強化は、今まで以上に必要性が高まっていると感じたことが今回の会談での感想です。
憲法改正の議論も長年続いていますが、日本の国防についてみなさまはどのようにお考えでしょうか。
それにしてもゼレンスキー大統領の大国を目の前にしても一歩も引かないという態度は、リーダーの姿としては胸を打つものがあります。
国も自分の立場も追い込まれ、トランプ大統領が「君にはカードがない」と言っているように、実際に客観的にみれば交渉できる立場ではないにもかかわらず、絶対に譲れない一線は妥協しないという姿勢をみると応援したくなるのが人情です。
日本の総理大臣がトランプ大統領を前にしても、妥協しない、議論を恐れないという態度を取っている強い姿も見てみたいですね。
今月もよろしくお願いいたします。
2月に入りました。
1月21日、メジャーリーグで大きな功績を残した選手が対象となるアメリカ野球殿堂入りが発表され、イチローが選出されました。
メジャーリーグで、10年連続200本安打、シーズン歴代最多安打(263安打)、通算3,089安打などの功績が評価されました。
394人の記者による投票では満票には1票足りなかったものの、99.7%の得票率で選出されたことは私たち日本人としても誇りに思います。
ここ数年間は野球の話題は大谷選手ばかりでしたが、私自身と歳の近いイチローが久しぶりに注目されたことをうれしく思っています。
また長年所属していたシアトルマリナーズはイチローの背番号「51」と永久欠番にすると発表しました。
私の年代で永久欠番というと読売ジャイアンツの王さんの「1」と長嶋さんの「3」をイメージするので、イチローがメジャーリーグで伝説級の野球選手の仲間入りを果たしたこともすばらしいことだと喜んでいます。
今回の殿堂入りに際してイチローの会見を何度も見返しましたが、そのなかで印象に残ったことを2つ挙げたいと思います。
1つ目は、満票でなかったことについての感想を求められたときの回答です。
イチローは「一票足りなかったのはよかった。不完全だからこそまた進もうと思える。」と答えました。
51歳になった今でもトレーニングを欠かさず、メジャーリーグの選手たちへ一緒に身体を動かしながら指導しています。
また日本では高校生に対して定期的に指導をしています。
自分自身ができることを探し、まだまだ常に成長していきたいという姿勢は学ぶべき点を多いと感じています。
2つ目は、これから野球選手を目指す若い世代に向けてのメッセージです。
イチローは、「今、高校生に夢を聞くとメジャーリーグに行きたいと言う。でも一歩ずつ進んでほしい。大きな成果をあげるためには地道に一歩ずつ進むことが大切だ」と答えています。
これはスポーツにもビジネスにも会社経営にも当てはまることだと思います。
大きな夢や目標を持つことは重要ですが、そのためにどうするか、今日どう行動するかという毎日毎日の積み重ねがとても大切であるということを改めて感じました。
私自身もイチローからの学びを日々の生活や仕事の励みにしたいと思います。
私は現在、小学5年生、6年生の野球チームで指導者をしています。
指導している子供たちのなかから将来プロ野球選手が現れることを夢見ながら、私も子供たちと一緒に野球を楽しみたいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
あけましておめでとうございます。
2025年、令和7年となりました。
本年もよろしくお願いいたします。
今年の干支は「へび」。
60年に一度のサイクルである十干十二支では「乙巳」となります。
乙巳の年は、新しい挑戦や転換がテーマとなる年で、これまでの努力や準備が実を結び勢いが増す年とのこと。
今年一年がみなさまにとってよい年になるように願っています。
年の初めに自分自身への自戒も込めて大前研一氏の箴言をご紹介します。
人間が変わる方法は3つしかない。
1番目は時間配分を変えること。
2番目は住む場所を変えること。
3番目はつきあう人を変えること。
最も無意味なのは、「決意を新たにすること」だ。
私は最後の一文を特に重視しています。
決意しても何も変わらないということ。
自分を変えるのは行動でしかありません。
このことに肝に銘じ一年を過ごしていきたいと思っています。
年初の毎月レポートは私たちの医療に関連する高額療養費の見直しについて解説します。
政府は12月27日、2025年度の一般会計予算を決定し、そのなかに高額療養費の見直しが含まれています。
高額療養費は健康保険などの公的保険が適用された医療費の自己負担分が一定金額を超えた場合、あとで払い戻される制度です。
この自己負担額の上限額が見直されます。
概要としては今年2025年8月から2026年、2027年と3段階で見直され、所得が多いほど引き上げ幅が大きくなります。
詳細は以下の通りになります。
<高額療養費 自己負担限度額(月額)70歳未満>
年収 現行 2025年8月~
約1,160万円~ 256,000円 290,400円
約770万円~ 167,400円 188,400円
約370万円~ 80,100円 88,200円
~約370万円 57,600円 60,600円
住民税非課税 35,400円 36,300円
<2027年8月から>
年収区分を13区分に細分化して見直し
年収 自己負担額上限額
約1,650万円~ 444,300円
約1,410万円~ 360,300円
約1,160万円~ 290,400円
約1,040万円~ 252,300円
約950万円~ 220,500円
約770万円~ 188,400円
約650万円~ 138,600円
約510万円~ 113,400円
約370万円~ 88,200円
約260万円~ 79,200円
約200万円~ 69,900円
~約200万円 60,600円
住民税非課税 36,300円
これを見ると所得が多い世帯の引き上げ幅は相当大きいですね。
大企業の会社員では、健康保険組合独自で付加給付がある会社も多く、実質的な自己負担額の上限が2万円とか3万円のケースもあります。
なので付加給付のある会社員は今回の高額療養費の見直しの影響が少ないと考えられます。
しかし、中小企業の経営者や会社員、または個人事業主でけっこう稼いでいる世帯にとっては今回の見直しは影響が大きいと思います。
2027年8月以降、年収が1,650万円以上だと自己負担上限額が44万円以上となっており、これはいくら稼いでいたとしても医療費の負担は大きいと思います。
該当される世帯は要注意です。
今回の高額療養費の見直しを受けて、民間の生命保険会社が販売している医療保険やがん保険のニーズが高まると予測しています。
ですがやみくもに今入っている保険を見直したり増額したりしないで、自分自身にとってどのような見直しが必要になるかを見極めることが大切です。
自分や世帯の年収区分に照らし合わせてどのくらいの保障が必要なのか。
勤務先の健康保険制度がどのようになっているか、付加給付があるのか。
など区分が細分化されることによってニーズやあるべき保障も細分化されることになります。
民間の医療保険やがん保険は、あくまでも健康保険などの社会保障制度の補完的な役割です。
社会保険で補えない保障を民間の保険でどのように補完するか。
これが高額療養費見直しと関連づけた民間保険の見直しの方向性かと思います。
ご参考になれば幸いです。
今年もよろしくお願いいたします。
12月に入りました。
今年も残り1か月ですね。
先日の衆議院選で国民民主党が掲げた「年収103万円の壁」の問題について話題になっています。
国民民主党は、「手取りを増やす」をスローガンに、最低賃金の上昇にあわせて非課税の対象となる額を103万円から178万円に引き上げるべきだと主張しています。
そしてこれを受けて石破首相は11月29日の所信表明演説で「年収103万円の壁の引き上げは25年度税制改正で議論し引き上げる」と述べました。
なので178万円になるかはともかく、非課税額が現在の103万円からそれなりに引き上げられるのだろうと考えられます。
今回は、「103万円の壁」に関連する、税・社会保険料を巡る「年収の壁」と諸問題について解説したいと思います。
<税・社会保険料を巡る「年収の壁」>
| 年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 | 配偶者特別控除の減少 |
|---|---|---|---|---|
| 150万円~ | かかる | あり | ||
| 130万円~150万円 | かかる | なし | ||
| 106万円~130万円 | かかる | かかる 従業員51名以上の場合 | なし | |
| 103万円~106万円 | かかる | なし | ||
| 100万円~103万円 | かかる | なし | ||
| 0~99万円 | なし | |||
※日経新聞の図表より
(注)住民税の基準額は自治体ごとに異なる
【現状の問題点】
1.103万円を超えると企業が配偶者手当を打ち切るケースが多いこと。
2.アルバイト学生は103万円を超えると特定扶養控除がなくなり親の税負担が増えること。
3.従業員51名以上の企業に勤めている場合、年収106万円を超えると社会保険に加入する義務が発生すること。
4.これらにより働く時間をあえて抑えようとする人が多いこと。
国民民主党が示す資料によれば、課税最低限度額を103万円から178万円に引き上げることで国民にとって一定の減税効果があるとしています。
その減税効果は、年収200万円の人で8.6万円、300万円の人で11.3万円、500万円の人で13.2万円と試算されています。
私は年収の壁を引き上げることでの手取り額UPは、私たち国民にとって一定のメリットがあると感じ、国民民主党が主張する案に賛成です。
減税に対する財源をどうするかという問題も、手取り額がUPすることで消費も増えて減税分くらいは埋まるのではないでしょうか。
また働き控えによる人手不足にもそれなりの効果が出て、生産性向上により企業業績もよくなり法人税収が増えることも税収UPにつながるのではないでしょうか。
年収の壁が引き上げられても企業は人件費の関係で必ずしもパート従業員の労働時間を増やそうと考えないかもしれません。
でもパート従業員側は、壁が引き上げられれば例えばもう1つ別のパート先を見つけて労働時間を増やしたり、または労働時間をより多く確保できる企業へ転職したりするかもしれません。
こうしたことで、従業者の賃金上昇、消費増、生産性向上による企業業績UP、将来的な税収増と従業員、企業、国、それぞれにメリットが出てくるのではないでしょうか。
非課税額103万円は1995年まで物価上昇に合わせて引き上げられていて、その後は約30年間、103万円のまま据え置かれています。
ここにも失われた30年の痕跡があるわけです。
私はやはり30年間も据え置かれているのは異常だと思うので、103万円からの引き上げは賛成します。
年内には政府の税制改正大綱が決定し、来年2025年には何らかの税制改正がされるはずです。
一般労働者にとっても、経営者にとっても大きくかかわる話題なので今後の動向を注目していきたいですね。
今月もよろしくお願いいたします。
11月に入りました。
早いもので今年も残り2か月ですね。
そんななか10月27日に衆議院選挙の投開票が行われました。
結果は以下の通りでした。
|
与党 今回の議席数(公示前の議席数) |
野党 今回の議席数(公示前の議席数) |
|
|---|---|---|
| 自民 | 191(247) | |
| 公明 | 24(32) | |
| 立民 | 148(98) | |
| 維新 | 38(43) | |
| 国民 | 28(7) | |
| れいわ | 9(3) | |
| 共産 | 8(10) | |
| 参政 | 3(1) | |
| 日本 | 3(0) | |
| 社民 | 1(1) | |
| 無所属 | 12(23) | |
| 計 | 215(279) | 235(186) |
<結果の概要>
・自民党がマイナス56人と大幅に議席数は減らしたこと。
・連立政権を組む公明党と合わせても215議席で過半数233議席を割り込んだこと。
・立憲民主党と国民民主党が大幅に議席数を増やしたこと。
・維新が議席数を減らし今までの勢いが止まったこと。
・れいわ、参政党が議席数を伸ばし、日本保守党が3議席を確保したこと。
石破首相は、与党の過半数確保を勝敗ラインと位置付けて選挙にのぞみましたが、結果は惨敗となりました。
自公の過半数割れは政権交代が起きた2009年以来、15年ぶりのことです。
支持率が高まりやすい政権発足直後に衆議院解散に踏み切りましたが、自民派閥の政治資金問題や旧統一教会との関係による逆風に勝つことができませんでした。
選挙終盤には自民党から一部の非公認候補の党支部に活動費として2,000万円を支給したことが発覚し「政治とカネ」をめぐる怪しさが上乗せされました。
党支部への資金なので候補者へは資金は流れないとのことでしたが、このような事情は国民は理解できません。
李下に冠を正さず。疑わしいことはしない。
政治家のみなさまにはこうした社会人であれば常識的な感性も身につけてもらいたいと思っています。
与党が過半数割れしたことで今後の政権運営は不透明になりましたが、ある意味、自民党にとっては国民から厳しいお灸を据えられたことで緊張感のある政治活動や国会運営ができるようになるのではないでしょうか。
また今回の選挙で私が注目しているのは、れいわ新選組、参政党、日本保守党などのSNSやネットの親和性の高い新しい政党(政治団体)が議席を増やしたことです。
投票率は53.85%と戦後3番目の低さであったのにもかかわらず、こうした新しい政党に票が集まったことは、今まで選挙で投票していた層が、投票先を新しい政党に乗り換えたということでもあります。
こうしたSNSやネットの影響力は今後もますます高くなることが予想されるので、従来とは異なった投票行動が進んでいくのではないでしょうか。
SNSやネットからの情報はデマだったり極端な偏りがあったりすることもありますが、従来の大手メディアにはない多様性があることも事実です。
私は、社会というのは大局的にみれば良い方向に向かっていくと思っています。
今回の選挙結果も、日本が社会が私たちの生活が、より良い方向に向かっていく転機となるように願っています。
石破総理におかれてはせっかく総理になったわけですから、反対勢力やネガティブな報道に負けず、もういろいろと開き直って強いリーダーシップを取ってもらいたいですね。
今月もよろしくお願いいたします。
10月に入りました。
9月27日に実施された自民党総裁選は、石破茂氏が接戦を制し、新総裁に選出されました。
本日10月1日に臨時国会が召集され、首相指名選挙で首相に石破氏を選び、石破総理大臣が誕生します。
石破氏をリーダーとする新政権においては、しっかりと日本の舵取りをしてもらいたいと期待しています。
そんななかメジャーリーグの大谷選手のレギュラーシーズンが終了しました。
今年は打者に専念し、打率310、ホームラン54本、打点130、盗塁59と大活躍をしてくれました。
そしてホームラン王と打点王の2冠王を獲得し、所属するドジャースは地区優勝を決めました。
私は毎朝、仕事の前に大谷選手の試合経過をネットでチェックしダイジェスト版の動画を観たりして、大谷選手の活躍ぶりを励みにさせていただきました。
一人の野球ファンとして大谷選手の活躍は誇りに思います。
思えばシーズンはじめには通訳に20億円以上を横領されたことが発覚し、新天地のドジャースでのはじまりは大きな不安がありました。
大谷選手にとって身近な存在の裏切り行為は、金額以上に精神的なダメージは大きかったと思います。
そんな苦難を乗り越えてのこの活躍です。
身体能力はもちろん精神力も並大抵ではないと感心しています。
大谷選手が残している言葉に次のようなものがあります。
「イライラしたら負けだと思っています。いちいち他人にイラついて不機嫌になるのは人生損する。イラつくときは、またひとつ自分の強みが発見できた、そう思えたらストレスもたまらない。あの人いつも時間に遅れてくるな、と思うのは自分はいつも時間を守るから。レスが遅いと思うのは、自分は即レスしているから、周りに配慮がないなと思うのは、自分はいつも周りに気配りをしているから。そう思うようにしたら他人にイライラすることが激減した。イライラは自分の強みを再認識するチャンスなんです。」
どうやってこうした心のあり様を身に着けたのか。
私よりも20歳以上も若い大谷選手ですが、その精神性は本当にすばらしいと思っています。
この言葉は、親、教員、上司、経営者など、幅広い層で役立つ言葉だと思います。
私も未熟ながら大谷選手のこの精神性を見習いたいと思います。
メジャーリーグには、1シーズンに40ホームラン以上と40盗塁以上を同時に達成した選手集団の40-40クラブというのがあります。
これまで過去に5人ですが、今年、大谷選手が加わり6人になりました。
40-40でも偉大な記録ですが、今年の大谷選手は、40-40を遥かに超える54-54を達成しています。
これを受けてメジャーリーグでは50-50クラブができました。
もちろん過去には誰も存在せず、現在、大谷選手のみです。
120年以上の歴史を持ち、最高の野球選手が世界から集まってくるメジャーリーグで大谷選手ただ1人です。
現在50-50クラブのメンバーは大谷選手1人だけ。
10年後も20年後も1人だけのままかもしれません。
私がこの世からいなくなった50年後も、大谷選手自身がこの世から去った100年後も1人だけのままかもしれません。
そんなメジャー球界史に残る偉大な記録を作ってくれた大谷選手は日本スポーツ界の誇りです。
これからポストシーズンが始まります。
大谷選手にはシーズン中と同じように活躍してもらい、是非ワールドチャンピオンを目指してもう少しの間頑張って欲しいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
9月に入りました。
私の子供たちは長い夏休みが終わり今日から学校がはじまります。
8月14日、岸田文雄首相は9月に予定されている自民党総裁選に立候補しないと表明しました。
これにより2021年10月からスタートした岸田政権は3年で終了することになります。
そして新たな自民党総裁を選ぶ総裁選の日程が、9月12日告示、9月27日投開票と決まりました。
9月27日には新しい自民党総裁と内閣総理大臣が決定します。
今回の総裁選は立候補を目指す自民党議員が多いです。
今名前が挙がっているのは、石破茂氏、加藤勝信氏、上川陽子氏、斎藤健氏、野田聖子氏、小泉進次郎氏、河野太郎氏、小林鷹之氏、高市早苗氏、林芳正氏、茂木敏充氏の11名です。
党所属国会議員20人の推薦がないと立候補できないので、この中の誰が立候補できるかはまだ分かりませんが、この11人の中から新しい内閣総理大臣が誕生する可能性が高いですね。
私としては、若手か女性になってもらいたいと個人的には思っています。
40代の総理大臣、女性の総理大臣、どちらも話題性十分で世界が注目してくれると思います。
また従来の古い政治を変えるきっかけを作ってくれるような期待感もあります。
女性総理大臣なら日本史上初です。
40代も初かと思って調べたら、伊藤博文氏の総理大臣就任時の年齢は44歳でした。
ただ小泉進次郎氏が総理大臣になれば就任時年齢が43歳なので日本史上で最年少となりますね。
総裁選のあとは、衆議院の解散、衆議院選挙が控えています。
総裁選直後に解散し、10月末から11月初旬に衆議院選挙が行われるのではないかと予想されています。
その場合、体制が一新された自民党が他の野党に比べて有利な選挙戦になるでしょうね。
また11月5日にはアメリカの大統領選挙が控えています。
大統領戦もトランプ氏かハリス氏どちらが勝つか分からない状況です。
今年2024年の後半は日米両国で政治が大きく動き、その結果で経済にも大きな影響を与えると考えています。
今後の選挙の動向に注目しながら変化に柔軟に対応していきたいと思っています。
自民党総裁選は私たちには投票権がありませんが、その先の衆議院選挙では有権者となります。
今後の日本を担う政治をどの政党に、誰に任せればよいのか、しっかりと見極めて投票行動を取りたいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
8月に入りました。
東京は梅雨明けしてから連日猛暑が続き、夕方にはゲリラ豪雨となることも多く、外に出る仕事をしている身としては天候を気にしなければならない日が続いています。
去る6月の経済誌の記事がきっかけですが、金融庁は某大手保険代理店向けの生命保険会社による広告出稿について実態調査に動き始めました。
一部の大手保険代理店が生命保険会社から相場よりも高い多額の広告費を受け取っており、各生命保険会社からの広告費の多寡によってお客様に勧める保険会社や商品を左右していた懸念があるためです。
広告は代理店が運営する店舗やWebサイトに掲載されています。
分かりやすく解説すると以下のようなことです。
ある保険代理店が、A社・B社・C社・D社・E社の5社の生命会社の代理店をしていたとします。
そして広告料を1番払ってくれているのがA社、2番目がB社、3番目がC社、D社とE社を広告料を払っていないとします。
そうするとこの代理店はお客様の意向や商品の競争力に関係なく、A社商品を優先的に販売し、次にB社、その次にC社の商品を勧め、広告料を払わないD社・E社の商品はお客様に勧めず販売しない、ということです。
新聞記事によれば、同社は特定の保険商品を販売すると営業担当者の評価を割り増しにするキャンペーンを実施し、多額の広告費を支払う保険会社の商品が対象になっていたとのこと。
そのため割り増し評価する保険商品を優先的に勧める動機が働きやすくなり、お客様目線での公平な販売をゆがめていたという懸念がもたれています。
これが本当ならば複数の保険会社を扱う乗合保険代理店の社会的な信用や信頼を失いかねない極めて不正な企業行動だと思っています。
今後、金融庁の調査で実態が明らかにしていただき、不正があれば業界全体で業務改善や再発防止に努めてもらいたいと思います。
会社経営というのは、結局のところ経営者の日々の判断の累積した結果であると考えています。
そしてその日々の判断は、「人間として何が正しいかを判断基準とする」ことが大切だと京セラの創業者である稲盛和夫氏は説いています。
保険会社も代理店もまずは経営者が率先垂範して「人間として何が正しいか」を判断基準として行動し、それを他の役員・従業員も一人ひとりが判断基準を認識し、正しい仕事をしていかなけばならないと思います。
保険業界に携わる一人として、社会の一員として、私自身も肝に銘じたいと思います。
今月もよろしくお願いいたします。
7月に入りました。
東京は梅雨らしい天気が続いており、今日も朝から雨が降っています。
そんななか東京都知事選がはじまっています。
すでに6月21日から期日前投票がはじまっており、投票日は7月7日(日)です。
私はまだ投票していませんが、近々、期日前投票に行こうと思っています。
今回の都知事選挙ですが、報道されている通り、大変カオスな状況となっています。
まず立候補者が56人で過去最多となり、最大48名を想定していた選挙ポスター用の掲示板の掲示スペースが足りなくなってしまいました。
それで東京都の選挙管理委員会はどうしたかというと、あぶれてしまった候補者8名にはクリアファイルと画鋲を配り、掲示板の外側どこでもいいので貼っていいという対応を取りました。
これはNHK党を含む立花孝志氏の関連団体が、今回24人の候補者を擁立したことが大きな要因になっています。
またNHK党は今回、一定の金額(25,000円)を寄付すれば、都内14,000か所にあるポスター掲示板のうち1か所を寄付者が独自に作成したポスターを最大24枚貼れるという活動もしました。
このことで一部では不適切な描写のポスターが貼られ、警視庁が警告を行ったりしています。
私も有権者の一人なので動画で候補者の政見放送を20人くらい見ましたが、「なんだこれは!」と驚いたり呆れたりする内容の候補者が多数いました。
立候補の動機が当選することではなく、宣伝や広告、資金集めに変容しているとも言えます。
もし地方に住む年頃のお子様が東京に行きたいと言ったら、「あんな人がいっぱいいるようなところには行かせられない。」と反対する親御さんもいるのではないかと思えるほどでした。
東京都知事選には、一部の被選挙権を失っている人を除き、30歳以上の日本国民で供託金300万円を支払えば、誰でも立候補できます。
立候補要件のハードルがそれほど高くないことも今回のような乱立の原因になっているという向きもあります。
今回の都知事選を見て、都民はどう考えるのか興味があります。
私は、ポスター掲示板はあってももっと数を減らしていいと思いますよ。
例えば各市町村役場前と主要な駅前に1か所程度でよいと思います。
現に今回も候補者は多いですがポスターを貼る人員が追い付かず、掲示板はまだ空白ばかりです。
掲示板を作成、設置コストが無駄だと思います。
今はネットでの記事や動画があるのでそれで代用は十分にできます。
また候補者の乱立ですが、私はこれも「あり」だと考えます。
都民が都政に関心を持つためには多少の刺激があった方がよいと思っています。
現在は、東京だけでなく、日本全体で多様性をどう考えるかの過渡期です。
日本全体で人口が減り、外国人を受け入れるかどうかという議論も多様性を考える1つです。
多様性が広がると混乱を生むのか。
混乱を恐れて多様性を排除するのか。
それとも多様性と秩序は両立できるのか。
私は多様性が広がることでさまざまな混乱が生じると思いますが、徐々に混乱を克服し、一定の秩序が形成できると信じています。
それが私たち日本人が未来に向けて発展繁栄していくために大切な挑戦だと考えています。
東京都の知事は一人だけです。
次の東京都知事は誰になるのか。
私自身も都民の一人として7月7日の投票結果を楽しみに待ちたいと思います。
今回の都知事選立候補者の一覧を載せておきます。
⇒ 東京都知事選挙立候補者一覧
今月もよろしくお願いいたします。
6月に入りました。
東京ではここ最近、曇りや雨の日が多く梅雨に時期が近いと思わせる天気が続いています。
私は28歳で生命保険会社に転職し34歳で保険代理店として独立して現在51歳になりますので、生命保険業界に23年身を置いています。
その間、世の中の環境はいろいろと変化していますが、20年前から議論されていることがあります。
それは生命保険不要論です。
生命保険の必要性についてたびたび賛否が分かれますが、生命保険不要論も根強くあります。
生命保険は要らないと考える方の理由は以下のようなものです。
・若くして亡くなることは滅多にない。
・生命保険なんて宝くじを当てるようなもの。
・公的な遺族年金があるので十分。
・貯金をしておけば困らない。
こんな主張がネットでもよく見かけます。
私は多くの人にとって生命保険は必要だと考えますが、実際のところどうなのかを客観的に考えてみたいと思います。
生命保険文化センターの2022年度「生活保障に関する調査」によると、日本で生命保険に加入している人は、男性では77.6%、女性では81.5%となっています。
日本人の約80%の人が生命保険に加入していることになります。
これを見ると生命保険に加入している人が圧倒的に多数を占めていると言えます。
何故、それだけ多くの人が生命保険に加入しているのでしょうか。
私は以下のような世帯にとっては生命保険は必要だと考えています。
・結婚していて小さな子供がいる。
・妻が専業主婦。
・夫の労働収入のみで家計を支えている。
・不動産収入やその他権利収入などは特にない。
こういう世帯は多いのではないでしょうか。
若い年齢で亡くなることは滅多にないと言われることがありますが実際はどうなのでしょうか。
以下は厚生労働省が発表している令和4年の簡易生命表です。
令和4年簡易生命表(男性)
令和4年簡易生命表(女性)
これによると、現役世代と考えてよい、65歳までの日本人の生存率は、男性が89.6%、女性が94.4%です。
つまり65歳までに亡くなる人は、男性が10.4%、女性が5.6%です。
確かに死亡率は高くはないですが、滅多にないと言うほど低くもないのではないでしょうか。
例えば小学校のときに同じクラスに30名いたとします。
65歳のときにクラス会をしたら、クラスの中の2~3人はすでに亡くなっているということです。
確かに確率は低いですが、私の印象としては、自分自身がこの2~3人に絶対に入らないかと考えると、確信は持てないレベルです。
少なくとも宝くじで当たる確率よりは断然高い確率です。
また夫一人の収入で家計を支えているような上記のような世帯では、夫が亡くなったあとの生活費や子供の教育費を貯金や遺族年金だけで賄うことは現実的にはできません。
だからこそ生命保険は他で代替えできない資産として必要なのだと考えています。
35歳の夫が家族のために月10,000円の生命保険に加入したとします。
子供が成人するまでの20年間、毎月10,000円を支払うと、20年間の保険料総額は10,000円×12か月×20年で240万円です。
このくらいの金額であれば、水道光熱費や携帯電話などの通信費などの生活インフラに必要なコストと同様に、私は家庭にとって必要なコストだと考えています。
そのうえで、それでも生命保険は不要と考える場合には、生命保険に加入しなくてよいと思います。
しかし実際の統計や正しい情報とはいえないような一部の否定的で極端なネット記事やインフルエンサーの意見などを鵜呑みにして、安易に生命保険は不要と判断するのはやはりリスクが高いと思います。
自分にとって家族にとって、生命保険は必要なのか不要なのか。
家族構成やライフスタイルなどによっても必要性やニーズは個々に違います。
そのあたりを十分に考えながら生命保険については検討されることをお勧めします。
ご参考になればと思います。
今月もよろしくお願いいたします。
本日は5月1日です。
連休の谷間ですがいかがお過ごしでしょうか。
私は連休中もカレンダー通りに仕事をしています。
4月28日、衆議院の3つの小選挙区(東京15区・長崎3区・島根1区)で補欠選挙の投開票が行われました。
結果は、立憲民主党がすべて勝利。
政権与党の自民党は、不戦敗も含めて全敗しました。
衆議院は2025年10月30日に任期満了を迎えるため、それまでには必ず衆議院選挙が行われます。
今回の補選3区は、今後の政局に大きな影響を与えるのではないでしょうか。
今回の選挙結果は、自民党派閥の政治資金問題が自民党不信につながった結果だと思います。
自民党安倍派や二階派が政治資金パーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載しなかった疑いがあるとして、東京地検特捜部は政治資金規正法違反容疑で現職国会議員を逮捕しました。
パーティー券の販売ノルマ超過分を所属議員にキックバックさせており、安倍派の収支報告書に記載されていない「裏金」は2018年~22年の5年間で約6億円とされています。
これを受けて自民党は連休明けから政治資金規正法をより透明度が高く厳格な方向で改正するとしています。
私は法を改正しても政治不信や裏金などの不正がなくなるとは思えません。
法律で規制する以前に、国会議員一人一人が、人としてどうあるべきかを自問自答し、心のあり様を改めるべきだと考えます。
かつて京セラの創業者である稲盛和夫氏は、会社経営の根本を「人として何が正しいかを判断基準とする」と説き実践されました。
また親しくしている経営者は、居酒屋で知人の経営者が一人で飲んで領収証をもらっている姿をみて「いつも偉そうなことを言ってるけどセコいな」と軽蔑していました。
また公私ともにお世話になっている社長は、経営者の集まりで講演をして数万円の謝礼をもらったあと、その謝礼を会社に持ち帰り適切に処理されたと言います。
私自身も自分の会社でお客様本位の業務運営方針を掲げ、その第1項は、「当社は、コンプライアンス(法令等順守)を業務の基盤とし、人間として何が正しいのかを判断基準としながら、お客様目線で価値判断を行い、お客様の利益を第一に考えて業務に取り組みます」と稲盛氏の箴言を盛り込みながら日々実践しています。
中小企業の経営者と従業員は、日々、倫理観や道徳観を忘れないように努力しながら、一生懸命に仕事に向き合っています。
なので国の政治を代表する国会議員こそ、法律でしばられる以前に、一人一人が、恥ずかしいことはしない、おてんとうさまは見ている、という人として当たり前の価値観で日々の生活や政治活動をしていただきたいと思います。
そうすれば、裏金やキックバックみたいな言葉からして怪しい悪習慣もなくなり、私たちの政治不信も少しは緩和されると思います。
与党・野党にかかわらず国会議員のみなさまには国民の手本となるような倫理観や道徳観を持っていただきたいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
4月に入りました。
東京は3月下旬でも気温が低い日が続き桜の開花が遅れていましたが、ここ数日、急に気温が上がり、やっと桜が咲き始めました。
先月のレポートでは日経平均株価が最高値を更新したことを取り上げましたが、今回は日銀の金融政策について取り上げたいと思います。
3月19日、日銀は金融政策決定会合で、マイナス金利政策の解除を決めました。
政策金利を引き上げるのは、17年ぶりです。
また長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)の撤廃も決め、2013年に始まった大規模緩和は終了しました。
金融政策は正常化に向けて新たな段階に入り、日本経済の復興は、先月の日経平均株価の最高値更新に続き、第二段階に入ったと考えています。
今回の金融政策転換は、政府・日銀の物価安定目標である2%が定着しつつあることが要因です。
デフレ脱却に向けて日銀が異次元緩和を始めたのが2013年。
目標とした物価上昇率2%は当初想定した2年程度では実現できず、10年目の2022年にようやく到達しました。
これは政府や日銀の政策が功を奏したというより、コロナ禍とウクライナ危機による世界的なインフレの波が押し寄せた外圧が大きな要因でした。
日本が海外から輸入する食料や資源価格の高騰に加え、円安が重なり、インフレ化に拍車がかかったのでした。
マイナス金利解除後、各銀行では預金金利を引き上げる動きがありますが、貸出金利についてはまだ動きはありません。
ただ今後はやはり貸出金利についても徐々にではあっても引き上がっていく方向にはあると考えます。
家計最大の借入金である住宅ローンは右上がりを続けています。
住宅金融支援機構によると、2022年度の住宅ローン残高は215.9兆円で、1989年度の2倍になっています。
懸念があるとすると、変動金利のローン金利の引き上げです。
住宅ローン利用者の70%超が変動型を選んでいます。
マイナス金利解除後も変動金利の基準となる短期プライムレート(短プラ)は、当面、据え置かれる見通しですが、これについても将来的には引き上がっていくことになるのではないでしょうか。
ここ数年、不動産の物件価格は上がり続けてきました。
金利引き上げの影響により、買い控えや物件価格が抑制されることになるのか。
または金利引き上げでもこのまま不動産価格は上がり続けていくのか。
このあたりは、今後の状況の推移を見守りたいと思っています。
いずれにしてもここ10年間くらい、変動金利の住宅ローンが中心でしたが、住宅ローンの組み方については変化が出てくるかもしれないですね。
これから住宅購入をお考えの方にとっては固定か変動かの判断は迷うところだと思います。
金融政策の転換により、日本もゼロ金利や超低金利の時代から、金利のある世界に変化していくことになります。
私たちもこの変化に柔軟に対応していく必要がありますね。
3月に入りました。
年度末を迎え忙しくされている方も多いと思います。
2月22日、日経平均株価がついに史上最高値を更新しました。
バブル期の1989年末につけた最高値38,915円を上回り、初めて3万9,000円台に乗せました。
およそ34年ぶりの更新です。
私は今51歳です。
社会人になってからずっと失われた30年で過ごしてきた身からすると、現役のうちにはじめてこうした明るい話題のなかで仕事ができることは感慨深い思いです。
株価は高まっても、今回はバブルではないと言われていますね。
報道やデータからの抜粋ですが、今回の株高がバブルではなく、企業の実態をある程度正当に反映したものと考えられるいくつかの指標や根拠を挙げてみたいと思います。
出典は主に日経新聞です。
1.1株当たりの利益が増加
日本企業の1株当たりの利益は2012年と比べて2.8倍と企業の稼ぐ力が強化されていること。
PER(株価が1株当たり利益の何倍になっているかの指標)が16.5倍とまだまだ割高とはいえないこと。
バブル期のPERは61.7倍。これを見るとバブルはやはりバブルだったのだと思います。
2.企業統治改革の確かな推移
資本効率の向上策や株主還元策(配当増や自社株買いの増加)の取り組みにより株主のメリットを向上させていること。
資金に余裕のある企業が市場から自社株を買い取ることで、発行株数が減り、株主の1株あたりの利益配分が増えることが株主のメリットになります。
3.デフレ脱却の兆し
長いデフレから脱却するという期待感から海外からの投資をさらに呼び込む可能性があること。
現在の日本の消費者物価は3%前後で、物価上昇がやや落ち着いた米国とほぼ同水準。
インフレになると現金の価値が目減りするため、株や投資信託などの高いリターンが期待できる金融商品へ資金が流入しやすくなります。
4.個人マネーの株式市場への流入
新NISAの影響が大きく今後もますます個人マネーの流入が増加する可能性が高いこと。
貯蓄から投資へが日本人のマインドとして浸透しつつあること。
5.国内基幹産業企業の成長性
以下は日本の時価総額トップ10社の1989年と2024年の比較です。
30年以上も経っているので当たり前といえば当たり前ですが、メンバーは大きく変わっています。
<時価総額上位10社の推移>
| 1989年末 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 1位 | NTT 23兆円 | トヨタ自動車 57兆円 |
| 2位 | 日本興業銀行 15兆円 | 三菱UFJ銀行 18兆円 |
| 3位 | 富士銀行 10兆円 | 東京エレクトロン 17兆円 |
| 4位 | 三菱銀行 9兆円 | キーエンス 17兆円 |
| 5位 | 三和銀行 8兆円 | ソニーグループ 17兆円 |
| 6位 | 野村証券 7兆円 | NTT 16兆円 |
| 7位 | 新日本製鉄 5兆円 | ファーストリテイリング 14兆円 |
| 8位 | 三井銀行 5兆円 | 三菱商事 14兆円 |
| 9位 | 関西電力 5兆円 | ソフトバンクグループ 13兆円 |
| 10位 | 太陽神戸銀行 4兆円 | 信越化学工業 13兆円 |
| 10社合計 | 91兆円 | 196兆円 |
これを見ると日本経済を支える基幹産業が通信・金融から製造業に変化していてまだまだこれからも成長していくという期待感があります。
また上位10社の時価総額合計も1989年と比べ2024年は2.15倍に成長しており、株価がバブル期に戻ったというより、日本企業がそれぞれに地道に努力してきた結果の成長であると感じています。
ちなみに米マイクロソフトの時価総額は円換算で約450兆円です。
日本企業トップ10社の時価総額を合計しても遠く及ばないので、やはり日本とアメリカの差は大きいです。
そうはいっても日本は日本で長い間かけて成長はしてきていると思います。
もちろん企業に集う役員、従業員みんなの努力の結果でもあります。
株価は経済指標の1つに過ぎず、今後、上がるのが下がるのかは結局のところ分かりません。
ですがこうした公表されているデータを見ると、明るい材料であることは間違いないと思います。
失われた30年からの脱却。
ニッポン反転。
こうしたよい流れに乗って、年度末をしっかりと乗り切りたいものです。
そして日本経済が、私たちの暮らしが持続的によくなっていく、明日に希望の持てる社会が来ることを願っています。
今月もよろしくお願いいたします。
2月に入りました。
2月は日数が少ない月ですが、今年は閏年なので29日までですね。
年明け1月から新しいNISA制度がスタートしました。
お客様からの問い合わせやご相談なども多く、関心が高い話題なので、今回は新NISAについて解説させていただきます。
2024年からの新しい制度でのNISAは、年間の投資額が拡大されたこと、非課税保有期間が無期限化されたこと、制度が恒久化されたことがポイントですが、これからの少子高齢化時代の自助努力による積立投資として非常にメリットのある制度だと考えています。
ご関心のある方は是非活用いただくことをお勧めします。
目的やメリット、特徴など以下にまとめましたのでご参照ください。
<主要な目的>
1.65歳以降の生活財源の計画的な準備
2.お子様の教育資金の積立て
3.不動産購入など中長期(5年以上)の積立投資
4.インフレに対応すること
<メリット>
1.長期投資の複利効果により高い運用成果が期待できること。
2.積立投資で購入単価を平準化することで投資リスクを抑制できること。
3.資産タイプ(国内株式、外国株式、債券、不動産など)の分散により安定的な運用が期待できること。
4.長期運用で時間を味方にすることで少額でかつリスクを抑制しながら積立てができること。
5.運用益(売却益・配当/分配金)が非課税となること。
6.金融庁の基準を満たした投資信託等に選別されているので投資先に一定の信頼性があること。
<デメリット(リスク)>
1.元本保証はないので、運用の結果しだいで投資した資金が元本割れするリスクがあること。
2.短期(1年2年など)では、運用成果があまり期待できないこと。
<概要>
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限化 | 無期限化 |
| 非課税保有限度額(総枠) | 1,800万円 | 1,200万円(内数) |
| 口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
| 投資対象商品 | 投資信託 | 上場株式・投資信託等 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
※つみたて投資枠と成長投資枠は併用可
※詳細 NISA早わかりガイドブック(金融庁発行)
<口座開設と購入の手順>
1.金融機関(銀行・ゆうちょ銀行・証券会社(ネット証券含む)で専用口座を開設
窓口で「NISA口座を作りたい」と相談すれば案内してくれます。
すでにNISA口座を持っている方、NISAで金融商品を購入されている方は自動的に新NISA向けへ変更されます。
2.購入する金融商品を選択して購入
【初心者向けのお勧め金融商品】
「つみたて投資枠」を活用し、全世界の株式に分散投資できるインデックスファンドの投資信託
※通称:オルカン(オールカンパニー)
全世界といってもアメリカを中心とした先進国の優良企業への株式投資の割合が高いことが一般的
積立投資の方法は、NISA以外にも、イデコや変額保険、変額個人年金などがあります。
より詳細をお聞きになりたい方は、お気軽にお問合せください。
2023年12月のNISA利用者の割合は約18%だそうです。
新NISAのスタートにより、利用者がこれからも増えていくと考えています。
NISAだけでなく何かしらの将来に向けた積立投資をしていたか、それとも何もしなかったかで、10年、20年で考えると大きな差が生じてしまいます。
NISAは、店舗では1,000円から、ネットでは100円からはじめられます。
資産や収入がそれほど多くない方でも気軽にはじめられる制度です。
まずははじめてみることをお勧めします。
今年もよろしくお願いいたします。
あけましておめでとうございます。
2024年、令和6年になりました。
今年は昭和99年になるそうです。
昭和100年に向けて、私個人も会社も日本全体も飛躍の年になることを願っています。
年末に「昭和99年ニッポン反転 日本診断」というシリーズ記事が日経新聞に掲載されました。
前向きで希望が持てる非常によい記事でしたのでポイントをご紹介します。
記事では四半世紀続いた日本の停滞がいよいよ反転し、日本がNO.1に再興すると説いています。
1.「再訪したい国」世界一
米国大手旅行雑誌の読者投票で
10月の訪日外国人数はコロナ前を超える251万人に
観光が地域経済を活性化。
2.世界で駆けるアスリート
大谷翔平選手をはじめ世界で活躍する日本人スポーツ選手
今年夏に開催されるパリオリンピックでの日本人選手の躍進に期待
スポーツコンテンツによる経済効果大
3.日本株に反転に兆し
日経平均、33年ぶり高値の33,000円台を回復
新NISAスタートで投資行動がさらに加速
バブル期最高値38,915円超えにも期待
4.半導体産業の再興
台湾のTSMC熊本工場が稼働
半導体の製造装置や素材分野で高シェア
半導体製造装置の各国シェア:米国35% 日本31% 中国9%
主要半導体部材の各国シェア:日本48% 台湾16% 韓国13% 米国9%
昨年は当社のお客様企業でも国内工場の増設や海外拠点の進出など、設備投資がすでに進んでいる印象を受けます。
今年の干支は、甲辰(キノエタツ)です。
甲は十干の一番最初で物事のはじまりという性格があり、辰は成長という意味を持つそうです。
これまでの努力が実り飛躍する。
何か新しいことに挑戦するにはよい年。
このような年回りでもあるそうです。
ニッポン反転。
すごくいい響きだと思います。
今年一年、明るく前向きに、よい年になるように願っております。
今年もよろしくお願いいたします。
12月になりました。
今年も残すところあと1か月ですね。
東京は気温が下がりインフルエンザも流行っていますので体調管理に努めたいと思います。
ここ数か月、米ドル建て一時払終身保険の販売が好調です。
背景には、米国金利の引き上げにより保険会社の予定利率や積立利率が上昇したことがあります。
ただし外貨建て保険については、銀行窓販等での高齢者のお客様の契約をめぐってのトラブルも多いと聞きます。
なので今回は外貨建て保険の1つである米ドル建て一時払終身保険について解説したいと思います。
この商品は、米ドル建ての保険料を円換算して一時払いで円で支払い、一生涯の死亡保障を準備する生命保険です。
ドルベースでの死亡保険金や解約返戻金は契約後、増えていきます。
この増える割合が円建て商品に比べて高いことが米ドル商品が選ばれる理由です。
主な加入目的は、1.生命保険金の非課税枠を活用した相続税対策、2.資産運用、となります。
また多くの場合、健康告知が不要で高齢者や既往歴がある方でも契約できることも選ばれやすい要因の1つです。
ですが、ドルベースの積立利率が高くても、為替リスクはあります。
死亡保険金や解約返戻金は、通常、円で受取りますが、契約時よりも円高になっていた場合には、当初想定していた金額が円ベースでは目減りするリスクがあります。
そのため米ドル建て一時払終身保険をご検討されるときは、以下のポイントに留意されるとよいと考えます。
1.契約後の死亡保険金や解約返戻金の推移
2.将来、死亡保険金や解約返戻金を受け取るとき、どの程度の円高まで円ベースでの金額がマイナスにならないか。
この2点をチェックすれば判断を誤ることは抑えられると考えます。
現在は、積立利率が高いため、円高リスクへの抵抗力が高く、そのため生命保険金の非課税枠を活用した相続税対策をお考えのお客様へは、比較推奨商品の第一候補としてこの種の保険をお勧めしています。
ご関心のある方はお気軽にお問合せください。
今月もよろしくお願いいたします。
11月に入りました。
今年も残り2か月、月日が過ぎるのは本当にあっという間です。
先月、中東地域で深刻な紛争が起きてしまいました。
10月7日、パレスチナのイスラム組織ハマスが、ロケット弾や戦闘員の侵入によってイスラエルへ大規模な攻撃を仕掛け、一般人を含む多くのイスラエル人が犠牲になりました。
これを受け、イスラエルはすぐさま反撃し、ガザ地区への空爆により、一般人を含む多くのパレスチナ人が犠牲になっています。
そして先日、イスラエルのネタニヤフ首相は、「戦争の第二段階」に入ったと述べ、ガザ地区の北部でイスラエル軍による地上作戦が開始されている可能性があることが分かりました。
また今朝の報道では、イスラエルがガザ北部の難民キャンプを空爆し、新たに多数が犠牲になったとのこと。
連日SNSを通じて小さな子供が犠牲になった痛ましい映像が目に触れ私自身も大変ショックを受けています。
戦争や紛争というのは、古今東西、ある意味では、互いの国や組織で互いに譲り合うことのできない大儀があるのだと思いますが、罪のない民間人の犠牲というのは、どのような理由も言い訳にならず、大儀はないと私は思います。
多数の市民を殺害し、人質を連れ去ったハマスの無差別テロは許されません。
しかし高い塀に囲まれ、水道や電気も使えない状態になっている逃げ場のないガザ地区で、罪のないパレスチナの民間人を犠牲にする報復攻撃も同じように許されない行為だと考えます。
当事国の指導者には、人道支援や停戦など、これ以上の民間人が犠牲が拡大しないような方策を早急にとってもらえることを強く願います。
今回の紛争をめぐる日本の立ち位置というのは非常に難しいことも事実です。
イスラエル側は米国を後ろ盾としており、日本にとって米国をはじめとした西側諸国は、政治・経済・安全保障の面で密接な関係であり、この関係なくして日本は成り立ちません。
一方、エネルギー資源のない日本は、石油を100%輸入に頼っており、その大半を中東諸国からの輸入に頼っています。
経済産業省「資源・エネルギー統計年報」によれば、2021年度の原油の輸入先比率は、サウジアラビア:37.3% アラブ首長国連邦:36.4% クェート:8.4% カタール:7.8% その他の中東諸国:2.6% となっており、これら中東地域からの輸入割合(中東依存度)は、なんと92.5%です。
原油の輸入先(2021年度)経済産業省
原油のほとんどすべてを中東に頼っているといっても過言ではありません。
よって中東、アラブ諸国とも原油輸入先として良好な関係を保つ必要があり、中東諸国なくして日本のエネルギー政策は成り立ちません。
つまり、日本にとってどちらも重要な国や地域であり、どちらの味方もできない立場であります。
またパレスチナの領土をめぐる、ユダヤ人とアラブ人というのは、ユダヤ教とイスラム教という一神教同士の対立でもあり、八百万(やおよろず)とたくさんの神と共存する日本人には理解しにくい側面もあります。
唯一の神を絶対的に信じるユダヤ教やイスラム教の宗教観を、クリスマスを祝い、神社にお参りをし、朝日が昇れば手を合わせるような雑多な宗教観を持つ日本人は私も含めて本質的な部分で理解するのは難しいのだと思います。
ですが、だからこそ、政治や宗教を超えて、私たち日本人だからこそ明確にできるポジションもあると考えます。
それは以下の通りであると私は考えます。
1.ハマスの無差別テロは断固として許さない。
2.イスラエル軍による民間人を犠牲にするガザへの地上攻撃も容認できない。
3.イスラエル(米国)、パレスチナ(中東諸国)どちらも日本にとって重要なパートナーである。しかし紛争についてはどちら側にも加担しないし味方もしない。
4.民間人の犠牲をこれ以上拡大させないために必要な人道支援、停戦を求める。
5.イスラエルとパレスチナの将来的な和平を望む。
日本は年末まで主要7か国(G7)の議長国でもあります。
岸田総理をはじめ政治家のみなさまには、是非、リーダーシップを発揮し、紛争解決に向けての一翼を担っていただきたいと思います。
日本だからこそできる役割があると私は思っています。
また現代はSNSの普及により、正規の報道機関が規制するような情報や映像も、個人レベルで入手することができます。
私自身も引き続き情報収集し関心を持ち、気づいたこと感じたことをできるだけ発信していきたいと思っています。
そしてイスラエル、パレスチナともに、民間人の方々の平和と心の平穏が戻ることを祈念します。
今月もよろしくお願いいたします。
10月に入りました。
東京では、朝晩はだいぶ涼しくなってきましたが、日中はまだまだ暑い日が続いています。
先日は新潟からコシヒカリの新米が届きました。
食欲の秋を楽しみたいと思っています。
8月24日、東京電力は、福島第一原発から出た処理水の海洋放出を開始しました。
これを受け、中国での日本産の水産物輸入を全面停止したことによる経済への影響、国内での風評被害が問題となっています。
私自身も処理水の海洋放出は心配なこともありましたが、自分なりにいろいろと調べた結果、処理水は安全であり、海洋放出しても水産物は安心して食べられて、健康に懸念する必要はないと今は考えています。
本日は、その根拠について情報共有させていただきます。
2011年3月11日の東日本大震災の際の津波による原発事故から現在に至る過程は以下の通りです。
1.汚染水の発生
汚染水:原発事故により発生している高濃度の放射線物質を含んだ水のこと。
↓
2.ALPS処理
ALPSという多核種除去設備で、トリチウム以外の放射性物質を安全基準まで十分に浄化
↓
3.処理水として保管
敷地内タンクに保管しているものの2024年には満杯になる予測
↓
4.処理水を海水で大幅に希釈
トリチウム濃度を国の安全基準の1/40、WHO飲料水基準の1/7に希釈
↓
5.海洋放出
今後も安全性についてのモニタリングを継続
30年後の廃炉を目指す
処理水の海洋放出については、7月4日、国際原子力機関IAEAが「東電が計画しているALPS処理水の海洋放出が人と環境に与える放射線の影響は無視できる」と結論づけた包括報告書を出しています。
ここまで精密に丁寧に処理していて、国も国際的な機関も大丈夫といっているなら大丈夫だろうというのが私の考えです。
しかし、それでも廃炉までは少なくとも30年かかる見通しとのこと。
30年後というと私は80歳を超えます。
80歳過ぎてテレビでも見ていて廃炉のニュースをみたとき、「事故から40年以上、やっとか。」と思うのかと想像すると気が遠くなります。
一度の事故での後処理の過酷さを考えると、やはり原発に依存し続けるのはどうなのかと思ってしまいます。
また事故とは無関係に、原発を通常運転させても高レベル放射性廃棄物、通称「核のゴミ」は出ます。
この核のゴミは増え続け、各原子力発電所に溜まり続けています。
最終処分は地中深くに埋め込むことを想定しているようですが、現在でも最終処分地は決まっておらず、実質的に候補も決まっていません。
核のゴミが人や環境に安全な基準までには10万年隔離する必要があると言われています。
事故処理や核のゴミの処分を考えていくと、やはり原子力発電の弊害はあまりにも大きいと気づかされます。
とはいっても原発を稼働させないと電気代も高くなり私たちの生活を圧迫してしまいます。
そう考えると、今ある原発を安全に稼働させながら、できるだけ早く再生エネルギーなどの代替エネルギー源を開発していくことが急務なのではないでしょうか。
風力・太陽・地熱などの再生エネルギーでの発電を増やし、原発の発電シェアを段階的に落としていく。
そして将来的には原発を0にする。
それが100年かかっても200年かかっても、私たちの子孫や地球環境のために、取り組まなければいけない大きな課題なのではないでしょうか。
今回の処理水の海洋放出を機に、私は原子力発電と将来のエネルギー対策について考えが改まりました。
みなさまはどのようにお考えでしょうか。
今回の処理水の海洋放出や核のゴミ問題について参考にした文献を添付しておきます。
「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと。」 経済産業省
「1から分かる核のゴミ」NHK
今月もよろしくお願いいたします。
9月に入りました。
うちの子供たちも長い夏休みが終わり、本日から学校がはじまりました。
まだまだ暑い日が続きますので体調管理には気を付けたいと思います。
大手中古車販売会社のビッグモーターの不正請求問題が大きく報道されています。
当社は取扱い保険会社のなかにSOMPOひまわり生命もあるのですが、当社経由でSOMPOひまわり生命の保険契約をいただいているお客様から他社に切り替えたいと解約依頼がありました。
ビッグモーター問題で損保ジャパンも不正請求に関与しているのではないかという報道をみて、そういう保険会社には自分の保険を任せておけないというのが理由でした。
また解約には至らなくても、同様の不安の声やお問合せを複数件いただいています。
損保ジャパンとSOMPOひまわり生命には、保険契約のうえで直接的な関係はなく、SOMPOひまわり生命の保険契約には影響はないのですが、お客様が心配したり不信感を持たれていることは真摯に受け止めなくてはいけないと思っています。
なので今回はビッグモーター問題を私なりに調べましたので、分かっている範囲でこの問題について解説したいと思います。
株式会社ビッグモーターの会社概要は以下の通りです。
売上高:5,200億円(2022年9月期)
従業員数:6,000名(2023年5月現在)
店舗数:約300店舗
創業:1978年
【業務内容】
1.中古車販売・買取
2.修理・板金・塗装
3.車検・点検・整備
4.自動車保険代理店業
非上場で創業者である元社長が実質的にほとんどの株を保有しているオーナー企業ですが、売上高は5,000億円を超える大企業です。
会社の特徴としては、以前から車の販売だけでなく、修理や車検、自動車保険の販売など、車周辺のお客様ニーズを一手に提供できる車のワンストップ型の業態です。
このワンストップサービスがお客様ニーズを捉え、全国に300店舗も持つような大企業へ発展しました。
今回の問題では、修理をめぐる不正請求・水増し請求が注目されていますが、問題はそれだけでなく、もっと複雑で複合的です。
ビッグモーター問題の内容を整理すると以下の通りになります。
1.中古車販売・買取業務での問題
お客様の経済力を超える無理なローン契約
事故車の不正販売
街路樹の除去
※店舗を見通しよくするため、社内の厳しい環境整備チェックへの対策など理由や動機は諸説あり。
2.修理・板金・塗装業務での問題
故意に傷をつけるなどした不正請求
過大な修理費による不正請求
3.車検・点検・整備業務での問題
車検不正・手抜き
4.自動車保険代理店業務での問題
架空に近い不当な保険契約
このようにビッグモーターが手掛ける業務全体で不正が発覚しつつあります。
これは担当者や個別の店舗、個別の部署の問題とは考えにくく、やはり組織全体の問題という印象を持ちます。
何故このような企業体質になってしまったのか。
私は、その原因は、行き過ぎた売上至上主義とお客様目線の欠如にあると考えています。
高い報酬に見合った成果を常に求め、店舗ごと個人ごとの売上と利益を過度に追及し、成果が出なければ、降格人事や厳しいペナルティーを課す。
その結果、従業員は管理職も含めて、お客様目線、お客様の利益を優先するという企業の本来の役割を果たさず、社内の上席や幹部からの評価や会社利益を優先する考え方になってしまっていたのだと思います。
京セラ創業者の稲盛和夫氏は、経営者をはじめ会社に集う従業員の行動規範として以下のような言葉を残されています。
「人間として何が正しいかを判断基準とする」
まず経営者が率先垂範し、人間として正しいか正しくないか、よいことか悪いことかという正不正、善悪を判断基準にすることが大きな間違いをしないために大切なことだと説いています。
今回のビッグモーター問題は、まさにこの「人間として何が正しいか」という判断基準が欠落していたのだと思います。
人は弱いものです。
どの企業でも売上と利益は重要な要素であり、これを一定水準に保たなければ経営はできません。
しかし成果を求めるなかで難しい判断をしなくてはならない局面に立ったとき、「人間として何が正しいかを判断基準とする」ということを忘れていけないと私自身も改めて感じています。
それが結果的に、お客様・従業員・家族・会社を守ることになると信じています。
現在、金融庁は、ビッグモーターと取引きしている損保会社7社に対し、報告徴求命令を出しており、特に損保ジャパンは重点調査の対象となっています。
損保ジャパンはビッグモーター問題に関して、9月末までに記者会見を開くことを表明しています。
私ももうしばらくは、この問題の推移を見守りたいと思っています。
この問題を契機に、業界の問題を改善し、中古車販売業界全体がよりよくなってくれることを願っています。
みなさまはこのビッグモーター問題をどのように感じていらっしゃいますか?
今月もよろしくお願いいたします。
8月に入りました。
毎日、猛暑が続くなか、高校野球の季節がはじまっています。
すでに東京の予選は終了し、西東京は日大三高、東東京は共栄学園がそれぞれ優勝し、甲子園の出場を決めました。
私の母校、佼成学園は準々決勝で早大学院に0-3で惜しくも敗戦し、ベスト8で夏を終えました。
それでも4回戦では昨年敗戦した桜美林高校に勝ち、昨年の雪辱を果たしてくれました。
西東京で堂々のベスト8。
選手のみなさんには今年も私たちOBを楽しませてくれて感謝しています。
また秋の新チームに期待したいと思います。
そして、東京代表の日大三高と共栄学園には甲子園での活躍を期待しています。
それにしても暑い日が続きます。
特に炎天下の野球場と応援席は日陰がほとんどありません。
今は5回が終了した時点で10分間の休憩が入りますが、それでも選手や応援席にいる方の熱中症対策は非常に重要です。
野球の試合だけでなく、日常生活でも長い時間、外を歩いていたりすると立ちくらみがしたり吐き気がしたり、私自身、熱中症の初期症状と思われるような状態になったこともたびたびあります。
熱中症対策は小まめな水分補給はもちろんですが、それだけでは不十分だそうです。
首、脇の下、太ももの付け根を冷やすことが熱中症対策には効果的とのこと。
それらの部位は体表の近くに太い静脈が流れていて、皮膚を通じて静脈の血液を冷やすことで、大量の冷えた血液が体内に戻り、効果的に体内を冷やすことができるそうです。
首の保冷グッズはよく売ってますね。
脇の下や太ももの付け根などはなかなか人前では冷やせないですが、トイレなどでタオルを水で冷やして当てたりすれば短時間でも効果はあると思います。
今年は空梅雨で例年より本格的な夏がはやくきました。
少なくともあと1か月は、今のような猛暑が続くのだと思います。
体調管理に努めて、それぞれの夏を楽しみたいですね。
今月もよろしくお願いいたします。
7月に入りました。
東京の天気は、昨日は晴れて今週も晴れて暑い日が続く予報になっていますので、梅雨明けが近いかもしれません。
株価の好調が続いています。
日経平均は30,000円を超えて、バブル期以後の高値を更新し、6月30日(金)の終値は33,189円でした。
将来、バブル期の史上高値を超えて40,000円を超える日も来るのではないかという専門家もおります。
昨今の株高の要因を考えたとき、報道などから情報を整理すると主に以下の6つかと思われます。
1.好調な企業業績
コロナ禍が終息し、経済活動が正常化したこと、加えて円安効果で国内景気をけん引する輸出企業の業績が好調なこと。
商社を含めた卸売・空輸・陸運などの業種も好調。
2.米国のNYダウ平均株価が好調であること。
やはり米国の株価の影響は多大
3.金融不安の後退
欧米の金融不安が後退し不安材料が低下したこと
4.東証のPBR(株価純資産倍率)改善要請
企業の株価を引き上げるモチベーションが高まったこと。
株主還元の一環として自社株買いを実施する企業が増えたこと。
5.日銀による金融緩和政策の継続姿勢
4月に就任した植田新総裁が当面金融緩和を継続する姿勢を示したことが市場の安心感につながったこと。
6.バフェット効果
著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏が4月に来日し、日本の総合商社をはじめ日本株への積極投資の意向を示したこと。
このように見ると、内部要因と外部要因が噛み合わさって、現在の株高が支えられていることが分かります。
いつまで好調をキープできるかは不明ですが、やはり要因の柱は企業業績だと思います。
そうすると現在の景況感というのはしばらく続くのではないでしょうか。
こうした経済環境を受けて、当社が取り扱っている変額保険の販売も好調です。
私は1972年の生まれで新卒で社会人になったのは1995年で、すでにバブルは崩壊していました。
以来ずっと失われた〇〇年とか言われる経済環境でした。
なので個人的にはバブル超えの日経平均40,000円超は、「あり」だと思っています。
そうなるといいですね。
今月もよろしくお願いいたします。
今日から6月に入りました。
東京は曇天や小雨が降る日が増えてきて、近い将来に梅雨入りすることを思わせる日が続いています。
今月は、会社員の退職金についての話題に触れたいと思います。
60歳や65歳の定年退職時に勤務先から受け取る退職一時金についてです。
当社は法人のお客様が多いですが、近年、従業員の退職金制度をはじめとした福利厚生の充実について関心が高まっていると感じています。
先日も生命保険を活用して退職金や弔慰金準備のための福利厚生プランをご契約いただきました。
売上高20億円規模、従業員はパート含めて約100名、そのうち勤続3年以上の正社員約50名を対象にした福利厚生プランで、具体的な保険種類は変額養老保険です。
従来から退職金積立てとして特定退職金共済を活用されており、その2階建て部分として生命保険をご採用いただきました。
現在もすでにそうですが、今後は少子高齢化がますます加速し、労働力人口の減少による人材不足がさらに進行すると考えています。
そのような環境のなかで、在職従業員の定着率向上と新規人材の採用力向上が人材不足を回避できる対策となり、退職金制度を含めた従業員の福利厚生制度の充実は、人材不足を回避するための有力な対策だと考えています。
なので日本の中小企業の持続的な成長と発展に微力ながら貢献できる対策として、これからも積極的に法人の従業員向けの福利厚生プランの提案や構築に携わっていきたいと考えています。
退職金に関するデータを2つご紹介します。
<退職給付制度がある企業の割合(企業規模別)>
| 従業員数による企業規模 | 退職金制度がある割合 |
|---|---|
| 1,000人以上 | 92.3% |
| 300~999人 | 91.8% |
| 100~299人 | 84.9% |
| 30~99人 | 77.6% |
| 全体 | 80.5% |
※厚生労働省平成30年就労条件総合調査より
<モデル退職金(東京都内中小企業)>
| 学歴 | 勤続年数 | 会社都合支給額 | 自己都合支給額 |
|---|---|---|---|
| 高卒 | 10年 | 114万円 | 89万円 |
| 高卒 | 20年 | 333万円 | 278万円 |
| 高卒 | 30年 | 622万円 | 543万円 |
| 高卒 | 定年 | 1,031万円 | - |
| 大卒 | 10年 | 148万円 | 113万円 |
| 大卒 | 20年 | 425万円 | 353万円 |
| 大卒 | 30年 | 785万円 | 705万円 |
| 大卒 | 定年 | 1,118万円 | - |
※東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)より
退職金制度があり、すでに中小企業退職金共済などで積立てをされていても、退職金規程に照らし合わせた積立額が不足しているケースも多々あります。
そのようななかで2階建て部分として積立金額を積み増すことをご検討の場合には、養老保険を活用した福利厚生プランも検討に加えると幅広く自社にあった計画的な退職金積立てができると思います。
養老保険にも他の制度にはないメリットが多々ありますのでご参考にしていただければと思います。
例えば65歳で定年退職時に退職金を受取り、その後も再雇用で働いていく。
すぐに公的年金を受け取らずに、減額された給与と退職金の取崩しで75歳まで働いていく。
そして75歳からの厚生年金の繰り下げ受給により、基準年金額の約1.8倍に増額された厚生年金で安心して100歳まで暮らしていく。
このようなライフプランが人生100年時代には必要になってくるのではないでしょうか。
そのために企業として従業員の退職金を含む福利厚生の充実策の必要性が今後ますます高まってくるのではと考えています。
今月もよろしくお願いいたします。
今日は5月1日、連休の谷間です。
今日と明日を休んで9連休にされる方もいらっしゃると思いますが、私はカレンダー通り仕事をしています。
最近、個人のお客様と話しをしていて話題になることが多いのが、老後資金の積立てについてです。
政府の「貯蓄から投資」へという後押しもあり、NISAやiDeCoなどの投資型積立て制度についての話題も多いです。
しかし、いろいろな制度があって、どれがいいのか、どのように選んだらいいのか分からないとご相談されるケースも多々あります。
なので今回は、積立投資の代表的な制度・商品である、「つみたてNISA」「iDeCo」「変額保険」の3種類の特徴や概要を掲載した比較表をご案内させていただきます。
企業の従業員向け研修でも取り上げさせていただいている内容ですのでご参考にしてください。
<積立投資制度の比較>
| NISAつみたて投資枠 | 2024年1月~ iDeCo 変額保険 | (有期型・年金) | |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 短期(5年) 中期(10年) 老後など 長期の積立て | 老後など 長期の積立て | 中期(10年) 老後など 長期の積立て |
| 運用期間 | 無制限 | 65歳まで | 任意に選択可 |
| 運用商品 | 投資信託など | 預貯金・投資信託・保険商品 | 日本株・世界株・債券などの特別勘定 |
| 税制優遇(掛け金) | なし | 全額所得控除 | 生命保険控除 |
| 税制優遇(運用益) | 非課税 | 非課税 | 一時所得の対象 |
| 年間投資上限額 | 120万円 | 14.4万円~81.6万円 | 特になし |
| 資金の途中引出し | 可 | 60歳まで不可 | 可 |
| 積立金のスイッチング | × | 〇 | 〇 |
| 付加価値 | 死亡保障 三大疾病保険料免除等 | ||
| 対象年齢 加入資格 | 18歳以上 | 公的年金加入者 | 0歳から |
| 専属担当者の有無 | △ | △ | 〇 |
※NISA制度は2024年1月から改定されます。本表では改定後のNISA制度のうち、つみたて投資枠のみ掲載しています。
※積立金のスイッチング:今までの積立ファンドの種類を積立金ごと他の積立ファンドに移転させること(例:世界株式ファンドから債券型ファンドなど)
このように各制度で違いがあり、メリット・デメリットもそれぞれあります。
資金を積み立てる目的もさまざまです。
短期の積立て、お子様の教育資金の積立て、将来の不動産取得のための積立て、老後資金の積立てなどが主な目的と思われます。
それぞれの目的やニーズに照らし合わせて、どのタイプの積立投資商品を選ぶのか、または組み合わせて複数の制度で積立てをしていくのかを検討しながら選択するとご自身にあった積立投資ができると思います。
ご質問などありましたらメールでお問合せいただければ個別にご回答させていただきます。
今月もよろしくお願いいたします。
4月に入りました。
今日から新年度という会社も多いのではないでしょうか。
今年は桜の開花が早く東京ではすでに桜が散ってしまっていますが、春らしい心地よい天気が続いています。
近所の小金井公園ではこの週末、お花見のグループでにぎわい、また観光地でも人出が多く、コロナ前の光景に戻ってきていると実感します。
5月8日には新型コロナウイルスの感染症分類を季節性インフルエンザと同じ5類に移行することも決まっており、丸3年間続いたコロナパニックもやっと終息してきました。
過去の歴史で私たち人間は、さまざまな脅威や危機に直面しそのたびに乗り越えてきましたが、今回の新型コロナウイルスによるパンデミックという試練も、私たちは克服したと言ってよいのではないでしょうか。
ワクチンや治療薬などの技術と、マスクや自粛といった知性によって乗り越えたのだと思います。
当社は3月決算で無事に16期目を終えました。
昨年度は、企業の生命保険を活用した従業員向け福利厚生プランの拡充や、個人の将来に向けた資産形成商品の販売が好調でした。
これは、コロナ禍の終息に見通しがつき、企業も個人も将来のことに関心を向けられる余裕ができ、前向きな対策をとることが可能となったことが要因の一つだと思っています。
これからビジネス環境は一気に好転していくのではないでしょうか。
これまでの3年間は、様子見や守りに重きを置く環境でしたが、これからは積極性や攻めがキーワードになってくると感じています。
そしてその変化は想像以上に早いスピードで進むと見ています。
企業は環境の変化に柔軟に対応することが必須です。
私も当社も世の中の早いスピードで好転していくであろう環境の変化に遅れを取ることなく、マインドを積極性にギアチェンジし、具体的な行動で波に乗っていきたいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
3月に入りました。
東京はここ数日暖かい日が続き、春の到来を感じています。
今年の桜の開花は例年よりも早めになると予想されていますね。
東京では3月25日頃が満開の見ごろを迎えるような予想もされているので、お花見の予定を考えていきたいと思っています。
先月もお客様から生命保険に関するご相談を数多くいただきました。
お客様とご面談するなかで、よくいただくご質問は以下の2つです。
1.みなさん保険料ってどのくらい掛けているのですか?
2.生命保険ってどのくらいの人が入っているのですか?
基本的なことですが、この2つは昔からよく聞かれます。
なので本日は、生命保険文化センターの調査をもとに生命保険に関する統計データをご紹介したいと思います。
出典元は、2021年12月に生命保険文化センターから発行されて「生命保険に関する全国実態調査」です。
代表的な調査結果は以下の通りです。
■生命保険世帯加入率 89.8%
■年間払込保険料(平均) 37.1万円
■死亡保険金額(平均) 2,027万円
■個人年金加入率 24.3%
■医療保険・医療特約の加入率 93.6%
■ガン保険・ガン特約の加入率 66.7%
■介護保険・介護特約の加入率 16.7%
※ 2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査 生命保険文化センター より
いかがでしょうか?
生命保険加入率は約90%です。
これは携帯電話の普及率と大差ないくらい、日本人のほとんどすべての人が何らかの生命保険に加入しているという実態があります。
加えて、医療保障やがん保障の加入率も高いですね。
新型コロナワクチンの接種率やマスクの装着率と同様に、日本人は、リスクに対する備えに敏感なのかもしれません。
または、「みんながやっているから」という同調意識も高いのかもしれないですね。
一方で個人年金の加入率が24%というのは、ちょっと低いと感じます。
日常的に報道などで、少子高齢化により公的年金を含めた将来の社会保障財源が厳しいと言われているなかで、老後の生活を支えるための個人年金の加入率が4人に1人程度しか準備していないということです。
若くして亡くなったり、病気で長期入院をする確率よりも、長生きする確率の方が圧倒的に高いにもかかわらずです。
私は、万が一や不測のリスクに備える保険料を、もう少し、長生きの生活に備える個人年金など、将来への自助努力による積立ての方に振り向けていってもいいのではないかと考えます。
生命保険文化センターの生命保険に関する全国実態調査は、1965年から3年に1度、継続的に実施してきた調査であり、多くの興味深い統計値が公開されています。
今回の調査書面も341ページと膨大な量のデータが掲載されています。
ご関心のある方は、是非、ご覧になり、ご自身の保険選びの一助になれば幸いです。
⇒ 2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査 生命保険文化センター
いずれにしても、生命保険でも個人年金でも、保険会社や商品が数多くあり、各世帯でのニーズに適う商品を納得いくかたちで選択することは、簡単なことではありません。
新規加入や見直しをご検討される場合には、信頼できるプロにご相談されることをお勧めします。
今月もよろしくお願いいたします。
ついこの前、新しい年が明けたと思ったら、あっと間に1か月が過ぎ、本日から2月に入りました。
東京は晴れていますが、冬らしい凛とした寒い日が続いています。
1月4日、明治記念館にて、私が所属する鴎友書道会が主催する、第45回鴎友書道展表彰式が開催されました。
全国から200名を超える表彰者が参列しました。
私が指導している、小金井・新潟・大宮の教室からも上位入賞者が出て、3名が壇上で表彰を受けました。
本日は、入賞者を選出する作品審査についての所感と、書作品とビジネスとの関連性について考えてみたいと思います。
昨年11月23日に会の役員と当番審査員で審査を行いました。
そしてトップ賞候補の作品を10点選出し、審査員の挙手制により、トップ賞以下の賞が決定します。
私も当番審査員の一人として1票を投じました。
全部で4,000点を超える作品のなかから選びだされた10点なので、どれも完成度が高い作品で優劣をつけがたい作品が並びます。
みんなすばらしい作品ばかりです。
そんななかで、選ぶ要素の1つは、「名前」です。
落款とも言います。
どちらもうまい、判断が難しい、となったときに名前を見たりします。
名前のうまさや丁寧さ位置などを見ます。
一見、付属のように思われる名前が、実は勝敗を決する鍵だったりするわけです。
名前も作品の一部だからです。
これはビジネスでも同じようなことがあるのではないでしょうか。
競合先と商品やサービスの価格や品質にほとんど差がないケースはよくあることだと思います。
そんななかで勝敗を分けるポイントはどんなことでしょうか。
人柄・身だしなみ・清潔感・きめ細やかさ・思いやり・誠実さ・迅速性・正確性など。
こうした商品・サービスの本質的な要素以外の、付随的ともいえる要素が意外に勝敗を分けるポイントになるのではないしょうか。
私の今までの経験を振り返ってみてもこうした要素は大いにあると感じてます。
書道の名前で考えれば、最後まで気を抜かない慎重さ、も含まれるかもしれません。
私が指導している方は、本格的に書道に取り組んでいるというより、経営者や会社員など、一般のビジネスパーソンがほとんどです。
これからも書道を通じ、ビジネスにも通じる気づきを見つけてもらい、生かしてもらいたいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
あけましておめでとうございます。
2023年、令和5年がはじまりました。
今年の干支は、癸卯(みずのと・う)です。
十二支だと「うさぎ年」ですね。
干支は、十干と十二支の組み合わせでできていて、60年をかけて一巡します。
そのため60歳を還暦といいます。
干支は中国の古い思想である「陰陽五行思想」を礎にしており、それぞれに意味を持っています。
それによると、癸卯は、「寒気が緩み、萌芽を促す年」とのこと。
停滞した世の中に希望が芽吹き、花開く助走の年ということになります。
縁起担ぎをすると、今年は、コロナ禍が終息し、ロシア・ウクライナ戦争が終結し、世の中が正常の状態に戻り、経済が再び活発化する年となるのかもしれません。
年のはじめに、「今年はよい一年になる」と思いながら準備し、また毎日を過ごしていきたいものです。
大前研一氏は次のように言っています。
p人間が変わる方法は三つしかない。一つは時間配分を変えること。二番目は住む場所を変えること。三番目は付き合う人を変えること。この三つの要素でしか人は変わらない。もっとも無意味なのは、「決意を新たにすること」だ。かつて決意して何か変わっただろうか。行動を具体的に変えない限り、決意だけでは何も変わらない。
示唆に富む本質的な箴言だと思います。
変化の激しい世の中に対応していくためには、自分自身も変化し続けなければいけません。
自分が変わること。
それには、行動を具体的に変えること。
このことをいつも忘れずに一年を過ごしていきたいと思います。
みなさまにとって今年一年がよい年になりますように祈念します。
今年もよろしくお願いいたします。
本日から12月です。
気づけば今年も残り1か月となりました。
1年あっという間ですね。
最近、また新型コロナの感染者が増えています。
すでに報道などでご存じの方も多いと思いますが、9月26日以降、新型コロナ感染による医療保険の給付要件が変更されました。
今までは、年齢や症状に関係なく、自宅療養でもみなし入院として入院給付金支払いの対象となっていました。
しかし9月26日以降は、入院給付金等の支払い対象を以下の重症化リスクの高い方に限定されることになりました。
1.65歳以上の方
2.入院を要する方
3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
4.重症化リスクがあり、かつ、酸素投与が必要な方
5.妊婦の方
このように支払い要件は制限されています。
しかし、基礎疾患のある方が新型コロナに感染した場合、新型コロナ治療薬が処方されるケースが多く、引き続き、医療保険の入院給付金支払いの対象になる例もけっこうあることが分かってきました。
当社のお客様でも、9月26日に新型コロナに感染し、自宅療養だったためお客様ご自身は「入院給付金の対象にならない」と判断されて保険会社への請求を諦めていたにもかかわらず、私が状況を聞き、新型コロナの治療薬を処方されたことが分かり、請求対象になった事例が複数件発生しています。
保険会社が指定する治療薬はおおむね共通しており、以下の通りです。
新型コロナに感染し、以下の治療薬を処方された場合には、自宅療養であっても入院給付金の支払い対象になります。
| 名称 | 商品名 |
|---|---|
| カシリビマブ・イムビマブ | ロナプリーブ |
| ステロイド薬(デキサメタゾンなど) | デカドロンなど |
| ソトロビマブ | ゼビュディ |
| トシリズマブ | アクテムラ |
| ニルマトレルビル・リトナビル | パキロビッドパック |
| パリシチニブ | オルミエント |
| モルヌピラビル | ラゲブリオ |
| レムデシビル | ベクルリー |
会社で医療保険に契約している場合も対象になります。
また各従業員様が個別に加入している団体契約の医療保険も同様です。
経営者の方は、法人での契約も合わせてご確認いただき、従業員様とも情報共有していただくと助かる方も多いと思います。
また給付要件は保険会社各社によって違いもあります。
新型コロナに感染し、入院給付金の請求をご検討される方は、契約している保険会社または代理店へお問合せいただき、詳細をご確認ください。
ご参考になれば幸いです。
本日から11月に入りました。
秋も深まり、朝晩は肌寒くなりましたが、日中は爽やかな秋晴れの日も多くなってきました。
円安が続いています。
私たち保険業界もドル建て保険など為替の影響を受ける商品があり、お客様からの問い合わせも多いため、現在の円安と外貨建て保険への影響と対応について解説したいと思います。
米ドルと円は、ここ数年、1ドル=110円前後の安定的な推移が続いていました。
しかしご存じの通り、今年はじめから円安へ推移し、ここ数か月で急激な円安となり、現在、1ドル=150円程度までドル高円安となっています。
生命保険商品には、米ドル建ての保険があり、この種の保険の保険料は、契約時の為替を円換算して支払います。
例えば、保険料が100ドルの保険は、1ドル=110円のときは11,000円となり、1ドル=150円だと15,000円になります。
支払う保険料で考えると円安はお客様にとって負担が大きくなります。
一方、死亡保険金や解約返戻金で考えると事情が変わります。
例えば、死亡保険金と解約返戻金が10万ドルの場合、1ドル=110円の場合には1,100万円となり、1ドル=150円の場合には1,500万円となります。
お客様にとっては受取り額が増えることになり、円安はメリットです。
現在、1ドル=110円のときに契約した保険を解約すると、1ドル=150円の為替差益が発生し、払い込んだ保険料よりも解約返戻金が上回るケースが頻発しています。
当社のお客様でも、契約から5年程度で円換算で利益が発生し、解約して利益確定される事例が出てきています。
思いのほか、払い込んだ保険料に比べ、大幅に多い金額が戻ってくるのですから、これはメリットなのですが、ご注意いただく点があります。
それは、税金です。
払い込んだ保険料よりも多い解約返戻金を受け取った場合、課税され、別途税金を支払うケースがあります。
課税の種類は、源泉分離課税または一時所得課税です。
そのどちらになるかは、保険種類・契約からの経過年数等によって変わります。
概要は以下の通りです。
<源泉分離課税の対象となる場合>
対象商品:養老保険・学資保険・変額保険有期型・個人年金保険・変額個人年金保険
保険料払込方法:一時払または全期前納・一部期間前納等
保険期間等:契約期間5年以下の満期保険金・契約から5年以内の解約返戻金
課税内容:差益(解約返戻金等-支払保険料)の20.315%
税金の支払い方法:保険会社で源泉徴収
<一時所得課税の対象となる場合>
対象商品:上記以外(終身保険・米ドル建て終身保険・一時払終身保険等)
保険料払込方法、保険期間等に制約なし
課税内容:(差益(解約返戻金等-支払保険料)-50万円)*1/2…A
Aの金額がその年の課税所得にプラスされて課税
税金の支払い方法:個々に確定申告
現在、円安で解約を検討される方が契約している保険種類は、一時払ドル建て終身保険、全期前納ドル建て終身保険、払込済のドル建て終身保険、ドル建て養老保険などです。
一時所得の方が低率の課税となり有利です。
また一時所得の対象となる場合、上記の計算式の通り、差益が50万円以下であれば実質非課税で受け取ることができます。
このように保険契約の内容によって課税関係が変わり、課税金額に差が生じます。
円安で保険契約を解約して利益確定を検討される方は、この課税関係についてはご確認ください。
個別契約についてのお問合せは、契約している保険会社または所轄税務署にされるのがよろしいと思います。
ご参考にしてください。
為替の予想は難しいのですが、今後、どうなるのでしょうか。
今後は円高に向かうという予想もあるし、さらに円安が加速するという予想もあります。
結局のところは分かりません。
不透明な状況は続きますが、推移を見守り、その都度、対応していきたいと思っています。
10月に入りました。
朝晩は涼しく過ごしやすい季節になりました。
本日は、コロナと生命保険の入院給付金について重要な変更事項がありましたので情報提供させていただきます。
9月26日から新型コロナウイルスの感染者に支払う入院給付金の対象が変更され限定的になりました。
今までは、病院に入院しなくても、自宅やホテルで療養する「みなし入院」でも給付金が支払われてきました。
コロナに感染すれば給付金が受け取れるという状況でした。
医療保険は本来、入院しなければ給付金を受け取ることができないのですが、感染者で病床があふれる事態を防ごうと、各社は金融庁の要請も踏まえて約款の解釈を変更し、みなし入院でも給付金を支払う特例措置を2020年4月から続けてきました。
当社にも多くのお客様がコロナに感染されご請求をいただきました。
しかし、最近ではコロナに感染しても重症化するおそれが小さくなり、軽症や無症状の感染者が増加したことで、岸田総理が感染者の情報を集める全数把握について、9月26日から全国一律で、重症化リスクの高い層に限定する簡略化を表明され、運用がはじまりました。
今回の入院給付金対象の変更は、こうした政府の動向に合わせたことになります。
9月26日以降、コロナ感染者の入院給付金対象は、以下に限定されます。
1.65歳以上
2.入院した場合
3.治療薬や酸素投与が必要な場合
4.妊婦
65歳未満の軽症者で自宅療養の場合には、対象外となります。
ただし陽性判定が9月25日以前の場合には、従来通り、自宅療養やホテル療養でも入院給付金支払いの対象となりますので、この点はご留意ください。
また9月26日以降も、65歳以上の方や妊婦の方は、みなし入院でも入院給付金の対象となりますので合わせてご確認ください。
コロナ第7波を受けて、給付金請求はまだまだ高水準にあります。
生命保険協会によると、8月の支払い件数は全社で102万件と初めて100万件を突破したとのこと。
1日3万件以上の支払いということです。
保険会社各社は、人員を増やして支払い業務にあたっていますが、それでも追いつかず、各社業務がパンク状態で、給付金支払いにあたっては相当な時間がかかっています。
給付金の対象となっている方は、是非、お早めにご請求ください。
コロナもやっと終わりが見えつつありますね。
10月11日からはGoToトラベルの後継である全国旅行支援もはじまります。
久しぶりの観光の秋が楽しめるといいですね。
今日から9月に入りました。
ここ数日の東京は朝晩は涼しい日が続き、秋の訪れを少しずつ感じられるようになりました。
京セラの創業者の稲盛和夫さんが8月24日に90歳でお亡くなりになりました。
報道で知り、突然のことでショックでした。
心からご冥福をお祈りいたします。
私は、稲盛さんが主催する経営塾である盛和塾で、塾生として2008年から2019年12月までお世話になりました。
当時、保険代理店として起業したことを機に、「ばかうけ」で有名な栗山米菓の栗山敏昭社長からの勧めで入塾し、盛和塾<新潟>に所属させていただきました。
以来、2019年12月の解散まで、塾長例会、世界大会などで稲盛塾長の講話を直接聞く機会に恵まれました。
また月一回の新潟での自主例会や機関誌、著書の購読などで、稲盛経営哲学を学びました。
当社で掲げている<お客様本位の業務運営方針>は、6項で構成されており、その第1項<お客様利益の追求>には、稲盛さんの言葉である、「人間として何が正しいのかを判断基準とする」という文言を引用させていただいています。
このことに重きを置き、従業員と共有し、日々の業務の基盤とできていることは、稲盛さんと盛和塾での学びを反映させた代表的な実践です。
また、私自身は、稲盛さんの箴言のなかで以下の2つをいつも心掛けるようにしています。
1.土俵の真ん中で相撲を取る。
2.もうダメだというときが仕事のはじまり。
常に努力し油断せず、謙虚にして驕らず、安定した業績を継続させ、余裕を持った経営と人生を送る。
しかし、ときには、もうダメと思うくらい土俵際に追い込まれるようなピンチになることもあるものです。
そんなとき、ここからが仕事のはじまりと思い、諦めず、誰にも負けない努力をして、もう一度、土俵の真ん中まで押し戻す。
人生も経営もこの繰り返しなのかもしれないと思い、この2つを常に心がけています。
稲盛さんが亡くなっても、書籍や機関誌でいくらでも学び続けることができます。
これからも微力でも歩みが遅くても、しっかりと稲盛哲学を実践し、従業員の物心両面の幸せを実現していきたいと思います。
稲盛さんは、2019年12月に、「自分が元気なうちにきれいな形で盛和塾を終わらせたい」とメッセージを残し、盛和塾を解散されました。
それから3年弱。
ご自身の人生も天寿を全うすることで静かにきれいに終わらせ、最後まですばらしい生き様を見せてくれました。
京セラを創業し、KDDIを創業し、JALを再生された、日本史を代表するような経営者の謦咳に接することができたことは、私の人生の誇りです。
心から感謝しています。
今日から8月に入りました。
東京は厳しい暑さが続いています。
そんななか高校野球の夏の甲子園予選が各地で行われました。
昨日、西東京の決勝が開催され、日大三高が東海大菅生に勝ち、4年ぶり18回目の夏の甲子園出場を決めました。
そして30日には東東京の決勝があり、二松学舎が日体大荏原に勝ち、2年連続5回目の夏の甲子園出場となりました。
トーナメント途中ではダークホース的な高校が勝ち上がったりしましたが、最後に優勝した2校は、東西の強豪であり、結局は順当な結果になったような気がしています。
私の母校、佼成学園は5回戦まで勝ち上がりましたが、ベスト8をかけた試合で桜美林に敗れました。
試合当日は、私も球場に足を運び応援しました。
7回終了まで2-0で試合を優位に進めていましたが、8回、9回に1点ずつ加点され、9回土壇場で2-2の同点。
そして延長10回表に2点追加され、結果、2-4、痛恨の逆転負けとなりました。
私も一緒に観戦していたOBも、大変悔しい思いで球場をあとにしました。
選手も悔しかったと思います。
この悔しさをバネに新チームで迎える秋の大会は、是非、頑張ってもらいたいと思っています。
試合後、いろいろな思いが込みあがりました。
野球のゲームセットは、9回裏。
それまでいくら勝っていても、最後に負ければ負けです。
これは大人になってからの社会でも同じようなことが言えると思います。
競合他社との受注競争、新技術の開発競争、組織内での出世競争。
どれも、途中のプロセスに有利不利の状況は変化しますが、最後には勝ち負けがはっきりします。
そして一旦は勝敗がついたとしても、また次の試合がはじまり、試合はその先もずっと続きます。
だからこそ、
勝っていとき(うまくいっているとき)は、油断せず、さらなる努力を。
負けているとき(うまくいかないとき)は、焦らず、諦めず。
こうした心構えが大切なのだと思います。
京セラの創業者である稲盛和夫氏の箴言に以下があります。
「謙虚にして驕らず さらに努力を」
「もうダメだというときが仕事のはじまり」
私は、前者は「うまくいっているとき」に、後者は「うまくいかないとき」に心掛けることと肝に銘じています。
スポーツやビジネスだけでなく、人生そのものにも言えることだと思います。
高校野球を通じ、多くの気づきと学びをもらっています。
高校野球はこれからが本番です。
今年も甲子園でたくさんのドラマが待っていると期待しています。
今日から7月に入りました。
今年は記録的に早い梅雨明けとなり、東京では連日、35度以上の猛暑日が続いています。
暑さ対策をしっかりしてお過ごしください。
学習指導要領の改訂により、2022年4月から高校での金融教育が必修化されました。
家庭科の授業に組み込まれているとのことです。
その背景には以下の3つが挙げられます。
1.成人年齢が18歳に引き下げられ、クレジットカード契約等を自分でできるようになること。
2.少子高齢化により老後の公的年金の給付水準が減少する可能性があること。
3.諸外国に比べて金融教育が遅れていること。
金融庁では高校向けの金融経済教育指導教材を公表しています。
教材の概要は以下のような構成となっています。
1.家計管理とライフプランニング
2.お金の使い方(現金・電子マネー・デビットカード・クレジットカードなど)
3.社会保険と民間保険
4.資産形成(株式・債券・投資信託など)
5.お金を借りる(ローン・クレジットなど)
6.金融トラブル
出典:高校生のための金融リテラシー講座(金融庁)
内容を見ると、私が生命保険業界に入ってはじめて研修を受けた内容と同じようなレベルにあり、高校生にはちょっと難しいという印象を受けます。
しかし思考が柔軟な高校生ならば、ゲーム感覚であっという間に必要な金融知識を身につけられるとも思っています。
また、学校で金融教育をしろと言われても、学校現場では金融について専門的な知識や情報を身につけた教員が少なく、戸惑いも多々あると聞いています。
ちょっと想像しただけでも今まで家庭科を教えていた先生が、いきなり金融教育と言われてもちょっと無理があると思います。
そうした意味では、生徒側よりも、むしろ教える側の教員に課題が多いと捉えることもできます。
こうした背景から、各学校で外部講師を招いて、教員向けの研修を行ったり、生徒向けの特別授業を行っている学校もあるといいます。
私自身も4人の子供がおり、子供たちには、人生を豊かにするための金融リテラシーは身につけてもらいたいと願っています。
また人生100年時代と言われる長生き社会を豊かに過ごしていくためには、日本全体の金融リテラシーを引き上げていく必要があり、そのためには、子供の頃からの金融教育が必須だと考えています。
私は、約10年前から企業向けに社会保障制度と資産形成をテーマとした研修を行っています。
タイトルは、「人生100年時代と豊かに過ごすために」。
これを学校教育の現場で、例えば、教員向け・生徒向け・保護者向けに応用できるのではないかと思っています。
学校関係者の方で、金融教育に関して外部講師による研修等のニーズがある場合にはお声がけください。
ご協力できることがあると思います。
私自身が長年身につけた専門的な知識や情報、経験にもとづく助言やアドバイスにより、わずかでも社会貢献できればと思っています。
本日は6月1日です。
今朝の東京は、晴れて爽やかな朝を迎えています。
円安が進みましたね。
本日、6月1日朝の為替レートは、1ドル=128.7円です。
昨年6月頃の1ドル=110円くらいでしたので、1年で18円、約17%も円安になったことになります。
輸入品が円安により割高となり、食品の値上げなど、私たちの日常生活にも影響を与えています。
そんななか、私たち保険業界が取り扱う、米ドル建て保険等の外貨建て保険にも円安の影響が出ています。
その影響は、お客様にとってプラス面とマイナス面があります。
米ドル保険は、通常の円建て保険に比べて予定利率が高く、保険料が割安なため、保障として考える場合にはメリットも多い商品です。
その一方で、販売者の説明不足やお客様のご理解不足によって誤解やトラブルも少なくないのも事実です。
本日は、現在の円安局面の情勢を受けて、米ドル建て保険について解説します。
米ドル建て保険のメリットとデメリットにも関連することですが、お客様からのご質問やお問合せの内容をもとに、以下の通りQ&A形式で解説します。
ご参考にしてください。
<米ドル保険について>
Q1:保険種類はどのような商品がありますか?
A1:終身保険・定期保険・養老保険・個人年金など円建て保険と同じような種類の保険があります。
Q2:保険料はどのように支払いますか?
A2:ドルの為替レートを円に換算して円で支払います。
Q3:月払い契約の場合、毎月の保険料は変動しますか?
A3:円で支払うため変動します。毎月の保険料が100ドルの場合、1ドル=100円の月の保険料は10,000円となり、1ドル=120円の月の保険料は12,000円になります。
Q4:死亡保険金や解約返戻金の金額は変動しますか?
A4:受取り時の為替レートで支払われるため、円換算の金額は変動します。考え方は上記A3と同様です。ただしドルで受け取ることも可能です。
Q5:一時払の場合のメリットとデメリットは何ですか?
A5:メリットは、返戻率が円商品より高いため、おおむね10年後くらいのドルベースの解約返戻率は円建て保険や銀行預金利率よりも高いことです。それに加え、保険金支払い時や解約時に契約時よりも円安になっていた場合、為替差益がプラスされることです。デメリットは、短期で解約した場合、ドルベースでも元本割れすることです。加えて保険金支払い時や解約時に契約時よりも円高になっていた場合、為替差損も加わりより損失が大きくなることです。
Q6:月払の場合の為替リスクをどのように考えればいいですか?
A6:為替レートによって毎月の保険料は変動しますが、変動するからこそ、為替レートや円で支払った保険料は平均化され、一時払契約などと比べて為替リスクは抑制されます。払込期間が長ければ長いほど為替レートがより平均化され、為替リスクは低くなると考えられます。
Q7:円安の今、契約中のドル保険を解約するメリットはありますか?
A7:ドルベースの解約返戻率が100%を割っていても、円安による為替差益により、円ベースではプラスになるケースがあります。その場合には解約するのも選択肢です。現在の契約状況を確認し検討してください。
Q8:資産運用として向いていますか?
A8:以前ほど予定利率が高くないので運用商品としての魅力は低いと思います。ただ長期間、例えば20年とか30年をかけて考える、将来の老後資金の積立てや法人で従業員の退職金積立を目的とした福利厚生プランなどは、円に比べて予定利率も高いためメリットがあると考えます。
ドル保険にかぎらず、金融商品全般に言えることですが、大切なことは、契約を検討するときに、「目的と意義」を明確にすることです。
そのうえで各商品の特徴や留意点、メリット・デメリットを把握し、ご自身の「目的と意義」に合致しているかを見極めることです。
今回取り上げたQ&Aは、代表的なものです。
これら以外にも、いろいろな疑問やご不明点があると思います。
些細なことでも構いませんので、ご質問やお問合せがあればお気軽にご連絡ください。
5月に入りGWとなりました。
コロナの行動制限も解除されて各地の観光地では賑わいが戻ってきているようです。
やっとコロナも収束に向かいそうで何よりと思っています。
そんななか、2月以降、コロナ罹患による給付金請求が急激に増えています。
当社にも、3月、4月は、「毎日のように」給付金請求やお問合せをいただいています。
お客様のなかには、病院で入院しないと給付対象にならないと思われている方も多いため、本日はコロナと医療保険請求について解説したいと思います。
新型コロナウイルス感染症は、生命保険会社で契約している医療保険の入院給付金支払いの対象となります。
病院に入院した場合にはもちろん、自宅療養の場合でも入院日額×療養期間が給付されます。
例えば日額10,000円の医療保険に加入していて自宅療養を10日間したとすると、10,000円×10日=100,000円が支払われます。
また家族がコロナ陽性となった場合、同居の家族は濃厚接触者となり7日間の隔離期間がありますが、その後、ご自身も発熱し病院を受診した場合、検査をしないで「みなし陽性」と判定されるケースもあります。
この「みなし陽性」でも10日間自宅療養する必要があり、その場合も医療保険の給付対象になります。
私は、自宅療養とみなし陽性の場合の請求漏れが発生する可能性があると思っています。
お客様でも、たまたま別件でやり取りをするなかで、「コロナで自宅療養しててさ」みたいな会話で知り、こちらから請求を促したケースが多々ありました。
自宅療養の場合には給付対象になると思っていない方が多いのだと思います。
以下、コロナと医療保険についてポイントを箇条書きにしておきます。
・新型コロナウイルスは医療保険の入院給付金の対象となる。
・病院で入院した場合、療養専用のホテルで療養した場合も対象。
・自宅療養でも対象。
・検査をしない「みなし陽性」も対象。
・複数社で加入してる場合、それぞれ別々に給付対象となる。
・請求や給付の情報が他に漏れることはない。
・濃厚接触者は対象外。
該当の心当たりのある方は、契約している保険会社のカスタマーセンター、担当営業職員、担当代理店へご連絡ください。
オミクロン株になったからの感染は、ほとんどの方が風邪と同じような症状で治っています。
そうしたお客様が給付金を受け取ったときの感想は、「臨時収入でうれしい」です。
もらえるものはもらった方がいいですので、是非、請求漏れのないようにしてください。
今朝の東京は、満開の桜に冷たい雨が降り、肌寒い朝を迎えています。
本日は4月1日。
新年度を迎える方も多いと思います。
4月から私たちの生活に影響する制度がいくつか変更されます。
そのなかで、公的年金制度の変更についてご紹介したいと思います。
2022年4月1日から、年金の「繰り下げ受給」の受給開始年齢の上限が、従来の70歳から75歳に延長されます。
端的に説明すると、厚生年金等の公的年金は、原則65歳から受給できますが、それを最長で75歳まで繰り下げて受給することができるようになります。
年金の受給は繰り上げと繰り下げがあり、主な年齢での受給率は以下の通りです。
60歳 76%
65歳 100%
70歳 142%
75歳 184%
つまり75歳から受給を受けると、65歳に比べて、1.84倍多く、年金を受け取ることができます。
※日本年金機構繰り下げ受給解説PDF
65歳以降のライフプランを考える場合、非常に重要な制度変更なので、続けて解説していきます。
私は、今回の制度変更を受けて、以下のようなライフプランも有力な選択肢だと考えています。
65歳まで 労働収入を柱に生活
65歳~75歳 労働収入+私的年金の受給で生活
75歳から 繰り下げで184%に増額された公的年金で生活
将来は65歳以降でも働ける環境を整えた企業も多くなると思います。
なので65歳以降、できれば年金を受け取らず、可能なかぎり75歳まで働いて労働収入を得る。
しかしやはり現実には65歳までの給与水準を維持することは難しく、65歳以降の給与は減額されていくのが現実だと考えます。
そこで現役世代に積み立てた個人年金等の私的年金を65歳からの10年間で取り崩し、給与+私的年金のハイブリッドで生活を支えていきます。
そして75歳になってから184%に増額された公的年金で人生100年時代を豊かに過ごしていく。
令和2年の簡易生命表によると主な年齢からの平均余命は以下の通りです。
| 男 | 女 | |
|---|---|---|
| 60歳 | 24.21年 | 29.46年 |
| 65歳 | 20.05年 | 24.91年 |
| 70歳 | 16.18年 | 20.49年 |
| 75歳 | 12.63年 | 16.25年 |
これを見ると、75歳まで生きた人は、平均で男性は87歳まで、女性は91歳まで生きていくことになります。
75歳から年金を受け取っても、十分な期間、年金を受給できる可能性が高いです。
また現在の年金水準から試算した繰り上げ受給、繰り下げ受給の年金額は以下の通りです。
<令和3年4月分からの年金額>
厚生年金 月額220,496円
※夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額
※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合
※日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について より
この給付水準が維持されるという前提ではありますが、繰り上げ受給、繰り下げ受給した場合の年金額は以下の通りです。
| 年金額 | |
|---|---|
| 60歳 | 167,577円 |
| 65歳 | 220,496円 |
| 70歳 | 313,104円 |
| 75歳 | 405,713円 |
こうして見ると、75歳まで繰り下げて受給すると、年金額は月40万円を超えます。
年間では480万円です。
夫婦二人の生活であれば十分に生活できる金額だと感じます。
ちなみに繰り上げと繰り下げの損益分岐点年齢は以下の通りです。
65歳と70歳:81歳
65歳と75歳:86歳
70歳と75歳:91歳
長生きする自信があれば、75歳からの繰り下げ受給がよいのだと思います。
そうは言っても、75歳で受け取りをはじめて1年2年で亡くなってしまうというリスクもあり、このあたりは難しいところですね。
みなさまはどのようにお考えになるでしょうか。
いずれにしても65歳以降も働けるように、健康を維持し仕事上のスキルを磨いていくということは必要なことだと思います。
また65歳以降のために、個人年金やNISA、イデコなどの積立投資による資産形成の必要性も高まっていると感じています。
この65歳以降のライフプランについては動画でも解説しています。
関心のある方は以下の動画も合わせてご覧ください。
⇒65歳以降のライフプラン(動画)
みなさまのライフプランのご参考になればと思います。
本日から3月に入りました。
コロナ禍が長引くなか、ロシアがウクライナを侵攻し、戦争が始まってしまいました。
戦争で最も被害を受けるのは何の罪もない一般人です。
小さな子供も被害に遭っているようです。
現在、停戦に向けての協議が行われているとのこと。
一刻も早い事態の収束を願っています。
コロナ禍が始まってからここ2年間、お客様とのオンライン面談の機会が増えました。
私のZOOMアカウントには常時オンラインミーティングの予定が入っています。
先日は、鹿児島のお客様とLINEビデオ通話を使い、3人でオンライン面談を行いました。
お相手は2人とも60代の女性です。
また新潟のお客様とは、コロナ禍のため、私も新潟にいながらにして、ZOOMでオンライン面談を実施しました。
ここ最近は、私自身もオンラインに慣れたのと、お客様側もビジネスでオンライン面談を活用する機会も多いようで、お互いに慣れてきて以前よりもよりスムーズにオンライン面談を行うことができるようになりました。
さらに、ある土曜日の午前中、私が自宅に戻ると、小学校1年の息子がノートPCを前にオンラインで授業を受けていました。
担任の先生が30名の生徒を相手に、オンライン授業を進め、各家庭の保護者が横についてサポートしていることもあり、全く違和感なく授業ができていました。
すばらしい授業の進化です。
高齢の方も、現役世代のビジネスマンも、小学生もオンラインでコミュニケーション。
そういう時代になりました。
私は、感染を心配したり、パーテーションやマスク、ソーシャルディスタンスなどさまざまな制約を受けての対面より、こうしたオンライン面談の方がよい部分もたくさんあると感じています。
元々知っている人同士であれば、実際に会って話すのとほとんど変わらない一体感でコミュニケーションが取れます。
ただ、まだまだオンラインに抵抗がある方も多いです。
その理由の一つは、オンラインシステムの設定や操作に不安や煩わしさがあることです。
スマホがあれば、利用者が多い、LINEのビデオ通話が手軽で便利だと思います。
音声電話もテキストでメッセージを送ることも可能で、高齢の方にもお勧めできます。
コロナ禍が続き、人と全く会えていない。
たまには話相手が欲しい。
一日中、家にいて暇。
こんな方も多いのではないでしょうか。
別に具体的な用件がなくても構いません。
ちょっと話をしたい、という方はいつでもご連絡ください。
私でよければいつでも。
設定や操作が分からなければ、電話やメールでサポートします。
コロナ禍が長引き、それが一因となって精神的な病に苦慮されているお客様やそのご家族も何件もあります。
人は人のためにあり。
やはり人は人との触れ合いが大切なのだと思います。
オンライン面談は、電話とはまた違った親近感があります。
少しでも気持ちが軽くなったり、気分転換できたらいいなと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
新年が明けたと思ったらあっという間に1月も終わり、本日から2月に入りました。
オミクロン株の感染拡大でまた自粛モードになってしまいました。
私自身も感染予防に努め、世の中と協調しながら過ごしていきたいと思います。
そんななか、1月は変額保険の販売が好調でした。
近年、個人保険分野では、変額保険等の資産形成商品の関心が高まっていると感じています。
その背景にあるのは、銀行預金の長引く低金利、将来の年金不安だと考えています。
また「つみたてNISA」や「iDeCo」などの長期の積立投資や私的年金制度の充実と普及の相乗効果もあり、隣接商品である変額保険についても関心が高まっているのだと思います。
本日は、お客様からよく受ける質問やお問合せについて比較表にもとづいて解説させていただきます。
以下が代表的な長期の積立投資や私的年金制度の比較です。
| つみたてNISA | iDeCo | 変額保険(有期型・年金) | |
|---|---|---|---|
| 運用商品 | 投資信託・ETFなど | 預貯金・投資信託・保険商品 | 日本株・世界株・債権などの特別勘定 |
| 運用期間 | 20年 | 60歳まで | 任意に選択可 |
| 税制優遇(掛け金) | なし | 全額所得控除 | 生命保険料控除 |
| 税制優遇(運用益) | 非課税 | 非課税 | 一時所得・雑所得 |
| 年間投資上限額 | 40万円 | 14.4万円~81.6万円 | 特になし |
| 資金の途中引出し | 可 | 60歳まで不可 | 可 |
| 加入窓口 | 銀行・証券会社等 | 銀行・証券会社・保険会社等 | 保険会社・銀行・代理店等 |
| 付加価値機能 | 死亡保障 保険料支払免除 |
これを見ると、税制優遇の優位性は、iDeco>つみたてNISA>変額保険 となります。
また途中引出し等の資金流動性は、つみたてNISAと変額保険が優位です。
そして付加価値機能としては、死亡保障があり三大疾病罹患後は保険料支払いが免除される変額保険に優位性があると考えられます。
それぞれの特徴を踏まえてご自身にあった積立投資商品を選択するのがよいと思います。
どれを選択しても、目的は10年以上の長期の積立投資です。
市場の値上がり、値下がりを気にせず、一定額をこつこつと積立投資することで、複利効果でゆっくりと確実に資産を貯めていくことができます。
できるだけ若い時からはじめ、時間を味方にするのも重要な要素です。
人生100年時代を健康で豊かに生活していきたいものですね。
ご参考になれば幸いです。
積立投資や私的年金についてご関心のある方はお気軽にお問合せください。
メールやオンラインでの面談も可能です。
それでは今月もよろしくお願いいたします。
あけましておめでとうございます。
2022年がはじまりました。
今年の干支は、壬寅(みずのえとら)。
その意味するところは、「陽気をはらみ、春の胎動を助く」となり、厳しい冬が過ぎ、春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれること、となるそうです。
約2年間のコロナ禍が終息に向かい、経済も社会も力強く復活する、という意味にも解釈できます。
そんな希望を抱きながら、明るく前向きに過ごしていきたいと思っています。
昨日、私が所属する?友書道会主催の?友書道展表彰式が明治記念館で開催されました。
大人と子供合わせて約4,000点を超える書道展で、表彰式には付き添いも含め約200名が参加されました。
私が指導している小金井・新潟・大宮からも多くの上位入賞者が出て、一緒にお祝いをしました。
書道は日本の伝統文化ですが、昨年、書道界にとって明るいニュースがありました。
書道が登録無形文化財として登録されたのです。
技術継承に取り組む保持団体には、日本書道文化協会が認定され、今後、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産登録を目指しています。
書道は、鑑賞対象であるとともに、文字を学ぶ手本として一般人の生活にも浸透し、芸術性だけでなく生活文化の歴史の上でも価値が高いと評価されました。
無形文化財に登録されたことにより、今後は、技術継承などの活動に国の財政支援を受けられるようになります。
これを機会に書道のより一層の普及を期待しています。
私のライフワークは、経営/家族/販売/保険/書道 で成り立っています。
そのなかで書道は、精神的な豊かさと幅をもたらしてくれている重要な役割を担っていると感じています。
今年も経済活動と書道を通じた文化活動の両輪によって、明るく前向きに過ごしていきたいと思っています。
みなさまにとっても今年1年が良い年になりますように祈念いたします。
今年もよろしくお願いいたします。
本日は12月1日。
早いもので今年も残り1か月となりました。
11月19日、大リーグ、エンジェルスの大谷翔平選手がアメリカンリーグのMVPに選ばれました。
投票した記者30人全員から1位票を集め、満票で文句なしのMVP受賞となりました。
本当にすばらしいことだと思います。
コロナで閉塞感が続く中、大谷選手の活躍は私自身も大きな励みになりました。
シーズン中の朝、仕事前にラジオやネットを通じて大谷選手の活躍を聞いたり見たりして、その日、自分も頑張ろうと元気をもらいました。
まさに歴史的な活躍だった今シーズンの成績は以下の通りです。
<打者>
ホームラン:46本 打点:100 三塁打:8本(リーグ最高) 敬遠:20(リーグ最高)
<投手>
勝利:9 防御率:3.18 奪三振:156 勝率:0.818(9勝2敗)
<走者>
盗塁:26
打って、投げて、走って。
投げては160キロ超えのスピードボール。
打てば140m超えの大ホームラン。
子供のころ、リトルリーグで野球をやっているとき、対戦相手で一人だけ化け物みたいな選手がたまにいました。
大谷選手は大リーグでそれをやりました。
本当に痛快でした。
まだ27歳。
大谷選手を見ていると、まだまだ伸びしろがあるように感じます。
本人もそう言っています。
なのでまた来シーズンが楽しみです。
ケガなく過ごし、来年、今年以上に活躍してくれることを応援したいと思います。
今から20年前、2001年にイチロー選手がMVPと新人王をダブル受賞しています。
20年も前にすでにイチロー選手が偉業を成し遂げていることにも驚きです。
2001年はイチロー選手がオリックスからマリナーズへ移籍した大リーグ最初のシーズンでした。
私も2001年の4月に保険会社へ転職し、フルコミッションの営業職に着いた1年目でした。
イチロー選手の危機感や活躍を自分に重ね合わせ、自分自身を鼓舞して必死に1年間過ごしたことを思い出しました。
あれから20年経った今、大谷選手の活躍に触れ、自分自身をもう一度奮い立たせようと改めて感じています。
今月もよろしくお願いいたします。
今日から11月に入りました。
今年も残り2か月ですね。朝晩は寒い日が続いていますので体調管理に気を配りたいと思います。
本日、11月1日、衆議院選挙の結果が出て、全議席が確定しました。
各政党の議席数と前回からの増減は以下の通りです。
自民党:261(-15)
公明党:32(+3)
立憲民主党:96(+14)
日本維新の会:41(+30)
共産党:10(-2)
国民民主党:11(+3)
れいわ新選組:3(+2)
社民党:1(+-0)
NHK党:0(-1)
諸派:0(-1)
無所属:10(-1)
概要とポイントを記してみます。
1.自民党単独過半数確保
2.自公連立での議席数は293(議席占有率:63%)
3.日本維新の会の躍進
4.立憲民主党の議席減
5.投票率:55.92%(推計)
6.大物議員の小選挙区での落選
自民 甘利幹事長の小選挙区落選(比例で復活)
自民 石原伸晃元幹事長の小選挙区落選(比例でも復活できず)
立憲 小沢一郎氏の小選挙区落選(比例で復活)
私自身は居住区が東京18区であり、菅直人元総理と長島昭文氏の小選挙区での戦いに注目していました。
長島氏が立憲民主党から自民党へ鞍替えし、元の党幹部、それも元総理と同選挙区で戦ったいわば師弟対決だったからです。
結果は、小選挙区で管直人氏が僅差で勝ち、長島氏は比例で復活当選しました。
大物議員の小選挙区落選など時代の変化も少し感じられましたが、やはり自民党が強かった印象です。
それから日本維新の会の躍進が目立ちます。
自民も立憲も嫌いという層の受け皿になったのかもしれませんね。
投票率も相変わらず低いですね。
今回はコロナでの社会不安もあり、政治や選挙に関心を持つ人が多くなって投票率が少し上がるのではないかと思っていました。
期日前投票に行ってもけっこう混んでいたし、当日の投票会場も混んでいたと聞きました。
でも結果は約56%と低い投票率のままでした。
いずれにしても、選挙の結果を受けて、岸田総理体制が改めて始まります。
コロナも感染者が減り、終息が見えてきました。
コロナ後の社会がどう復活するか、日常は戻ってくるか、経済は立て直せるか。
これらは私たちひとり一人の努力がもちろん大切ですが、政治の役割も大きいと思います。
今後、任期4年間の舵取りは、岸田体制に任せるしかありません。
是非、期待したいと思います。
今月もよろしくお願いいたします。
このメルマガは毎月1日に送信していますが、今回、非常に有益と思われる保険商品の情報提供があり、特別版として配信させていただきます。
よろしければ是非ご一読ください。
当社の取扱い保険会社の1社である、SOMPOひまわり生命から、がん保険の新商品「健康をサポートするがん保険 勇気のお守り<終身がん保険(C2)(がん治療給付型)(Ⅰ型)、終身がん保険(C3)(がん診断給付型)>」が10月2日に発売されました。
従来のがん保険にはない商品仕様、付加価値サービスがあり、充実した内容となっています。
新たにがん保険の加入を検討されている方、または今のがん保険を見直そうと検討されている方にとっては、選択肢の一つとしてお考えになることをお勧めします。
新しいがん保険の注目すべきポイントは以下の5点です。
1.非喫煙者保険料率の新設
たばこを過去1年間吸っていない方は割安な保険料で申込みができます。
2.自宅でできるがんリスク検査サービスの提供(有料)
一滴の尿から15種類のがんリスクを高精度に判定できるHIROTSUバイオサイエンス社の「N-NOSE」。
だ液で最大6種類のがんリスクがわかるサリバテック社の「SalivaChecker」。
サービス利用にはSOMPOひまわり生命のマイリンククロスの登録が必要です。
3.二種類の主契約からニーズに合わせて選択可能
A.毎月の治療費をサポートできる「がん治療給付型」
B.まとまった一時金を確保できる「がん診断給付型」
4.がん保険料免除特約
初めてがんと医師により診断確定されたとき、以後の保険料の支払いが免除されます。
5.責任開始後保険料払込方式の導入
がんに対する保障の開始は、従来通り、契約から3ヶ月経過後ですが、契約からがん保障開始までの3ヶ月間は保険料が発生しません。
●本がん保険の保障はご契約から3ヶ月後に開始し、がんの保障開始以降に保険料が発生する仕組みです。
●ご契約からがんの保障の開始までの3ヶ月間は保険料が発生しませんが、保険料を割り引いているものではありません。
このように、新しいがん保険は、がん予防・早期発見・万が一の保障・治療後のケアまでトータルにサポートする、今までにないコンセプトで設計されています。
その他、詳細は以下のSOMPOひまわり生命かのWEBページをご参照ください。
ご関心のある方はお気軽にお問合せください。
個別の設計書を作成してご提供させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
10月に入りました。
9月は政治の世界でいろいろな変化がありました。
菅総理の辞任、自民党総裁選挙、岸田総裁誕生、そして10月4日には岸田新総理が誕生する予定です。
そして本日10月1日、コロナの緊急事態宣言が全面解除されました。
10月というのは下半期のはじまりですが、このような大きな変化があり、例年以上に心機一転の気持ちが強くなっています。
緊急事態宣言が解除されましたが、全国で緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が発令されていない状態は4月4日以来、約半年ぶりです。
東京でも飲食店で20時までの酒類提供が解禁されます。
長く休業していた知り合いの飲食店も今日から営業再開されるとのこと。
コロナ騒動がはじまってから1年半、自粛と緩和を繰り返してきましたが、今、長い自粛期が終わり、緩和期が始まりました。
宣言解除で旅行・外食需要が急回復、という記事もあります。
ANAやJALでは10月運行分の予約数が急増しており、旅行代理店でも旅行予約が1か月前の2倍に増えているとのこと。
今までの経験上、緩和期を経て、また第6波が来てすぐに自粛期になると予想し、だからこそ短くなるかもしれない今の緩和期を楽しもうと思っている人が多いのかもしれません。
9月17日、政府は新型コロナワクチンの3回目の追加接種(ブースター接種)を国内で実施する方針を固めました。
2回目接種から8か月以上の間隔を空けて、12月頃から医療従事者から追加接種が始まる可能性があります。
その後、順次、高齢者への3回目接種がはじまり、私たち世代の3回目接種は来年の春以降ではないでしょうか。
3回目接種でコロナの景色が変わる、という専門家も多いです。
そうすると本来のコロナ終息は来年の春か夏頃と推察できます。
それまではやはり、感染者数が増えたり減ったりして、自粛と緩和を繰り返すのだと思います。
だからこそ、今からの緩和期をできるだけ有意義に過ごすということは大切なのではないでしょうか。
秋のシーズンは楽しみがたくさんあります。
スポーツ、観光、芸術、旬の食材。
私自身も、コロナで会えず、ご無沙汰している方と実際に会ったり食事したりしながら、楽しい時間を過ごしたいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
9月に入りました。
まだまだ残暑が続いていますが、今朝の東京は曇っていて涼しく、少しずつ秋の気配を感じ始めました。
私は、8月18日にモデルナ製ワクチンの2回目接種が完了しました。
新型コロナウイルスの免疫ができるのは2週間後くらいからということなので、私自身はコロナに対してある程度の防御ができたものと思っています。
また仕事上でも、相手がワクチン接種を完了していれば、オンラインではなく、リアルな面談のための訪問を積極的にしていきたいと考えています。
私も相手もワクチン接種済で、仕事の商談程度の接触であれば、お互いに感染リスクは限りなく低いと考えられるからです。
しかし東京はまだ緊急事態宣言中で、昨日の感染者数も約3,000人で高い水準が続いており、油断ができません。
当社のお客様からもコロナ感染の報告を受け、入院給付金の手続きが増えています。
ちなみに新型コロナウイルス感染による入院は医療保険等の入院給付金支払いの対象となり、自宅療養でも入院とみなされ対象となります。
感染は増えているもののその年齢層は若年齢層へシフトしていると感じます。
20代の方の感染報告が直近で2例あり、両親と同居していました。
その両親も濃厚接触者のためPCR検査を受けましたが、2例ともに結果は陰性。
20代ご本人のみが陽性で自宅療養をされました。
2例のご両親に共通していることは、ご両親ともにワクチンの2回接種が完了していることです。
もしワクチンを接種していなかったら、同居しているわけですからご両親ともに感染していた可能性が高かったと思います。
ワクチンが絶対ではありませんが、これらの事例からも、やはりワクチン接種は感染予防のキーポイントにはなると改めて感じます。
また1回目接種後に感染された事例もあります。
2回目接種の直前に感染というのは不運でしたが、やはりワクチンは2回接種が重要なのだと思います。
幸いこの30代のお客様も自宅療養を経て、今は元気にされています。
2回目接種でも半年程度で免疫が低下するなど、いろいろな課題もあるようですが、ワクチンがコロナ克服のキーポイントであることは変わらないと思います。
あとは20代30代の方への接種が進めば、状況がずいぶん改善されるのではないでしょうか。
若い世代で接種を希望しているにもかかわらず予約ができないという例が多いみたいですね。
政府には、ワクチン供給を十分に確保いただき、希望者が少しでも早く接種できるように体制を整備してもらいたいと願っています。
このメルマガで何度も「あと少しの辛抱」と呼びかけていますが、社会の状況はなかなか変わってきません。
ですが、諦めず、辛抱強く明るい未来を思い描きたいと思います。
コロナが終息し、いつもの日常が戻ってくることを願っています。
今月もよろしくお願いいたします。
8月に入りました。
先日からはじまった東京オリンピックが盛り上がっています。
8月1日現在で、日本のメダル獲得数は、金17個・銀5個・銅9個、合計31個です。
金17個は、前回の東京オリンピックとアテネオリンピックの16個をすでに上回り、日本の金メダル獲得数としては過去のオリンピックで最多となっています。
まだ残り1週間ありますので、これからも金メダルを上乗せしてくれるでしょう。
今回のオリンピックでは、
・期待されて期待通りの成果を出せた選手
・期待に応えれず不本意な結果となってしまった選手
・期待以上の結果で新たなヒーローとなった選手
など結果を見ればさまざまな境遇の選手がいます。
しかしどの選手も試合後のインタビューでは謙虚で清々しい内容でした。
思った結果を出せなかった選手も言い訳は一切ありませんでした。
それぞれの選手が自分のベストを尽くした結果であるからだと思います。
コロナ禍で1年延期になった東京オリンピック。
開催直前まで賛否両論ありましたが、私はやはり開催してよかったと思っています。
コロナで普段の娯楽が制限されているなか、私たちの楽しみをオリンピックは与えてくれていると感じます。
8月8日の閉会式まであと1週間。
残る期間も応援したいと思います。
選手たちの活躍をみて、私自身の振る舞いを自問しています。
コロナを言い訳にしていないか。
毎日を全力で過ごしているか。
結果に厳しくこだわっているか。
こう自問すると私は自分自身が甘いと感じます。
オリンピック選手から希望た励みをもらうだけでなく、自分自身への今後の成長のために学んでいきたいと改めて感じています。
今回オリンピックの動画特集をリンクしておきます。
ご関心のある方はご覧ください。
朝の通勤時などに見ると元気が出ると思います。
今月もよろしくお願いいたします。
時が過ぎるのは早いもので2021年も半分が終わり、今日から7月に入りました。
今月は東京オリンピックが開催されます。
オリンピックは、7月23日~8月8日、パラリンピックは、8月24日~9月5日で予定されています。
コロナ禍のなか、オリンピック開催の是非は日本中、世界中でさまざまな意見がありましたが、開会まであと22日と迫った今、東京オリンピック開会は予定通りに実現するものと考えてよいと思います。
私自身も、コロナ禍が終息しない状況でオリンピックを開催してよいものなのか、その是非に関する考えは揺れ動きました。
感染がまた拡大するのではないか。
各種イベントや運動会などの学校行事が中止されたり、我慢を強いられている国民が多いなか、オリンピックだけが特別扱いされてよいのか。
そんなことを思ったりした時期もありました。
しかし、開催が現実のものになった以上は、オリンピックが東京で行われることを歓迎し応援したいと思います。
何よりもここまで想像を絶する努力を続けてきた代表選手には心から応援したいと思います。
感染症のパンデミックが収まらないなか、1年延期されてのオリンピック。
私にとっては、人生で最初で最後の日本開催のオリンピックになると思っています。
ある意味では一生の思い出になると思います。
今年は東日本大震災から10年です。
当時、被災地での炊き出しで、心身ともに大変ななかでも列を乱さず秩序を保ちながらきちんと自分の順番を待つ姿に胸を打たれました。
海外でも大きく報道されたと聞きます。
10年経ってもまだ不自由な暮らしをされている方も多いかもしれませんが、やはり力強く復興をしていると思います。
そして今回のコロナ。
政府も自治体もできる限りの感染対策や経済対策をしていますが、やはり私たち国民ひとり一人の努力が大きいと思います。
他国に比べ、感染者数も死者数も少ないのは、私たちひとり一人の自粛力によるところが大きいのではないでしょうか。
復興力と自粛力。
これは世界に誇れる日本人の強みだと感じています。
オリンピックはその強みを世界にアピールできる大きな機会だと思います。
今回のオリンピックはイベントとしてはいつもとは様相が違うものかもしれません。
ですが、競技そのものはいつもと変わりありません。
世界から集まったトップアスリートが技と力を発揮し、いつものオリンピックと同じように多くの感動を与えてくれると思います。
日本の代表選手にも期待しています。
水泳池江選手の白血病を克服しての復活、バトミントン桃田選手の悲願の金、体操内村選手の底力、柔道各階級でのメダル、野球、サッカー、ソフトボール、ゴルフ松山選手のメダル、出場選手をみると楽しみにがたくさんあります。
東京オリンピックの成功を応援します。
最後にオリンピック開催にともない、7月・8月は祝日が移動されてますね。
以下をリンクしておきますので今後の予定の参考にしてください。
⇒2021年の祝日の移動について(首相官邸)
今月もよろしくお願いいたします。
今日から6月に入りました。
東京は6月20日まで緊急事態宣言が延長され、まだまだ不自由な生活が続いています。
そんななか、各地でワクチン接種が進んでいます。
菅総理は、「1日100万回接種」「7月末までの高齢者接種完了」の目標を掲げていますが、5月初旬時点ではその接種体制について疑問がありました。
しかしここ最近になって、ワクチン接種のスピードは確実に加速していると思われます。
以下は高齢者の4月下旬と5月下旬のワクチン総接種回数です。
4月30日 23,330
4月29日 11,368
4月28日 31,793
4月27日 32,782
4月26日 23,840
5月30日 200,187
5月29日 232,285
5月28日 312,794
5月27日 353,455
5月26日 371,561
これまでのワクチン総接種回数(高齢者等)5月30日時点 首相官邸 より
新型コロナワクチンについて 首相官邸 より
直近の回数は減少していますが、これは過去の数値実績からみて集計の遅れにより数値が反映されていない可能性が高く、接種回数は1か月前と比べ、約10倍増と、確実に接種スピードは加速しています。
ただし7月末までに高齢者接種を完了させるためには1日100万回接種が必要であり、現状ではまだ十分ではなく、さらに急激な加速が求められます。
現状を受けて、政府は、さらなる接種スピードを加速させるため、自治体や国の会場に加え、6月下旬には職場や大学での接種を始めるとのこと。
さらに臨床検査技師と救急救命士による接種も認め、ワクチン接種の場所と打ち手を増やすことで接種を加速しようとしています。
今まで日本は他国に比べワクチンの接種スピードが遅いと指摘されていましたが、「今からできることにベストを尽くす」という観点からすれば、対応が遅くなったとはいえ、目標に向かっての対策はされていると感じます。
またワクチン予約をめぐり電話がつながらないなどの混乱を聞きますが、自治体によっては創意工夫によってそうした混乱を事前に回避しています。
以下は新潟県上越市の取り組みです。
上越市では、集団接種で使う会場、接種日、時間を割り振ったうえで、住民に通知する方法をとっています。
そのため予約は不要です。
ただし接種日を変更したい人や接種を受けない人についてのみ、市へ連絡することになっています。
こうすることで予約の手間と混乱を避けて、接種を円滑に進める対策をとっています。
このような費用や高度な仕組みの必要がなく、ちょっとした創意工夫で事態を大幅に好転させる取り組みというのはすばらしいと思います。
⇒上越市ホームページ
現在、すでに高齢者接種を進めている自治体では接種の手法を今から変えることは難しいかもしれません。
ですが、今後、高齢者接種が終わっても、基礎疾患のある人、その後の65歳未満の一般の人の接種は続きます。
全国、特に人口の多い地域の自治体では、既存のやり方にとらわれず、上越市のやり方を参考に、より効率的な接種体制を構築していって欲しいと思います。
欧米ではワクチン接種が進み、感染リスクが低下し、経済が復活してきています。
経済復活の鍵はワクチンだと思います。
この調子でいけば、あと2か月もすれば、ワクチン接種済のお金と時間のある65歳以上の人が、旅行に行ったり食事に出かけることで、経済回復の足掛かりができるのではないでしょうか。
出口はもうすぐと信じ、また6月も1か月間、一生懸命に仕事に取り組みたいと思います。
今月もよろしくお願いいたします。
5月の連休が明け、当社も本日から業務を再開しました。
昨年の5月を振り返ると、緊急事態宣言発令の期間中でした。
あれから1年が過ぎましたが、コロナ禍は全く終息せず、また現在、3回目の緊急事態宣言となっています。
また政府では、当初5月11日期限としていた緊急事態宣言を、明日7日にも延長することを検討しているとのことで、再度、2週間から1か月間の緊急事態宣言延長の可能性が高まっています。
これにより緊急事態宣言の期間が、5月25日まで、または6月11日あたりまで延長される可能性が出てきました。
飲食店では時短営業要請に、アルコール類の提供自粛の要請も加わり、社会に対するコロナ禍の影響は良化するどころか、1年前と比べてもむしろ悪化しているような印象を持ちます。
またコロナに対抗する政策についても、「経済活動を正常化し感染者増を容認しながら医療体制の抜本的な強化を行う」「経済をロックダウンさせ感染者を極端に減らす代わりに事業者に対しては相応の補償をする」というどちらか両極端な方向へ大きく舵を切るということも難しい現状を考えれば、出口が見えない状況とも受け取れます。
しかし、どのような状況であっても、私たちは未来への希望と光を見出さなくてはならないと思うし、わずかですがそれがあると考えます。
1年前と比べて、大きく違う点は、有効なワクチンが存在するということです。
私はコロナ終息の最大にして唯一の鍵はワクチン接種だと考えています。
菅総理は、7月末までに高齢者3,600万人へのワクチン接種を完了させるという目標を掲げています。
あと3か月で3,600万人。
ワクチンは2度接種する必要があるので、3か月で延べ7,200万回の接種を完了させる必要があります。
これを考えたとき、1日あたりの必要接種回数が割り出されます。
すなわち、1日の必要接種回数は、7,200万回÷90日間=80万回 となります。
1日80万回のワクチン接種で7月末までに高齢者への接種が完了します。
しかし、現状はどうか。
首相官邸ホームページによれば、高齢者へのワクチン接種の日別実績は直近で以下のようになっています。
4月26日 13,266回
4月27日 16,654回
4月28日 13,999回
4月29日 3,221回
⇒首相官邸 新型コロナワクチンの日別実績
これを見ると、1日1万人ちょっとです。
これではとても1日80万回には追い付きません。全く話にならないレベルです。
連休明けにワクチン供給量や接種体制が大幅に増強する予定のようです。
自衛隊活用による政府主導の大規模接種会場も運用がはじまるとのこと。
ぜひ政府には、1日80万回、7月末までの高齢者3,600万人への接種完了という目標を達成していただきたいと思います。
ワクチン接種をコロナ対策の第一優先順位として位置づけ、接種体制の抜本強化を国民の一人として強く求めたいと思います。
これが出来れば、8月以降、私たち世代の一般人も接種が進み、今年中には集団免疫が獲得でき、コロナ終息に向かうと考えています。
コロナパニックが終息し、日常が戻ることを願っています。
今月もよろしくお願いいたします。
今日から4月に入りました。
東京の桜はすでに満開を過ぎ、少しずつ散り始めています。
それでも連日暖かい日が続き、春を感じさせる爽やかな天気が続いています。
今日から新年度ということで、私たちの生活にかかわる制度にいくつか変更点があります。
そのなかで4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法について取り上げたいと思います。
これは70歳までの就労機会をつくることが企業の努力義務となった改正です。
今まで65歳だったので、5歳伸びました。
現在は努力義務なので実施しなくても社名公表はされませんが、将来は、「実施義務」となる可能性もあります。
いずれにしても、少子高齢化、長寿化を背景とした社会保障費の増大を抑制させるために、できるだけ長く働いていく必要性はますます高まっているのだと思います。
経営者側も雇用者側も70歳までは働くという時代になったと認識するという意識改革が必要になってきていると感じます。
改正後の高年齢者雇用安定法の概要は以下の通りです。
次の(1)〜(6)のいずれかの措置を講じるように努める必要があります(努力義務)
(1)70歳までの定年の引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
⇒高年齢者就業確保措置について(厚生労働省)
(6)などは65歳以降などにフリーランスや起業などして元の勤務先から業務を外注してもらって収入を得るというイメージです。
企業はこれらいずれか1つを導入すればよいので、直接雇用しない㈬のような形態も選択できるわけです。
そうなると雇用される側も高齢になっても業務を委託してもらえるような専門的な技能や営業力が求められてきますね。
これからの働き方について、私自身も将来のことを考えていきたいと思っています。
65歳以降、70歳以降のライフプランについて、過去の動画で配信しています。
今後、特に65歳以降は、労働収入・公的年金・私的年金をどのようなタイミングでどのように組み合わせるかということが、人生100年時代を少しでも豊かに過ごすために、非常に重要な課題だと考えています。
現役世代の方には役立つ考え方だと思います。
よろしければ以下の動画をご覧ください。
⇒65歳以降のライフプラン(前編)
今月もよろしくお願いいたします。
今日から3月に入りました。
新型コロナワクチンは、2月17日から医療従事者への接種がはじまり、65歳以上の高齢者への接種は4月12日から開始されるとのことです。
また東京でも3月7日を期限に緊急事態宣言が解除される見込みです。
1歩ずつ、少しずつですが、コロナ終息へ確実に進んでいると感じています。
そんななか、コロナに関連する保険実務も対応すべき事例が出てきています。
先日も当社のお客様がコロナ陽性の診断を受け自宅療養されたため、入院給付金お支払いの手続きをさせていただきました。
でもこのお客様からの申し出でご請求をいただいたわけではありませんでした。
久しぶりにお会いしたとき、雑談のなかで、年末年始にかけてコロナで自宅療養していた、というお話を聞いたことがきっかけでした。
お客様の意識では医療保険の入院給付金の対象になるとは思っていなかったかもしれまんが、私が直接お話を聞けたことで、ご請求を促すことができたのでした。
請求いただき、すぐに11日間分の入院給付金が支払われました。
実はこういうお客様がけっこう多くいるのではないかと思っています。
つまりコロナでホテルや自宅で療養し、特に治療をすることなく回復された方は、医療保険に入っていたとしてもそれが給付金支払いの対象となるとは思っていないお客様が相当数いらっしゃるのではないかということです。
なので保険会社や代理店がしっかりと能動的にサポートしないと請求漏れが生じてしまうと思うのです。
そのため広く周知いただきたいと思い、このメルマガで取り上げさせていただきました。
新型コロナウイルス感染症を原因とする入院は医療保険の入院給付金支払いの対象になります。
そしてその入院先(療養先)は、病院はもちろん、医療機関の事情によりホテルや自宅などの臨時施設で療養した場合も同様に入院給付金の対象となります。
保険会社に提出する書類も多くの場合、医師による証明書や保健所・自治体の発行する書類等での簡易請求が可能です。
ちなみに下記はある保険会社の2020年11月30日までの新型コロナウイルス感染症による入院給付金および入院一時金の支払い実績です。
支払件数:1092件 平均入院給付金支払日数:約14日
1社だけでこの数です。
全社合計では相当の数の方がすでにご請求されているはずですが、同時に、コロナ感染の経験がありながら、まだ請求していない方も多くいると推察しています。
心当たりのある方、またはご家族がいらっしゃいましたら、保険会社や代理店にお問い合わせのうえ、是非ご請求されてください。
このメルマガの情報が少しでもお役に立てばと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
本日から2月に入りました。
コロナ騒動から約1年が経過し、数多くの企業や研究機関で新型コロナウイルスに対応できるワクチンの開発が進み、日本でも実際の接種に向けた体制が整いつつあります。
新型コロナワクチン接種推進担当の河野大臣は動画メッセージの冒頭で以下のように語っています。
「ワクチンは、新型コロナウイルスの感染症対策の決め手となるものです。」
私もそう思います。
課題は残るものの、ワクチン接種が進むことで、これまでの不安と混乱の大部分が改善されると期待しています。
人類が、今回の感染症も克服する道筋が見えてきたのではないでしょうか。
コロナは確実に終息の方向に向かっていると信じます。
まだまだ不自由な日常が続きますが、もう少し、辛抱したいと思います。
厚生労働省および首相官邸から発信されている情報をもとに、新型コロナワクチンについての情報を以下の通り抜粋します。
ご参考にしてください。
1.接種が受けられる時期
医療従事者等への最初の接種:2月下旬から
2.接種回数:2回
3.接種を受ける順位
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)それ以外の方
4.接種場所:居住地域の医療機関または接種会場
5.接種の手続き
市町村から「接種券」と「お知らせ」が届く⇒自身の接種可能時期確認⇒接種な書検索⇒電話やネットで予約⇒接種券と本人確認書類を持参して接種
6.接種費用:無料(全額公費)
7.接種を受ける際の同意:強制ではない。接種の同意がある方のみ接種
8.副反応が起きた場合の健康被害救済制度
予防接種法に基づく救済あり
9.効果
70%~95%
※数万人にワクチンとワクチンでないもの(生理食塩水または他の既存ワクチン)のどちらかを2回投与し、発症者や重症者の発生頻度を比較。ワクチンを接種したグループでは、ワクチンでないものを接種したグループより約70%~95%発症者が少なかったと報告されています。
出典元
新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(厚生労働省)
新型コロナワクチンについて(首相官邸)
一般的にインフルエンザワクチンの効果は50%程度と言われています。
それに比べ、70%~95%というのは相当高い効果だと思います。
医療従事者の方や研究者、開発者の方に感謝です。
これから1ヶ月、2ヶ月と日を追うごとに、コロナの状況が改善されていくことを願っています。
接種可能な時期が来たら、私自身もワクチン接種を受け、自身と他者への感染予防に努めたいと思います。
今月もよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
当社は本日1月5日から業務を開始いたします。
本年もよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染が再拡大していることで、政府は7日にも緊急事態宣言を再発令するとのことです。
年明け早々、暗い話題ではじまってしまいましたが、日経新聞によれば、今回の緊急事態宣言の概要は以下の通りになる見通しです。
1.対象区域:東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県
2.時期:1月7日から1ヶ月程度
3.知事の権限:住民への外出自粛要請、施設の使用制限、音楽イベントなどの開催制限
4.営業制限の対象:飲食店中心に検討(20時までの時短営業の要請)
5.学校:休校しない方針
飲食店、宿泊観光業にとっては、本当に厳しい状況が続きます。
コロナの影響はいつまで続くのか、先の見えない不安が大きいと思います。
しかし、厳しいのは、飲食店だけでなく、日本人全員が不自由な暮らしを続けており、我慢しているのだと思います。
みんなが疲れてきています。
それでも今日明日の生活のために、前を向いて、必死に生きています。
歴史上、感染症のパンデミックはいくつか事例がありますが、そのすべてを人間は克服しています。
だから、今回のコロナもいつかは私たち人間は克服すると確信しています。
人類が2年以上パンデミックで苦しんだ歴史はないそうです。
ワクチンもできてきています。
そして世界の研究機関でより有用なワクチンの開発を継続的に進めており、今後、さらに安全で効果の高いワクチンができてくるでしょう。
また有効な治療薬もできてくるでしょう。
私は出口はもうすぐだと信じます。
頑張れ日本!
希望は心の太陽と言います。
できない理由を考えるだけでなく、進むための方法を考えることも必要だと思っています。
年のはじめに大前研一氏の言葉をご紹介します。
===
人間が変わる方法は3つしかない。
1番目は時間配分を変えること。
2番目は住む場所を変えること。
3番目はつきあう人を変えること。
最も無意味なことは「決意を新たにする」ことだ。
===
私自身、肝に銘じ、行動していきたいと思います。
2021年がすばらしい一年になりますように。
本年もよろしくお願いいたします。
今日は12月1日。
早いもので今年も残り1ヶ月となりました。
今年はコロナで1年終わってしまうような印象ですが、今また感染拡大の局面にあり、油断できない毎日が続いています。
先日、11月24日、日経新聞に以下の記事が掲載されていました。
生保14社、4~9月期の新契約約42%減収 対面営業自粛で
主要生命保険会社14社の今上期4月~9月の新規契約の保険料収入(新契約年換算保険料)は、対前年同期比で約42%減収だったとのこと。
この最たる理由は、新型コロナ禍に伴う対面営業の自粛です。
4月~6月の約3ヶ月は、新規の対面営業を自粛した保険会社も多く、その影響がそのまま反映された結果です。
保険会社の売上高にあたる収入保険料は、私たち代理店や直販営業職員が挙げた契約の積み重ねなので、保険会社の新規契約が減ったということは、私たち代理店の新規契約も減ったということです。
当社の今上期の売上高も対前年比で19%減となっており、市場全体の減少率と比べれば健闘しているものの、やはりコロナ禍の影響を受けました。
このような保険会社の業績不振の報道があると、お客様からは、保険会社の財務や経営の健全性について不安視されることもあります。
しかし、現時点では、保険会社全体の経営状況は依然として底堅いと思っています。
その理由は、新規契約の業績が落ち込んでも、生命保険会社の収入の大半は既存の契約から得られる保険料であり、既存契約で支えられた生命保険会社各社の業績への影響は限定的であるからです。
しかし、ここ数年、生命保険業界は、利率低下による貯蓄性商品の販売減、税制変更による法人保険の販売減と、外部環境の変化による厳しい状況が続いています。
そして今回のコロナ禍での新契約減となり、このままの状況が長引けば、生命保険業界全体の業績不振につながります。
幸い、今下期、10月からの状況は、コロナ前の状況まで回復してきている実感があります。
この下期10月~3月のV字回復により、2020年度通期では前年度並みの業績で落ち着くことを願っています。
私たち保険販売に携わるものは、このような時期こそ、お客様第一主義を徹底することが重要だと考えています。
何をすればお客様に喜んでもらえるか、どうすればお客様のお役に立てるかを常に考え、プロとして品質の高い仕事に取り組んでいきたいと思っています。
ここ最近は気温も下がり、乾燥した天候が続いています。
コロナはもちろんですが、風邪やインフルエンザにも罹りやすい状況です。
みなさまにおかれてはご自愛いただき、一年の締めくくりをされてください。
今後ともよろしくお願いいたします。
11月に入りました。早いもので今年も残り2ヶ月ですね。
私は、毎月1回~2回、新潟に出張しています。
10月22日~23日に出張したときは、上越新幹線が半額、宿泊先のホテル日航新潟が35%OFF、さらに15%分のクーポンをいただきました。
現在、政府でGOTOトラベルキャンペーンが実施されており、加えてJR東日本で「お先にトクだ値スペシャル」というキャンペーンが実施されており、JR東日本管轄の新幹線と在来線特急が半額(50%OFF)で乗車できます(20日以上前の予約要)。
また、年末に家族と旅行でもと思って箱根湯本周辺のホテルや旅館の予約をしようと思い、よさそうなところ10件に電話やネット予約を試みましたが、すべて満室で断られました。
やっと1件、予約できそうな旅館がありましたが、料金が高すぎて費用対効果が合わないと思い、箱根を断念し、他の場所に行くことにしました。
今、年末にかけて、旅行需要は非常に高まっていると感じます。
コロナで危機的な状況だった観光業界にとって、このGOTOトラベルの恩恵は大きいと思います。
税金の大判振る舞い、感染拡大の懸念など、いろいろとデメリットもあるのかもしれませんが、私は人が往来することによる経済的なメリットの方が大きいと思うし、今回のGOTOトラベルの経済効果は想定以上に大きいと感じています。
現在、ホテルもレストランも感染防止のための対策は徹底されています。
私自身、宿泊や食事をすることによる感染リスクを感じることはほとんどありません。
今後、GOTOトラベルは、ビジネス利用の場合には制限がかけられるようですが、プライベート利用の場合にはまだまだ利用できます。
価値観はさまざまですが、家族旅行などに出かける場合には、キャンペーンを利用すると本当にお得です。
以下、キャンペーンの概要をリンクしておきますので、ご関心のある方は是非ご覧ください。
1.GOTOトラベル 旅行者向け公式サイト
2.えきねっと限定 お先にトクだ値スペシャル
秋本番です。
食欲の秋、芸術の秋、観光の秋、スポーツの秋。
コロナは油断できませんが、それぞれが感染防止に努め、少しでも日本の美しい秋を楽しめるといいですね。
今月もよろしくお願いいたします。
今日から10月に入りました。
ここ数日の東京は急に涼しくなり、例年よりも秋の訪れが早いような気がしています。
先日の4連休は、各地の観光地で相当賑わったようですね。
今までの自粛によるストレスが一気に発散された印象です。
東京は電車も飲食店も混みはじめました。
ですが、引き続きコロナは油断できない状況にあり、私自身も気を付けたいと思っています。
飛行機や飲食店でマスクをする・しないでトラブルになっているケースが目につきますね。
私は、その施設、お店の定めたルールには従うべきだと思っています。
しかし、コロナへの緊張感が少しずつ薄れるなか、自粛派と経済優先派のような考え方の違いが目立つようになっていると感じます。
遅くまで営業する飲食店を非難したり、逆に、コロナに神経質になっている人に対して気にし過ぎだと揶揄したり。
コロナは、年齢や既往症、家族構成やライフスタイル、その他さまざまな事情によって、その警戒度合いは全く違います。
実際、重症化する危険度も全く違います。
なので、個々の価値観の違いは私たち一人一人がお互いに尊重しなければならないと思っています。
自粛派は経済優先派を非難し、経済優先派は自粛派を非難する。
これは一見、立場は違うようにみえても、両者とも「心根」は同じだと考えます。
それは、人を変えよう、という心根です。
もちろん自分自身の行動が誰かに迷惑がおよぶことは自重しなければなりませんが、自分の価値観を押し付け合うということも避けなければいけないと考えます。
今まで何度も書いてきた言葉ですが、以下の言葉は、コロナ対応にも適用できると思います。
過去と他人は変えられない。
未来と自分は変えられる。
私たち一人一人が価値観の違った相手を尊重しあう。
私自身もそうありたいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
先月のメルマガで間違いがありました。
「理学療養士、言語療養士、作業療養士」と記載しましたが、正しくは、「理学療法士、言語聴覚士、作業療法士」でした。
お詫びして訂正いたします。
ご指摘いただいたY様、ありがとうございました。
本日から9月に入りました。
今朝の東京は小雨が降っており、半袖では肌寒いくらいの気温で、季節の変わり目を感じています。
先週、8月28日に安倍総理が健康上の理由で辞任を表明されました。
7年半にわたる国政へのご尽力に敬意を表したいと思います。
今月の早い時期に次期の総理大臣が決まるようです。
コロナ禍に不況対策など、課題は山積みですが、新しいリーダーの舵取りに期待したいと思います。
話題は変わりますが、3月中旬に不運にも伯父が交通事故に遭いました。
当日に救急車で緊急搬送され、大学病院のICUに1ヶ月半の入院、リハビリ病院で約3ヶ月の入院を経て、8月上旬に退院しました。
その間、私は、病院・保険会社・役所・地域包括支援センター・その他関連各所との窓口として携わりました。
伯父の療養期間のなかで一番強く感じたことは、日本の医療・福祉体制は、非常に充実していてすばらしいということです。
・高齢者医療制度により医療費は1割負担で高度な医療を受けられること。
・高額療養費制度により月額の自己負担医療費は50,000円以下であること。
・リハビリ病院では、理学療養士、言語療養士、作業療養士の各有資格者から高度で専門的、科学的なリハビリ療養が受けられること。
・面会禁止やさまざまな対策によりコロナはじめとする感染症対策が徹底されていること。
・病院、自治体、地域包括支援センターなどの関連機関の連携により必要なハード、ソフト両面の支援が受けられること。
・要支援2の認定により、自宅の手すり取付など在宅介護のための改修が介護保険の適用となり自己負担の工事費は1割ですむこと。
・週に2度のデイサービスの利用が介護保険の適用となり低料金でサービスを受けられること。これにより家族の介護負担が軽減できること。
・民間の医療保険や傷害保険、公的な健康保険の組み合わせにより、医療費や介護費用の経済的な自己負担はほぼなくなること。
・医師や看護師、その他の医療従事者は、使命感が高く献身的で思いやりのあるサービスを提供してくれること。
・在宅介護にともない、定期的な訪問看護により医療的な支援を継続的に受けられること。
ちょっと思いつくままに挙げてもこれだけの恩恵を受けることができました。
他国のことは分かりませんが、日本の医療・福祉体制はすばらしいと思います。
伯父も伯母も80代です。
退院したとはいっても、これからの在宅介護は伯母にとっても大きな負担となると思います。
私はこれからも親族として、保険担当者として、ファイナンシャルプランナーとして、できるかぎりのサポートをしていきたいと思っています。
新型コロナウイルスは、感染拡大がピークアウトしていく傾向にあるとはいえ、まだまだ油断はできません。
ですが、欧米に比べて日本は、感染者も死亡者も圧倒的に少ないということは事実です。
これにはさまざまな要因があると思いますが、日本の医療技術や医療体制がしっかりしていることも大きな要因の1つであるのではないでしょうか。
これは、伯父の入院療養を身近でみて強く感じたことです。
医療従事者の方々には感謝しています。
まだまだ先は長いかもしれませんが、新型コロナウイルスは終息する方向には向かっていると思います。
自粛と緩和、感染防止と経済活動、どちらにも極端にならずに、ねばり強く、自覚を持って、コロナと向き合っていきたいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
8月に入り、東京もやっと梅雨が明けました。
これから夏本番ですね。
7月5日に母校佼成学園野球部のOBによる選手激励会がグランドで行われました。
今年はコロナ禍により、甲子園大会は中止。
ですが、各都道府県では独自大会が実施されており、佼成学園も、西東京大会に出場しています。
激励会では、歴代のOBが集まり、寄付金による記念キャップの贈呈、一部のOBからボールの寄付などが手渡され、代表OBより選手たちへ激励の言葉が発せられました。
30年前に毎日練習に明け暮れた同じグランドでの激励会。
非常に感慨深いものがありました。
そのなかで3年生の選手一人一人が意気込みと思いを発表してくれました。
・コロナ下でも最後の大会ができることに感謝
・練習の成果を発揮する
・全力で戦いよい結果を出す
など、それぞれが、前向きで明るい気持ちで話してくれました。
甲子園が中止になったことを悔いるような発言は一切ありませんでした。
今、与えられた環境でベストを尽くす、という姿勢は、私たち大人も学ばなければいけないと感じました。
佼成学園は順調に勝ち進み、今、ベスト8に勝ち残っています。
そして、本日、日大三高とベスト4をかけて対戦します。
選手の家族しか応援に行けないので、球場での応援は叶いませんが、心から勝利を願っています。
コロナ禍が再拡大しており、終息の目途が立ちません。
この状況のなかで、私たちはどのような行動を取るべきか。
それぞれの立場でよく考え、マスコミや報道だけに振り回されず、主体的に行動していくことが大切だと思います。
高校球児たちの、熱く、前向きな姿勢を励みにしながら、しっかりと前を向いて歩んでいきたいと考えています。
今月もよろしくお願いいたします。
早いもので今年も半分が終わり、今日から7月を迎えました。
私は、本業とは別に、小金井と新潟で書道教室を開催しています。
小金井は5年前から、新潟は4年前から月に1度の割合で参加者に指導しています。
ここ数カ月、コロナ禍で中断していましたが、6月は、小金井・新潟ともに、久しぶりに教室開催しました。
どちらも通常通りに参加者が集まり、集中して書道に取り組まれました。
全体をみながら、いつも以上に真剣に作品制作に励んでいる印象を受けました。
やはり、こうした対面での文化活動というのは、私たちにとって大切なものだと実感しました。
限られた時間のなかで、日常の生活や仕事を離れて、一つのことに集中して向き合う。
そして美や技術を磨く。
こうした文化活動は精神を豊かにし、また日常の生活や仕事にも気づきや深さや幅を与えてくれるものと考えています。
いつまた中断せざるを得ない状況になるか分からないので、こうした時間を大切にしたいと思っています。
古く中国では唐の時代に三大書家が現れ、日本では平安時代や江戸時代に書やその他の文化が花開きました。
共通するのは、みな平和な時代です。
平和だからこそ、不要不急の活動ができ、結果として経済や文化が発展するのだと思います。
コロナ禍がおさまり、平和な日常が戻ることを願っています。
東京ではここ最近、また感染者が増えています。
私たち一人ひとりが自覚を持ち、感染防止対策を徹底していくことが何よりも重要だと思いを強くしています。
私自身も自分自身の行動を律し、今できること、やるべきことをしっかりと選択しながら活動していきたいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
今日から6月に入りました。
新型コロナウイルス感染拡大をうけた緊急事態宣言は、5月25日に全面解除されました。
経済活動は少しずつ再開され、本日6月1日から通常の勤務体制や営業体制に戻る企業や店舗も多いと聞いています。
私たちは、自粛力と医療技術を要因の一つとして、感染症を取りあえず収束させ、日常を取り戻しつつあります。
しかし第二波の懸念も指摘されており油断はできません。
私たちは、新しい生活様式を強く意識しながら定着させ、かつ、疲弊した経済を立て直すために新しい考え方と行動で事業活動を復興させなければならないと考えています。
京セラ創業者の稲盛和夫氏は、新しいことを成し遂げるための要諦として以下のように述べられています。
「楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する」
構想段階では、「こうありたい」という夢と希望をもって、超楽観的に目標を設定する。
しかし、計画段階では一転して、悲観的に構想を見つめ直し、起こりうるすべての問題を想定して対応策を慎重に考え尽くす。
そして、実行段階においては、「必ずできる」という自信をもって、楽観的に明るく堂々と実行していく。
私は今のような事業環境には非常に重要な考え方だと思います。
なぜなら、このコロナ問題は、まだまだ終息には至らず、ワクチンや治療薬の開発・普及されるまで、再流行しては、自粛と緩和を繰り返し、不安定な状況が今後1年、2年と長期間続く可能性を念頭に置かなければならないと考えるからです。
そのため、
新しい生活様式を意識しながら、これからの事業活動や日常生活について、明るく楽観的な構想で目標設定をし、
しかし、その目標を達成させるための計画段階では、社会が再度自粛行動になり、事業活動が著しく制限されることを想定し、それでも現状維持か落ち込みを最小限に食い止められるような対応策を事前に考えておき、
経済が再開される実行段階である今からは、「必ずできる」と自信をもって、明るく前向きに行動していく。
このような考え方と行動の指針が重要になってくると考えています。
自粛期間中に、オンライン化が進んだり、新しい仕組みが整ったり、さまざまな創意工夫によるノウハウが生まれたりしています。
私自身は、コロナ前に戻ることを願うのではなく、新しいコロナ後の社会は、以前に比べ、より洗練された社会になるのだと信じ、当社と私自身をより成長させる機会としていきたいと思っています。
今月もよろしくお願いいたします。
今日から5月になりました。
緊急事態宣言の発令から3週間が過ぎましたが、新型コロナウイルスの感染拡大が終息せず、当初5月6日を期限とした緊急事態宣言発令期間がさらに延長される見通しのようです。
当社のお客様でも宿泊業や飲食業をはじめ、多くの業種業態で大きなマイナスの影響を受け、急激な経済的落ち込みは深刻です。
保険代理店の当社も、お客様訪問やお客様の来社を避けなくてはならない状況で、業務が著しく制限されています。
ですが、この危機を何とか乗り越え、生き残り、当社がより成長するための機会としたいと心を強く持つようにしています。
この苦難を乗り越えれば大きな自信にもつながるとも思っています。
私はこの難局に対し、以下のような心がけで毎日を過ごしたいと思っています。
1.今できること、やるべきことに全力を尽くす。
2.あきらめない。
3.希望を持つ。
4.新しい取り組みに挑戦する。
このようなことを思い、新たな取組みとして、4月からyoutubeを利用しての動画配信をはじめました。
生命保険に関連する役立つ情報を収録し配信しています。
新型コロナウイルスに関連する保険会社各社の特別措置などの解説もしています。
よろしければご覧ください。
また昨日、新型コロナウイルス関連の補正予算が成立し、中小企業・個人事業主向けの施策がはじまっています。
持続化給付金という制度で昨年と比べ売上が50%以上下がっている月があれば、法人で200万円・個人事業主で100万円が受取れる制度です。
本日5月1日から申請の受付がはじまっています。
概要を以下からご確認ください。
新型コロナウイルスが終息し、私たちの日常が戻ることを切に願っています。
当社は、私も従業員も、車や自転車で通勤し、公共交通機関の利用を避けて感染防止に努めています。
またお客様訪問や来社を控えてはいますが、メールや電話、オンライン面談などを通じ、お客様対応をはじめとする業務は通常通りに行っています。
ご相談があればいつでもお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルスの感染が国内で広がっています。各自治体によると、国内での感染者は、3月31日午後10時までに216人の感染が新たに確認され、これまでの累計感染者は2135人に上っています。
とくに東京での感染者増加が顕著で、昨日新たに78人の感染者が確認され、累計では519人となりました。
3月30日の小池都知事の会見では、「爆発的な感染増になるかの岐路」と表現されており、私もそのように認識しています。
また、短期的な終息は見込めないようでもあり、私たちは、このコロナ問題と1年以上など長期的に向き合っていく覚悟を持たなければならないとも思っています。
しかし、一時の中国や、現在の欧米と比べれば、感染増と死者を圧倒的に抑制できていることも事実です。
私たち一人ひとりが自覚を持ち、自身への感染防止、他者への感染防止に努める行動が、今後の感染抑制につながるのだと思います。
各国では感染防止を図るため、国や自治体からの強力な権力の行使により、外出を禁止したりしています。
しかし、日本では今のところ、要請による自粛のみです。
私は、今こそ、日本人の底力を世界に見せるチャンスだと考えます。
国からの強制力なしに、「自粛」によって、この危機を乗り越えられる国民性を世界にアピールできる機会だと思います。
マスコミでは、身勝手な若者の行動や、買い占めをする高齢者の映像を流していますが、そんなのはごく一部です。
多くの若者もほかの世代と同じような秩序を保って行動しています。
高齢者だって私の知っている方は、利他的で品格のある方ばかりです。
感染防止のために避ける行動は、もうみんな知っていると思います。
あとは、一人ひとりが自粛によって、徹底するだけです。
そして多くの制約があったとしても創意工夫により経済活動も極力停滞せずにしていくべきだと思います。
私は、日本人はそれができると思うし、自粛によって、このコロナ問題を終息させることができると信じています。
そして、一年延期された東京オリンピックが開催されるとき、「jishuku」がそのまま世界標準の言語となり、日本が再び世界から注目されるようになることを願っています。
政治や医療体制について批判を言っても何も変わりません。だから専門家に任せるしかありません。
変えられるのは、私たち一人ひとりの行動のみです。
新型コロナウイルスの感染により影響を受けられたお客様に対して、保険会社各社で特別な対応や取扱いを開始しています。
各社によって違いはありますが主な取扱いは以下の通りです。
1.保険金・給付金の簡易請求
2.契約者貸付の利息減免
3.保険料払込猶予期間の延長
4.保険契約の更新手続きの遡及対応
5.保険契約の失効に関する特別措置
年度末を迎える3月に入りました。
新型コロナウイルスの感染拡大が続き、私たちの日常生活や経済活動に大きな影響を与えています。
このウイルスの真の危険度がどうかは別として、未知であることが一つの原因で、不安がさらなる不安を呼び、日本中、世界中がパニックになっています。
もうこうなると、しばらくはこの流れに沿って生活していくしかありません。
ウイルスも自然の一部であり、私たちは自然に勝てるわけがなく、生かされて生きているに過ぎないからです。
しかし、私たちは人類そして日本人は、これまでも戦争や経済危機、大地震や大水害など、幾多の危機を乗り越え、適応してきた実績があります。
今回の新コロナも必ず乗り越え、さらに私たちは強くなると信じています。
倫理研究所発行の栞の一節に以下のような文言があります。
私たちのあるべき暮らしぶりは「すなおな心」である。
すなおな心とは、ふんわりとやわらかで、何のこだわりも不足もなく、澄みきった張りきった心であり、これを持ちつづけることである。
これを今回の騒動にあてはめると、
「新型コロナウイルスが発生した。不況になる。そうなんだ。」と素直に現実を受け入れることだと思います。
報道や玉石混合の情報に触れることで「どうしよう!」と冷静さを失って慌てることではなく。
素直に現実を受け入れることで、今、やるべきことが見えてくるのだと思います。
日常生活や経済活動に多くの制約条件がつく現状のなかで、今できること、やるべきことは、個々の会社や個人によって様々です。
でも私たちひとり一人が、そうした素直な心で、今できること、やるべきことを模索し行動することによって、この騒動からの回復を少しでも早めるきっかけにつながるものと信じています。
コロナ騒動前と騒動後のビジネスのあり方は大きく変化すると感じています。
コロナ後の世界にどう順応するか。
自然界の掟は適者生存です。
強いものが残るのではなく、変化に順応したものが残ります。
まず肉体的にも経済的にも生き残る。
そしてこの騒動が収束したあと、私たちはさらに強くなり発展できる。
明日はきっとよくなる。
そう信じて、明るく前向きに過ごしたいと思います。
新型コロナウイルスによる感染拡大が一日でも早く収束することを願っています。
<追記>
新型コロナウイルスが原因での入院は、民間の医療保険の給付金対象となります。
保険会社によっては簡易請求が可能となるような措置を取っています。
何かご不安に思われる方は、保険会社や代理店へお問い合わせください。
当社のお客様については直接私が対応いたします。
いつでもお問い合わせください。
2月に入りました。今年は閏年なので2月29日までありますね。
中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎について、中国全土での感染拡大が止まりません。
日本でも現在のところは流行が認められるほどの状況ではありませんが、2月1日時点での国内感染者は20人となり、今後も感染者増加が予想されます。
これにより、生産や供給網に混乱をきたし、観光業や飲食業など経済的に大きなマイナスの影響を与えています。
私にも幼い子がいますので医療上の警戒はもちろんしていますが、それよりも、今後の日本経済や世界経済の減速などの影響が心配です。
今回の新型コロナウイルスは、まだ不明な点が多くあるものの、2003年のSARS、2012年のMERSに比べると、感染後、重症化するリスクはそれほど高くないとの見方もあり、通常の風邪やインフルエンザと同じような対策をすればよいとの認識もあります。
中国での感染者による致死率をみても(患者数:14,380人 死者数:304人 致死率:2.1%)、高齢者や持病がある方を除いては、それほど恐れる必要はないと私自身も思います。
私たちは、過度に感情的で非合理的なマスコミ報道に煽られることなく、日常の生活を守り、仕事など経済活動をしっかりとしていくことが大切だと思っています。
しかし予防や対策は必要です。
有効な対策は当たり前ですが、以下の通りです。
1.こまめな手洗い
2.うがい
3.手で眼・口・鼻を触れない
4.マスクをする
5.部屋を加湿する
また、もし感染したとしても、免疫力が高ければ、すぐに治ると考えています。
免疫力を高めるには、これも当たり前ですが、以下のことを心がけるとよいそうです。
1.適度な運動
2.規則正しい食事
3.睡眠をしっかりとること
4.体を冷やさないこと
特に、ジョギングやウォーキングなどの適度な運動がよいそうです。
また厚生労働省では事業者向けのQ&Aも掲載しています。
今回の感染症と労働基準法などに照らし合わせた労務上のQ&Aです。
事業者の方は参考になると思いますので合わせてご確認ください。
すでに欧米では中国人への差別的な態度が出てきているとのこと。
それがアジア系ということに発展し日本人へも差別の目が向けられるかもしれません。
また国内でもチャーター便で帰国した日本人を隔離しなかったことでメディアから厳しく非難されていた担当官僚が自殺したとの報道もありました。
本当に怖いのは、ウイルスでも経済減速でもなく、私たち人間の「心」なのかもしれません。
これを肝に銘じて、かけがえのない日常をしっかりと生きていきたいと思っています。
東京オリンピックを前に、この新型ウイルス問題ができるだけ早く収束することを願っています。
あけましておめでとうございます。
本日が仕事はじめの方が多いみたいですね。
今年もよろしくお願いいたします。
年のはじめに何の話題がいいか迷いましたが、昨年の春に現役大リーグを引退したイチローのメッセージを取り上げさせていただきます。
小学生のクラブチームで組織された軟式野球大会、イチロー杯の表彰式でイチローが小学生の選手たちへ送ったメッセージです。
イチローが現役引退したことでイチロー杯は今回で終了するとのことなので、最後のメッセージとなります。
このなかで2つのことを話していますが、そのうちの1つのメッセージが私たちにとっても多くの気づきを与えてくれていると感じています。
要約すると以下の通りです。
ーーー
学校の先生など教える立場の人たちにとって、厳しく指導することが難しい時代になっている。
なので自分自身を自分で鍛える必要性が高まっている。
自分で自分のことを教育しなければならないという時代に入ってきた。
ーーー
これは私がお客様と接するなかでも感じることです。
教員・経営者・上司など、子供、大人問わず、教えたり指導したりする立場の方たちが、ともすると過剰とも思われる様々なハラスメントを問われる場面が多くなり、相手のことを思ったとしても、厳しく指導することをあえて避けてしまうという傾向にあるように感じます。
誰からも強く怒られない生徒や部下たちにとって、この傾向は幸・不幸、どちらなのでしょうか。
この傾向は、ときに無関心な世界が広がり、逆に孤立したり、成長しようとする意欲が低下する原因になるかもしれません。
イチローはこのことを心配し、だからこそ、「自分が成長していくためには自分で自分を鍛え、教育していかなければならない」と言っています。
しかしこの傾向をただ単にネガティブに捉えるのではなく、そういう時代に入ってきたというむしろ時代の流れをポジティブに捉えて話しをしています。
このイチローのメッセージは、私たちビジネスマンにとっても非常に重要な気づきを与えていると思います。
上司やお客様、取引先に厳しく言われなくても、自らを律し、「自分で自分を鍛えて教育していく」。
これからの時代、こうした心がけがより重要になってくると私自身、改めて感じています。
言われなくても自ら行動する。
相手にとって何が役にたつか自分で考える。
日々、自分を磨くための勉強をする。
こんなことを心がけて一年間過ごしていきたいと思っています。
今年一年がみなさまにとりまして良い一年になりますように祈念申し上げ、新年のレポートとさせていただきます。
12月に入りました。
早いもので今年も残り1ヶ月となりました。
12月はあっとう間に過ぎてしまうので、しっかりと地に足をつけて納得した形で今年1年を締めくくりたいと思います。
先日、11月20日、保険会社主催の勉強会に参加しました。
テーマは、「尿1滴でがんを早期発見」。
これは、線虫を使ったがん検査で、がん患者の尿に含まれる微量な匂い物質を検知してがんの罹患を判定する技術です。
講師は、この線虫検査の開発者であり、運営会社の経営者である、広津崇亮氏でした。
昨年11月のメルマガでも同じテーマを取り上げましたが、このたび大きく進展がありましたので再度情報提供させていただきます。
この検査ですが、来年2020年1月から実用化が始まります。もう来月ということです。
検査費用もすでに決まっていて、1回9,800円です。
実用化当初は、25万人程度のキャパシティのため、病院や一部の企業に限られますが、数年後には、がん検査ニーズのある数千万人規模の検査が可能となり、定期健康診断や人間ドックなどのオプション検査などで利用できるようなる見込みです。
そうなれば私自身も毎年1度は検査を受診したいと思っています。
この検査が今までのがん検査と大きく異なる特徴は以下の通りです。
1.簡便(尿1滴で可能)
2.安価(9,800円)
3.高精度(85%の確率でがんを判定)
4.早期発見が可能(ステージ0・1の早期がん)
5.苦痛なし(尿1滴)
6.全身網羅的(1度の検査で全身)
この検査が普及すれば、日本のがん治療は一気に進化できるのではないでしょうか。
がん経験者の再発のための検査にも応用できます。
ステージ0の超早期発見でがんの早期治療が実現でき、がんは治る病気となる日も近いと感じています。
がん線虫検査の詳細は以下の専用ホームページで確認できます。
⇒ がん線虫検査(N-NOSE)
また11月25日の日経新聞には以下の記事もありました。
⇒ 血液1滴でがん検査 東芝、21年にもキット実用化 精度99%
こちらは血液での検査ですが、これも注目すべき技術ですね。
各研究機関にはこれからも高いレベルで切磋琢磨していただき、これからますますがん検査や医療技術が進展していくことを期待しています。
また有益と思われる進捗がありましたら情報提供させていただきます。
今日から11月に入りました。
東京はここ数日、晴れて秋らしい天気が続いています。
しかし10月は台風や豪雨など災害が続きました。
10月12日に伊豆半島に上陸した台風19号は、全国、特に関東から東北にかけて甚大な被害を及ぼしました。
これまで死者92人、行方不明者9名となっており、その他でも河川の氾濫などで被災された方は数多くいらっしゃいます。
被害に遭われた方におかれましては心からお見舞いを申し上げます。
被災地へのボランティアの報道をみているうちに、2016年に起こった熊本地震直後にツイッター上で話題になった「被災地いらなかった物リスト」が目につきました。
これからも日本国内ではどこでも災害が起こる可能性があり、また私たちの日常やビジネスのヒントにもなると感じましたので、まとめてみました。
<被災地いらなかった物リスト>
1.千羽鶴・寄せ書き
2.食品
お米など調理が必要なもの
生鮮食品など消費期限が短いもの
賞味期限が分からない・切れているもの
辛いラーメン
成分表がなくアレルギー対応ができないもの
3.古着・毛布・布団
穴があいている
使用済みの下着
汚れた毛布
4.古くて使えない家電
地デジ非対応のブラウン管テレビ
周波数が違う家電
5.使用済みの文房具・おもちゃ
6.医療品・サプリメント
7.本・雑誌
自己啓発本
旅行ガイド
宗教関連の書籍
これを見ると明らかに常識外れなものもあります。
好意で送ったとしても有難迷惑ですね。
寄せ書きなんかは、避難場所に送られてきても嬉しくないが、仮設住居など落ち着いたときにもらうと嬉しいし励みになるという意見もあるようです。
要はタイミングの問題だったりします。
こう考えると、このいらなかったリストは、仕事、家庭、友人知人関係など、いろいろな人間関係にも応用できると思います。
こちらがよかれと思ってしたことが逆に迷惑になる場合ってあります。
ときには、あまりに的外れだと、やってるという事実で恩をきせたり自己満足をしているだけ、と思われてしまうかもしれません。
仕事でもお客様に喜ばれる行為というのは、
「今、その人が欲しているモノやサービスを適切に提供すること」
に尽きると思います。
要らないモノはタダでも要らなかったりします。
それには、相手が何を求めているかのニーズを知ることが大切です。
ニーズを知るには、
・相手の立場を自分のことにように考え、理解しようとする思いやりの気持ち
・相手の話しをよく聞き、ニーズを捉えること
が重要で、そのうえで自分や会社ができることを選別することなのだと思います。
被災地でも自治体によっては今必要な支援物資をホームページで掲示しているようです。
その時々で必要なモノは変化します。
過去に必要だったり、未来に必要だったりしても意味がありません。
やはり、「今」をタイムリーに捉えることが喜ばれる重要な要素なのだと思います。
自分ができているかと自問自答したときに、私自身もまだまだだと感じます。
被災者への接し方やボランティアのあり方、また仕事への取り組み方、家族への接し方など、いろいろな場面での教訓にしたいと思っています。
10月1日になりました。
今朝カレンダーをめくったら残りがあと3枚でした。
今年も早いものであと3ヶ月ですね。
今日から消費税率が8%から10%に上がりました。
10%への増税は当初は15年10月の予定でしたが、政府は2度にわたって延期していました。
消費税率の引き上げは、2014年4月に5%から8%に上げて以来となります。
増税前には駆け込み需要が発生し、物流部門が大変忙しいと聞いていました。
こうした駆け込み需要の反動を抑え、消費や景気を下支えするための政策も打ち出されています。
私たちの生活にも影響があることが多いのでちょっと記しておきます。
<消費増税と今後の家計関連政策>
■2019年10月1日から
・消費税率を10%に引き上げ 軽減税率制度で食品と新聞は8%に据え置き
・中小店舗の買い物で原則5%をポイント還元 キャッシュレス決済することが条件
・低所得世帯と子育て世帯(0~3歳半)に25%分のプレミアム付商品券の販売
・低年金者に月5,000円を基準に支給
・3~5歳児の保育料を原則無償化
・自動車購入時にかかる取得税が廃止
・毎年かかる自動車税が引き下げ
・住宅ローン減税の税額控除期間を10年から13年に延長
・すまい給付金の対象者を年収775万円以下に拡大し、給付額を最大50万円に引き上げ
キャッシュレスで買い物すると5%還元されるというのは、今後のキャッシュレス化の流れを加速させるような動きになりそうですね。
また消費税導入後の為替変動について興味深いデータがあるのでご紹介しておきます。
<消費税増税後の為替レートの推移>
| 消費税率 | 導入直前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 3% |
1ドル=133円 1989年3月末 |
1ドル=159円 1990年4月末 |
| 5% |
1ドル=124円 1997年3月末 |
1ドル=145円 1998年7月末 |
| 8% |
1ドル=103円 2014年3月末 |
1ドル=124円 2015年5月末 |
| 10% |
1ドル=108円 2019年9月末 |
? |
いかがでしょうか。
増税から1年半後程度の為替推移をみると、15%~20%程度の円安になっていることが分かります。
ロジックもあるようですが難しいことは分かりません。
でも過去3度の増税後の共通点ではあります。
現在は1ドル=108円程度です。
これから1年半後、為替はどうなっているか。
その間、東京オリンピックもありますね。
現在は日本だけでなく先進諸国全体で超低金利となっています。
なので金利よりも為替が経済に与える影響は大きくなっているという過去3度とは違った要素もあります。
結局のところ、為替は読めないのだとは思いますが、ご参考にしてください。
下半期、私たちは、消費増税を言い訳にすることなく、しっかりと目の前の仕事に打ち込み、一人一人が頑張って成果をあげていくことこそが、景気を下支えする大きな要因になると思っています。
9月に入りました。
今朝の東京は晴れていて、秋の訪れを思わせるような涼しい風が吹き、ずいぶんと過ごしやすくなりました。
8月8日、国立がん研究センターは、がんの3年生存率を公表しました。
それによると、全がんについて、2012年にがんと診断された患者の3年後の生存率は72.1%で、昨年に比べ0.8%改善、2009年~2010年に診断を受けた患者の5年生存率は66.1%と0.3%改善されており、新しい抗がん剤の開発等、医療技術がさらに進展していると考えられます。
種類別のがん生存率は以下の通りです。
| がんの種類 | 3年生存率(%) | 5年生存率(%) |
|---|---|---|
| 胃 | 75.6 | 71.6 |
| 大腸 | 78.7 | 72.9 |
| 肝臓 | 54.6 | 40 |
| 肺、気管 | 50.8 | 40.6 |
| 女性の乳房 | 95.2 | 92.5 |
| 食道 | 53.6 | 44.4 |
| 膵臓 | 16.9 | 9.6 |
| 前立腺 | 99.2 | 98.6 |
| 子宮頚部 | 79.6 | 75.3 |
| 子宮内膜 | 85.9 | 82.1 |
| 膀胱 | 73.4 | 69.5 |
| 喉頭 | 84.4 | - |
| 胆のう | 33.4 | - |
| 腎 | 85.6 | - |
| 腎孟尿管 | 55.6 | - |
出典:国立がん研究センター(日本経済新聞の記事を抜粋)
喉頭・胆のう・腎・腎孟尿管については今回から公表されたため5年生存率については非公開。
これを見ると、部位によって大きな差異があるものの、五大がんに含まれる、胃・大腸・乳房については、高い生存率となっており、がんは治る病気になりつつあることが実感できます。
私は、医療技術の進歩とともにがんの生存率が高くなるほど、がん保険の意義や必要性は高まると考えています。
長期化する治療費の自己負担額を補うためです。
お金のことを気にせず、治療に専念できる。
この安心感は、精神的にも治療によい影響を与えてくれると思います。
また、がんの進行度によって生存率が大きく違うのも事実です。
やはり、定期健康診断や人間ドックを受診することで早期発見・早期治療が重要です。
医療の進歩は日進月歩であり、その医療の進歩に合わせたあるべき保障も変化していきます。
これからも保険の仕事を通じて、私たちの役割は何かを考え、タイムリーな情報収集と情報提供を心がけていきたいと思っています。
8月に入りました。
東京も梅雨明けし、連日、猛暑が続いています。
水分補給をし、熱中症にお気をつけください。
7月17日~18日、パシフィコ横浜で開催された盛和塾の世界大会に参加しました。
盛和塾は、京セラの創業者である稲盛和夫氏が主催する経営塾で、塾生は世界に15,000人の規模です。
世界大会には約4,800人が集まりました。
すでに報道されていますが、この盛和塾は、稲盛塾長が高齢となったことから、今年一杯で解散することが決まっており、塾生が一同に集まる世界大会は今回が最後でした。
稲盛塾長は残念ながらご欠席されましたが、「フィロソフィをいかに語るか」と題した塾長講話が代読で発信されました。
最後の塾長講話は、いつもより長く、稲盛塾長の思いがびっしりと詰まっていると感じられる、大変すばらしい内容でした。
盛和塾の解散は残念ですが、入塾後、10年間学ばせていただいたことを、今後の仕事や日々の生活に生かしていきたいと思っています。
京セラとKDDIを創業し、発展させ、JALを再生に導いた、日本史上を代表する経営者だと思います。
末席から眺める程度でしたが、稲盛塾長の謦咳に接することができた経験は、私の今後の人生に大きなプラスの影響を与えるものと確信しています。
盛和塾で学ばせていただいたことはたくさんありますが、そのなかで、私が最も吸収したいと思う箴言は以下の2つです。
1.人間として何が正しいかを判断基準とする。
2.人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力
仕事をしていると日々、判断に追われます。
その判断は、自分の利益や利己的なものでなく、利他的で人として何が正しいかを基準にして判断する。
人生や仕事の結果は、考え方×熱意×能力という方程式で表される。
考え方にはプラスもマイナスもあり、熱意や能力がいくら高くても、考え方がマイナスであったら、すべての結果がマイナスになってしまう。
だからこそ、明るく前向き、利他の心といったプラスの考え方が重要である。
これからの人生や仕事において、この2つだけはしっかりと胸に刻み、日々心がけていきたいと思います。
今まで、数十年に渡り、ボランティアでご自身の経営哲学を余すことなく伝達いただいた稲盛塾長に心から感謝しています。
そして稲盛塾長のこれからのご健勝を心から祈念しております。
今日から7月に入りました。
東京は毎日、曇りや雨など梅雨らしい天気が続いています。
先日、6月27日、かんぽ生命は、お客様が新しい保険契約に乗り換えできずに不利益を受けた事例が2014年4月から2019年3月までに約19,000件にのぼると発表しました。
また本来は契約乗り換えの必要がなく、特約の切り替えで済んだ可能性がある契約も2017年10月以降で約5,000件あったとのこと。
この件について、契約数も多く社会的な影響も大きいかんぽ生命のことなどで解説と注意喚起をしておきたいと思います。
今までの契約を解約して新しい保険を契約する。
これを乗り換えと言います。
その際、既往症など、現在の健康状態に問題があると、新たな保険を契約できない場合があります。
しかし前から契約していた保険はすでに解約しており、お客様は無保険になってしまいます。
今までの保険を継続していれば保障があったのに、新しい保険に乗り換えをしたことによって保障が無くなってしまったわけです。
これはお客様にとって大変な不利益ですが、これが19,000件もあったというのです。
なぜこのようなことが起こってしまうのか?
これにはかんぽ生命の仕組みに原因があります。
かんぽ生命は、一人のお客様が契約できる保険金額の上限が2,000万円と定められています。
すでに2,000万円契約しているお客様が乗り換え契約をしようとすると、既存の契約を解約しないと、新たな保険に申込みができないそうです。
一時的に上限の2,000万円を超えてしまうからです。
このように解約を先行させないと乗り換えができないところに大きな問題があります。
このお客様にとって不都合な仕組みは、上限2,000万円とは関係のないことだと思います。
通常、他の保険会社では、乗り換えのときは、解約同時新契約や契約転換制度といって、解約手続きと同時に新契約の申込みをして、新契約の契約が可能であれば自動的に既存契約は解約、健康状態に問題があって新契約が契約できなければ、新契約の申込みと既存契約の解約が取り消され、既存契約が継続されるような仕組みになっています。
これであれば乗り換え時の保障の空白と新契約が乗り換えができなかった場合の無保険状態を回避できます。
かんぽ生命は、この仕組みがなかったため、今回のような不祥事が起きてしまったのです。
保険業界における信用不安を払しょくさせるためにも、是非、早急に、旧契約を解約せずに契約を見直せる制度を導入してもらいたいと願います。
日本郵政によれば、制度導入にはシステム対応が必要で数年かかるとのこと。
数年なんて遅すぎます。
契約者保護のためにも、1ヶ月とか2ヶ月で制度の見直しを実践したもらいたいと思います。
いずれにしても、みなさまにおかれては、生命保険の乗り換えは慎重に行ってください。
乗り換えることでメリットが出ることもありますが、年齢が上がったことや予定利率が下がったことで保険料が上がったり、貯蓄性が低下したりする場合もあります。
生命保険は大切な財産です。
営業マン任せにせず、自分自身で考え、必要におうじてご家族にも相談しながら判断してください。
かんぽ生命は、不利益販売の可能性がある契約について、新旧契約の乗り換え時に不利益事項の説明が十分だったかを含めて販売が適切だったかを調査し、問題があれば、お客様の意向も踏まえ、旧契約に戻すといった対応を検討しているとのこと。
今回の件で不利益を被ったお客様が、かんぽ生命の今後の適切な対応によって、安心を取り戻すことができるようになることを願っています。
東京は紫陽花が咲き始め、もうすぐ梅雨かなと思わせる湿気の多い日が続いています。
5月22日に金融庁の審議会から「高齢社会における資産形成・管理」の報告書(案)が発信されました。
これは、人口減少・高齢化長寿化の進展という現状を踏まえ、これからのあるべき金融サービスとは何か?という議論を報告書としてまとめたものです。
直後に新聞報道などで概要が掲載されていたのでご覧になった方も多いと思います。
文中、「年金の給付水準が今までと同等のものであると期待することは難しい。今後は、公的年金だけでは満足な生活水準に届かない可能性がある。」とはっきりと明記されています。
私たちはこれをどのように受け止めればよいのでしょうか。
国の関連機関の報告書に明記されることで、私たちが日頃抱いていた不安感が何となく明確になったという印象を受けます。
そして、60代以降、公的年金+労働+資産の取り崩し、という3つの要素を組み合わせて生活を維持していくことが望ましいと読み取ることができます。
加えて、資産形成については、若いうちから、長期・積立・分散投資など、少額からでも資産形成の行動を起こすように喚起しています。
また資産形成の具体的な手段としては、iDeCoやNISAが挙げられています。
年金だけでは生活できないので、自助努力でしっかりと蓄えを作って欲しいということです。
私も数年前から個人のお客様へ老後の資産形成の重要性を訴えていますが、今後、ますますその重要度と私たちの役割は高まると思っています。
例えば、35歳の人が65歳までの30年間、月1万円を銀行で積立てたとします。
そうすると65歳のときの積立額は、利息はほぼ0なので、360万円です。
でも月1万円を想定利回り5%の金融商品で積立てたとすると、65歳のときの積立額は、約830万円になります。
この差額は実に470万円、2倍以上です。
同じ1万円ずつを積み立てているのに、こんなに差が開いてしまいます。
これは、時間を味方につけ、長期で分散投資による積立てを行えば、十分に期待してよい数字なのです。
生命保険会社が販売している変額個人年金なども、長期・積立・分散投資を考えるうえでは非常に有力な手段だと考えています。
お客様の将来の生活を守るため、正しい情報を広くお伝えしていくことは、私たちの義務だと思っています。
選択するのはお客様自身ですが、将来の資産形成については、これからますます積極的に情報提供していきたいと考えています。
本日は令和元年5月1日です。
元号が平成から令和に変わり、新時代の幕が開けました。
令和になったからといって私たちの生活に特段の変化はありませんが、これからの時代はどうなるのだろう、また私たちはどうしていくべきなのだろうと抽象的ながらも節目ですのでいろいろな思いを巡らせています。
先日、2024年度に紙幣が一新されることが発表されました。
1万円札の図柄は、渋沢栄一となります。
渋沢栄一は、第一国立銀行(現みずほ銀行)など数多くの企業を設立し、日本の資本主義の父とされる人物です。
同氏の著書に、「論語と算盤」があります。
そのなかには以下のような記述があります。
「道徳と経営は合一すべきである。」
また大正12年の講演では以下のように語っています。
「仁義道徳と生産殖利とは、元来、ともに進むべきものであります。」
つまり渋沢栄一の思いと私たちに伝えたかったことは、
「人格を磨くことと、利益を追求することの両立が大切だ」ということです。
これは時代に関係なく普遍的な原理原則ですが、特にこれからの時代、私たちが心がけなくてはならないことだと思います。
人としても会社経営にも通じることです。
いくら人格がすばらしい社長や社員がいても、売上と利益をあげられなければ会社は存続できません。
また高い技術や販売力で売上をあげても、人格に問題があればどこかで不祥事などが発生し、やはり会社は存続できないのだと思います。
やはり、この2つの要素を両立させるからこそ、会社は永続的に維持発展できるのだと思います。
京セラ創業者の稲盛和夫氏は、これを、「フィロソフィ」と「アメーバ会計システム」として会社経営に導入し、京セラとKDDIを発展させ、JALを再建されました。
旧知の社長は、「技術と知性」と言い、最近お会いした社長は、「経営とカバナンス」と言いました。
どちらも同じような考え方で共感できます。
倫理道徳と企業業績の両立が会社を長きにわたり発展させられることは疑いようがありません。
最近の大企業や経営者の不祥事をみても、過去に両立できていても、どこかで道徳心が薄れてしまったりすると、すぐに転落してしまったりします。
だからこそ、今できていても、驕ることなく、日々を反省しながら、倫理道徳と経営をいつも両立させるべく、自分自身を磨き続けることが大切だと感じます。
令和の時代の幕開けに、「倫理道徳と会社経営の両立」を改めて目指し、また今日から精進していきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
本日は4月1日。
当社にとっても13期目の新年度がはじまりました。
東京は桜が満開。
本日の11時30分には新元号も発表される予定です。
まさに新たなスタートで私自身も心機一転、頑張りたいと気持ちを新たにしているところです。
3月21日、マリナーズのイチローが、東京ドームでのアスレチックとの開幕第2戦後に、引退を表明しました。
私としてはとうとうこの日がやってきてしまったという印象です。
昨年のシーズン序盤5月に、選手登録を外れ、会長付特別補佐に就任しながら、その後も練習を続け現役復帰を目指しました。
この前代未聞の新たな挑戦をし、メジャー復帰を目指し、今年のキャンプを迎え、オープン戦に出場しました。
しかし、結果を出すことができず、引退を決意したとのこと。
私は、叶うことはなかったものの、この挑戦する姿に敬意を表したいと思います。
この挑戦は次のキャリアに必ず生かされると思っています。
イチローがメジャーとしてマリナーズに入団したのは2001年です。
私はこの年、サラリーマンを辞め、フルコミッションの生命保険業界へ転職しました。
28歳のときでした。
結果がすべての厳しい世界で仕事をするなかで、イチローの活躍が励みでした。
毎日、スポーツ新聞をみてはイチローの全打席をチェックし、3安打、4安打、ときに5安打した結果をみては、自分も頑張ると鼓舞しました。
自分がスランプに陥ったとき、イチローの姿をみて、諦めない強い心を取り戻したこともあります。
メジャーの大男を前に、結果を残し続けるイチローの姿にどれだけ勇気と希望をもらったか分かりません。
同世代のスーパースター、イチローの現役引退は残念ですが、終わりはこれからのスタートでもあります。
今後は指導者としてのイチローに期待したいと思います。
いつかメジャーでのイチロー監督をみてみたいものです。
イチローからは、毎日を一生懸命に生きること、努力を積み重ねること、自らを律すること、今できることに全力で取り組むこと、一本のヒット(成果)を大切にすること、を学びました。
この学びを自分自身の人生や経営に生かしていきたいと思います。
人生は今日からが本番。昨日まではリハーサル。
日々新たに。
新年度のはじめに、今日からも一生懸命に過ごすと決意しています。
日数の短い2月があっという間に終わり、本日から3月に入りました。
2月は生命保険業界にとって激動のときでした。
2月13日、突然、国税庁から各生命保険会社に対して、「ピーク時の解約返戻率が50%以上ある法人向け定期保険について、税務取扱いの見直しを検討している」旨の連絡がありました。
このお上の鶴の一声で、各保険会社は即時の対応を余儀なくされます。
そしてその対応は想定以上の早さとなりました。
2月15日にはほとんどの保険会社で長くても2月28日をもって対象となる保険商品が販売停止とする方針が打ち出されました。
国税庁の連絡からわずか2週間です。
当社取扱いの保険会社でも他とほぼ横並びでの対応となりました。
これを受け、当社ではすでにご提案済みの法人へ状況を説明し、ご契約を希望される法人にはメリット・デメリットを丁寧に説明しながら、至急の対応で手続きを完了させ、そして昨日、予定通り、今まで売れ筋だった法人向け保険商品が販売停止となりました。
例年であれば今日からはじまる3月は年度末であり、保険会社にとっても多くの売上を見込む重要な月ですが、今年は、3月に販売できる法人向け商品が著しく制限されており、厳しい環境で3月を迎えることになりました。
この事情は、私たち販売代理店も同様です。
生命保険業界は3月以降、大きな転機を迎えることになりました。
しかし、決まってしまったことは嘆いても意味がありません。
この難局をどう乗り越えるかが重要であり、私は実力が試されるときだと考えています。
京セラ創業者である稲盛和夫氏が作った京セラフィロソフィには次のような項目があります。
・「常に明るく」
どんな逆境にあっても、自分の未来に希望をいだいて明るく積極的に行動していくことが、仕事や人生をよりよくするための第一条件なのです。
・「お客様第一主義を貫く」
お客様のニーズに対して、徹底的にチャレンジしていく姿勢が重要。お客様に喜んでいただくことが商いの基本である。
私は今こそ、この2点を徹底したいと思っています。
人間として何が正しいかを判断基準としながら、明るく前向きに行動し、お客様第一主義を徹底させる。
そして、できない言い訳はせず、変化にしっかりと対応していく。
こうした心がけを肝に銘じ、この難局を乗り越えたいと思っています。
あと1ヶ月もすれば桜が咲いていることでしょう。
年度末3月をしっかりと締めくくり、爽やかな桜咲く4月を迎えたいものです。
年が明けたと思ったら、もう1ヶ月が経ち、今日から2月に入りました。
また悲しい事件がありました。
千葉県野田市立小4年の栗原心愛(みあ)さんが、父親の暴力を受けた後に亡くなりました。
夜中に立たせたり、冷たいシャワーをかけたり、首をしめたり、ぎゃーと叫ぶ声が近隣に聞こえたりなど、日常的な虐待の様子が報道されています。
私にも4歳と2歳と0歳の幼い子供がいます。
だからこそ、心愛さんが受けた虐待の様子と死は、想像に絶えず、辛くてまともにニュースを見ることができません。
心からご冥福を祈ります。
今回、心愛さんの小学校で「父親から暴力を受けている。先生、どうにかできませんか。」と訴えたアンケートを市の教育委員会が父親に渡してしまったなど、児童相談所や学校、自治体の対応の不備が明らかになっています。
そうした誤った判断が重なった結果、救出の機会が失われたということは残念であり、公的機関の今後の対応力強化は必須だと思います。
しかしこのような悲劇がある一方で、児童保護機関のおかげで助かった命や健全な生活を送れているケースも、悲劇の何倍もあると私は信じたい。
悲劇の事件だけがクローズアップされるのではなく、児童相談所・学校・自治体が連携したファインプレーも数多くあるはずで、そうした事例も積極的に報道して欲しいと思います。
そうしないと、このままでは児童相談所に相談しても無駄なんじゃないかという風潮が広がり、より負の連鎖が起きやすくなってしまうと思うのです。
どんなことだって相談すれば、社会が守ってくれることは多くあると思います。
児童相談所・学校・自治体・親兄弟・親戚・弁護士などの専門家など、困ったときに相談しやすい、声をかけやすい、人のつながりを大切にするような社会が広がり、このような悲劇が二度と起こらないようにと切に祈っています。
あけましておめでとうございます。
今年は今日から仕事はじめの方が多いようですね。
今年もよろしくお願いいたします。
1月2日に皇居へ一般参賀に行ってきました。
報道にもありましたが、平成最後の一般参賀ということもあり、過去最高の15万4,800人が訪れ、予想以上の混み方でした。
私が東京駅に着いたのが11:30。
陛下がお出ましになる宮殿前にたどり着いたのが15時前。
何とか6回目の参賀に間に合いました。
しかし人がごった返し、陛下のお顔を直接拝見することはできませんでした。
それでもあの空気を味わえたことは満足です。
印象的だったのは、寒い中、あれだけ長時間待たされ、いつ列が動き出すかも分からないなか、誰も文句を言う人はいませんでした。
みな整然と並び、いざ動き出すと、警官の指示に従い、秩序を保ち、整然と歩き出しました。
そしてどの場面でも押しあったり割り込んだりする光景は見られませんでした。
私たち日本人もまだまだ捨てたものではないと感じました。
今年の干支は己亥(つちのとい)。
十干十二支が同じ干支は10と12の最小公倍数の60年に一度やってきます。
60年前の1959年は、現在の天皇陛下と美智子妃殿下がご結婚されたおめでたい年でした。
今年は4月30日に天皇陛下が退位され、5月1日から皇太子様が天皇となり、新しい元号がはじまる節目の年となります。
節目の年を迎え、私自身も例年以上に自分を磨き、成長していきたいと思っています。
年のはじめに自戒を込めて、大前研一氏の言葉をご紹介します。
===
人間が変わる方法は3つしかない。
1番目は時間配分を変えること。
2番目は住む場所を変えること。
3番目はつきあう人を変えること。
最も無意味なことは「決意を新たにする」ことだ。
===
私自身、具体的な行動によって、自分を変えていきたいと思います。
12月に入りました。今年も残り1ヶ月ですね。
私は業務として書道も行っており、小金井と新潟で書道教室を開催しています。
私が所属しているのは日展審査員であった故田岡正堂先生が創業された?友書道会です。
?友書道会では毎年1月4日に書道展を開催していて、11月23日はその展覧会の審査で、私も当番審査員の一人として参加しました。
学生:1,776点、一般:595点が出品され、私の教室、小金井と新潟からも学生一般合わせて、22名が出品しました。
書道作品の審査を通じて、ビジネスとも共通することがあると感じましたので、ご紹介したいと思います。
審査ではよい作品が選別され、最終的に1点最高賞が決まります。
最終審査に残った10点を前に貼り、13人の審査員が挙手して票を数えていきます。
残った10点は、多くの作品から勝ち上がってきたので、どれも甲乙付けがたいよい作品です。
結局、最高賞に選ばれた作品は、13人全員が挙手し、満票でした。
文句なしの最高賞です。
他9点も順次序列が付けられ、上位賞が決定しました。
上位10点はみなよい作品で実力は拮抗しています。
そのなかで優劣を決める要素は何か。
もちろん作品自体のよさは外せません。
が、意外に、墨色、紙質、名前のうまさなど、文字そのものというよりは、作品全体を補完する付随的な部分だったり、細部への気遣いが決め手になったりもします。
ビジネスも同じではないでしょうか。
現在は商品・サービスのコモディティ化が進み、差別化が難しくなっています。
つまりどこで買っても同じようなモノやサービスが手に入る時代です。
価格や品質に差がない場合、お客様は何で選ぶか。
売り手の、笑顔や話し方、服装や髪形などの身だしなみなどが決め手になったりするのではないでしょうか。
まさに商品や価格以外の、付随的な部分や細部への気遣いが決め手になることは多々あると思います。
書道展の審査を通じ、こういうことを疎かにしてはいけないと改めて気づかされました。
今日から11月です。
気づけば今年もあと2カ月ですね。
先日、京都大学の本庶佑特別教授がノーベル生理学・医学賞を受賞されました。
日本人のノーベル賞受賞はこれで24人目。
すばらしいことだと思います。
この研究での発見がもとで「免疫チェックポイント阻害薬」が開発され登場しました。
そして本庶教授が見つけた「PD-1」を応用して開発されたのが「オプジーポ」で、従来の抗がん剤や手術では治せないようながんでも高い効果を示しています。
このように医療の進歩は日進月歩であり、「がんを治せる時代」が近づいているという印象を受けます。
現に、全国がんセンター協議会の生存率調査(2018年5月集計)によれば、臨床病期㈵(ステージ1)の5年相対生存率は、全がんで91.8%となっており、がんは早期発見によって治せる時代となっていることが統計データからも裏付けられています。
私は、がん対策として重要なことは以下の3点だと考えています。
1.がんの原因を取り除くこと。
⇒ 食生活・生活習慣・ピロリ菌除菌などの医療対策
2.適切な定期検査を受診して早期発見に努めること。
⇒ 人間ドックや定期健康診断受診の徹底
3.がん治療のための経済的な備えをしておくこと。
⇒ がん保険・特定疾病のための保険加入等
今回は、2.に関連する、がん早期発見のための検査について情報提供させていただきます。
線虫を使ったがん検査「N-NOSE」です(HIROTSUバイオサイエンス)。
これは、がん患者の尿に含まれる、微量な匂い物質を検知する検査法で、2020年1月の実用化が予定されています。
詳細は以下でご確認ください。
⇒ 線虫がん検査「N-NOSE」検査法は、容器に尿を1滴落し、線虫が近づくか離れるかで判定します。
線虫が近づけばがんである可能性が高いという簡単な方法です。
それでいて、検査の信頼性は90%と高感度であり、ステージ0や1の早期発見が可能です。
また対象となるがんは18種類程度と多く、そのなかには早期発見が難しいと言われるすい臓がんも含まれていて、非常に汎用性が高い検査です。
そして検査費用も8,000円程度と安価となる見込みです。
2020年1月以降の実用化後は、企業の定期健康診断やオプション検査での導入が期待されています。
これはがんの早期発見に対し、大いに期待できるのではないでしょうか。
今後、実用化が近づくにつれて各方面のメディアで情報発信されると思われます。
是非、注目されるとよろしいかと思います。
今やがんが2人に1人が罹ると言われています。
お客様と接していても、がんに対する関心は高いです。
私自身も母をがんで亡くしています。
母はがんが見つかったときはすでにステージ4でした。
がんを治すには、早期発見がポイントであることは間違いありません。
検査技術のさらなる進歩で、早期発見によりがんが治る方が増えていくことを願っています。
当社業務でいくつかトピックスがあるのでご案内させていただきます。
法人のお客様からご要望をいただき、6月より新規の業務を開始しました。
会社の経営理念・社是・座右の銘などの文書を毛筆で書かせていただきます。
ご関心のある方は以下のホームページをご覧ください。
⇒ 筆文字経営理念また、事業承継に関するご相談が増えてきましたので、幅広い相談に応じられるよう、「金融業務2級 事業承継・M&Aコース」の資格を取得しました。
第三者への譲渡や買収などM&Aに関心がある方はご相談ください。
今日から10月に入りました。
今朝の東京は台風一過で晴れています。
10月は下期の始まりですね。
お客様との会話のなかでしばしば話題になるのが、医療保険やがん保険の是非です。
私は多くのお客様へ給付金支払いを経験し、「役にたった」「入っていてよかった」という声を聞いているので、医療保険やがん保険は「必要」という立場をとります。
しかし、不要というご意見もあります。
その理由は以下の2点に集約されます。
1.貯金があるので保険に頼る必要はない。
2.高額療養費制度があるのでかかる医療費は限定的。
なので医療保険やがん保険の必要性についての考え方のヒントになればと思い、今日は高額療養費について解説してみます。
高額療養費とは、医療機関や薬局で支払った額が一ヶ月で上限を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。
ただし入院時の食費や差額ベッド代等は含みません。
この高額療養費ですが、上限額が段階的に引き上げられていて、収入によって現在では結構な負担額になっています。
<高額療養費の上限額(69歳以下)>
平成30年8月診療分から
| 適用区分 | 一ヶ月の上限額 | |
|---|---|---|
| ア | 年収1,160万円~ | 約252,600円 |
| イ | 年収770万円~1,160万円 | 約167,400円 |
| ウ | 年収370万円~770万円 | 約80,100円 |
| エ | ~年収370万円 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
※厚生労働省保険局の資料から編集・簡略化して抜粋
このように年収770万円以上だと約17万円、年収1,160万円以上では約25万円と結構な負担額になります。
また高齢者の場合には医療費が安くなるという認識を持たれている方も多いですが、70歳以上の高額療養費も現役並の収入を得ている方は69歳以下と同じ水準になります。
例えばがん治療で抗がん剤を使用したとします。
抗がん剤は本来は大変高価ですが、健康保険の適用を受けられるので自己負担は3割で済みます。
しかし、元々の金額が高額であれば3割負担でも高額となります。
結果、高額療養費の上限額までは自己負担しなければなりません。
治療が長引き、数ヶ月、数年となると相当な負担となるはずです。
なので私は、自己負担部分を補えるくらいの医療保険やがん保険は必要だと考えています。
少子高齢化・長寿化社会がますます進行していきます。
健康保険料を払う人が減り、保険を使う人が増えていくということです。
なので国も健康保険の財務基盤をなんとか健全化させようとしています。
今のところ、「収入の多い人から医療費を多く取る」という方針が制度に現れています。
いずれにしても医療費の自己負担は今後も増えていくことが予想されます。
こうした背景を考慮されて、民間保険会社が販売している医療保険やがん保険の必要性を考えてみてください。
ご参考になれば幸いです。
当社業務でいくつかトピックスがあるのでご案内させていただきます。
法人のお客様からご要望をいただき、6月より新規の業務を開始しました。
会社の経営理念・社是・座右の銘などの文書を毛筆で書かせていただきます。
ご関心のある方は以下のホームページをご覧ください。
⇒ 筆文字経営理念また、事業承継に関するご相談が増えてきましたので、幅広い相談に応じられるよう、「金融業務2級 事業承継・M&Aコース」の資格を取得しました。
第三者への譲渡や買収などM&Aに関心がある方はご相談ください。
9月に入りました。
東京は、朝晩だいぶ涼しくなり、少しずつ秋の気配を感じるようになりました。
新さんまも出回り、もうすぐ新米の時期ですね。
先日、話題の映画、「カメラを止めるな!」を観てきました。
突如という感じで大評判となった映画です。
予告編を観ても、単なるホラー映画にしか見えず、「何でこんな映画が評判になるんだろう」という印象でした。
でも、これだけ話題なんだからと、時間をわざわざ作って観に行ってきました。
観てみてビックリ。
この映画、すごいです。
こんな映画、はじめて観ました。
子どもから大人まで例外なく楽しめます。
絶対お勧めの映画です。
あとからこの映画について調べてみると興味深いことがたくさんありました。
製作費はなんと300万円と超低コスト。
監督も役者も無名。
CMや広告もほとんどなし。
なのに国内、海外で数々の映画賞を受賞し、2018年6月に凱旋上映を行ってから、口コミで広がり、大ブレークしました。
純粋にコンテンツだけで評価されたということです。
私たち、中小零細の企業経営者にとっても多くの気づきがあります。
お金や人材がなくても、創意工夫によって付加価値の高い商品を生み出せば、大企業にも勝てる可能性があるのだと感じさせてくれます。
また大規模な広告宣伝をしなくても、口コミでも十分な宣伝効果があることも改めて感じます。
本当によいモノというのは、お客様が勝手に口コミで広げてくれるものですね。
現に私も頼まれてもいないのに、こうして口コミで紹介しているわけですから。
お金もない、人もいない、だからよい商品は作れない、大手には敵わないというのはすべて言い訳ですね。
小さくても、チャンスはいくらでもあるということを私も忘れないようにします。
この映画から勇気と希望をもらった気がします。
映画の公式サイトをリンクしておきます。
このサイトはネタバレしていないので安心です。
ご関心のある方はご覧ください
⇒ カメラを止めるな!当社業務でいくつかトピックスがあるのでご案内させていただきます。
法人のお客様からご要望をいただき、6月より新規の業務を開始しました。
会社の経営理念・社是・座右の銘などの文書を毛筆で書かせていただきます。
ご関心のある方は以下のホームページをご覧ください。
⇒ 筆文字経営理念また、事業承継に関するご相談が増えてきましたので、幅広い相談に応じられるよう、「金融業務2級 事業承継・M&Aコース」の資格を取得しました。
第三者への譲渡や買収などM&Aに関心がある方はご相談ください。
8月に入りました。
今年の夏は本当に暑いですね。体調管理にお気を付けください。
7月6日と26日に、オウム真理教の元教祖麻原彰晃と元幹部、13人の死刑が執行されました。
今もまだ被害者やご遺族の苦悩は続いていますが、日本最大のテロ事件は一つの節目を迎えました。
地下鉄サリン事件は1995年3月20日に東京の中心部で発生しました。
今から23年前、私が大学を卒業し、新社会人になる少し前のことでした。
その年、就職が決まり、私は4月1日から築地にある会社に新入社員として働くことが決まっていました。
入社するのが楽しみで希望に満ち溢れていました。
その10日前、事件が発生し、霞が関や築地の映像がテレビで流れました。
倒れている人を救護する姿や毒ガスマスクをかぶった警察や機動隊の姿があり、ただ事でないことがすぐに分かりました。
その後、事件の全容が少しずつ分かってきて、これから通う会社のすぐ近くでこんな事件が起きたことに恐怖を感じ、会社に行くことが不安になってしまったことを今でも覚えています。
結局、地下鉄サリン事件では13人が死亡し、6,500人が負傷という未曽有の同時多発テロとなったのでした。
事件に関わった幹部のプロフィールを見ると、高学歴で社会人としてのキャリアも高い人間が多くいます。
なぜこんな人物がこのような犯罪に手を染めてしまったのか理解に苦しみます。
もっと他の社会貢献となることに力を注げば、社会から感謝されるような大きな成果をあげていたかもしれません。
幹部の一人の死刑判決で、「師を誤るほど不幸なことはなく、この意味においても被告もまた不幸かつ不運であったと言える」と指摘した裁判官の言葉も印象に残ります。
京セラ創業者の稲盛和夫氏は、次のような人生の方程式を説いています。
人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力
人生や仕事の結果は、考え方と熱意と能力の3つの要素の掛け算で決まるということです。
そして能力と熱意は、0から100まであるのに対し、考え方は、-100から+100まであると言っておられます。
つまり、いくら熱意や能力が高くても、考え方次第で結果は180度変わってくるわけです。
むしろ熱意と能力が高いほど、考え方がマイナスだと、マイナスの度合いはより高くなり、最悪の場合、大きな犯罪を起こしてしまう可能性もあります。
一連のオウム真理教事件をみると、まさにそうだと感じます。
私たちだって、順調なキャリアを積み、能力が上がったとしても、何かのきっかけで考え方がマイナスになってしまう可能性はあります。
だからこそ、何よりも考え方を大切にしなければいけないのだと感じます。
プラスの考え方というのは、「人間として何が正しいかを判断基準とする」ことです。
このような事件が二度と起こらないように、私ひとりひとりが、しっかりと考えていく必要があると感じています。
オウム真理教に関わる事件で犠牲となった方々に心からご冥福をお祈りいたします。
当社業務でいくつかトピックスがあるのでご案内させていただきます。
法人のお客様からご要望をいただき、6月より新規の業務を開始しました。
会社の経営理念・社是・座右の銘などの文書を毛筆で書かせていただきます。
ご関心のある方は以下のホームページをご覧ください。
⇒ 筆文字経営理念また、事業承継に関するご相談が増えてきましたので、幅広い相談に応じられるよう、「金融業務2級 事業承継・M&Aコース」の資格を取得しました。
第三者への譲渡や買収などM&Aに関心がある方はご相談ください。
7月に入りました。
東京はすでに梅雨明けして本格的な夏になりました。
長く暑い夏になりそうです。
サッカーワールドカップ、日本が見事に予選リーグを突破し、決勝トーナメントに進みました。
今日の夜中3時からベルギーと対戦します。
ベルギーはFIFAランキング3位、日本は61位。
明らかに格上相手との対戦ですが、勝利を期待したいと思います。
ランキング1位のドイツが予選敗退するくらいですから、勝負は何があるか分からない、下剋上も十分にあり得ると思います。
それにしても前評判というのはあてになりません。
今回のワールドカップは、大会2ヶ月前に監督の交代があり、その後の親善試合でも良い結果が残せず、グループリーグ敗戦との予想が大半をしめていました。
しかし、はじまってみれば初戦のコロンビア戦に勝利し、その後も善戦し、見事に予選リーグ突破。
諦めない
希望を持つ。
明るく前向きに。
冷静に作を立てる。
今できることにベストを尽くす。
選手と監督のそんな気持ちが伝わってきました。
スポーツから学べることは本当に多いと感じます。
私たちビジネスマンも、他人の評価によって慢心や逆に余計な脅威を抱いてしまうことがあります。
どちらの場合も自分自身の正当な能力を発揮しにくくなってしまいます。
私自身も他人の評価に惑わされない強い心を備えようと改めて感じました。
急遽、日本代表を率いることになった西野監督。
実は、1996年のアトランタオリンピックのグループリーグで、ブラジルに勝ったときの監督なんですね。
世界トップのブラジルを破った「マイアミの奇跡」です。
あの試合も精密な相手分析と、具体的な戦術を実行したことが奇跡を呼んだと言われています。
スポーツも会社も率いるトップで結果に大きな違いが出るという実例だと感じます。
もし今日のベルギー戦に日本が勝ち、ブラジルがメキシコに勝つと、次戦ベスト8で日本はブラジルと戦うことになります。
ブラジルは過去の「マイアミの奇跡」を振り返り、日本を侮れない相手と警戒するかもしれません。
それがブラジルの余計な緊張につながり、日本が勢いに乗り、ブラジルに勝ち、一気にベスト4進出なんてこともあるかもしれません。
そんな夢を描きながら、まずは今日のベルギー戦を応援したいと思います。
今月のトピックスです。
法人のお客様からご要望をいただき、6月より新規の業務を開始しました。
会社の経営理念・社是・座右の銘などの文書を毛筆で書かせていただきます。
ご関心のある方は以下のホームページをご覧ください。
本日は6月1日。
今日の東京は晴れていますが、梅雨入りも近いようですね。
「定年って生前葬だな・・」という書き出しではじまる内館牧子氏のベストセラー小説「終わった人」が映画化され、6月9日から全国公開されるそうです。
今から17年前、平成13年6月の盛和塾の機関誌に、その内館牧子氏の「私の好きな言葉」として紹介された句があります。
「乱れて盛んなるよりは、むしろ固く守りて滅びよ」
これは、大蔵流狂言の先代山本東次郎の言葉だそうです。
現代への警句として示唆に富む非常によい言葉だと思います。
私たちも仕事をしていると、どうしても媚を売ることもあるし、不本意なことでも譲歩せざるを得ないことも出てきます。
その際、「ここまでは譲れる」「ここから先は滅んでも譲れない」というラインをどのレベルに引くかが重要になってきます。
内館氏は、このラインの高低が志だと表現しています。
私は、人としての誇りだと思っています。
売上は欲しい。
喉から手が出るほど魅力的な仕事がある。
でも仕事を取るためには後ろめたい行動を取らざる得ない可能性がある。
そんなときどうするか。
人間として間違っていると判断した場合には、きっぱりと断れるか。
この判断がその先の浮沈を左右するのだと思います。
日大アメフト部の反則タックル問題が大きな話題になっています。
・試合に勝ちたい監督
・試合に出たい選手
それぞれの欲を満たすため、人として間違った手段を使ってしまった。
乱れて盛んなるというより、乱れて滅んでしまったのだと感じます。
こういうことは、企業の不正や政治家の不祥事などにも同じようなことが言えます。
また私たちの日常生活や仕事でも、究極の選択を迫られる場面はあり、決して他人事ではありません。
私自身の「ここから先は滅びても譲れない」ラインをどこに引くか。
私生活でも仕事でも、このラインを意識して過ごしていきたいと改めて感じています。
GWが終わりました。
今日から通常営業ですね。
連休中の5月3日、マリナーズのイチロー選手が、会長付特別補佐に就任したと発表しました。
ベンチ入りメンバーの25人枠を外れ、今年の残りシーズンは選手としてプレーしないとのこと。
来期以降、現役復帰の道は残されているとはいえ、事実上の引退とも受取れます。
ついにこのときがやってきてしまったという思いです。
本人の記者会見では「喪失感」はないと言っていましたが、ファンの一人である私にとっては大きな喪失感があります。
イチローは、オリックスを退団し、2001年にマリナーズの選手として大リーグデビューしました。
そして開幕当初から大活躍しました。
私も2001年に会社員を辞め、フルコミッションの生命保険業界へ転職しました。
新たな業種とフルコミッションという給与形態は希望もありましたが、大きな不安もありました。
そんななかで、同世代のイチローの大リーグでの活躍は、私にとって大きな励みとなり、たくさんの勇気をもらいました。
卓越した技術、ケガをしない自己管理、常に全力・フェアプレーという姿勢は、プロとして職種が違っても見習う点が多くありました。
そして2012年のシーズン途中からヤンキースに移籍してからは不本意な境遇もあったと思います。
ヤンキースからマーリンズと移るなかで、試合出場も限られ、代打などスポットでの出場しかできませんでした。
スター選手がこのような境遇になると腐ってしまったりしますが、イチローにはありませんでした。
そうした「与えられた場所でベストを尽くす」という姿勢は、むしろ全盛期よりもその精神性に感心しました。
イチローの生きざまを見た時、一つの言葉が思い浮かびます。
それは、一燈照隅(いっとうしょうぐう)。
伝教大師 最澄の言葉です。
これは、「自分が今置かれた場所で精一杯努力し光り輝く」という意味です。
まさにイチローにピッタリだと思います。
だからこそ、他のアスリートもイチローを見習う選手は多いそうです。
その影響は野球選手だけでなく他のスポーツ選手にも波及し、私のような一般のビジネスマンにも波及しています。
この言葉には続きがあります。
萬燈照国。
これは最初は一隅を照らすような小さな灯りでも、それに波及されるものが十・百となれば、国中をも明るく照らすことになるという意味です。
イチローの存在は、すでにこのようになっていると感じます。
私自身も見習いたいと思います。
イチローは私の一つ下の44歳。
この歳まで大リーグで活躍できたこと自体が奇跡です。
日本が生んだスーパースター。
立場が変わっても、今後のイチローをファンの一人として追い続けたいと思います。
最後にイチローの現在までの日米通算成績を載せておきます。
日本:1278安打 打率0.353 118本塁打 529打点 199盗塁
米国:3089安打 打率0.311 117本塁打 780打点 509盗塁
改めてすごい選手でした。
4月、新年度がはじまりました。
電車で真新しいスーツ姿の若者をみると、私自身も気が引き締まる思いです。
当社も4月から新年度です。
今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
今から15年前、保険会社の研修でタイのバンコクに行ったことがあります。
現地の若い案内スタッフと二人で雑談する機会がありました。
そのなかで彼が流暢な日本語で私に話したことを今でも覚えています。
「日本人は悪いことをすると自分で切腹するから警察はいらないのですよね?」
江戸時代の昔話がそのまま語り継がれているような話ですが、彼は冗談ではなく、真面目に話していました。
そこには、日本人に対する尊敬と憧れがあるように感じ、私自身、日本人として誇りに思いました。
海外の人からみた日本人には、正直・誠実・潔さという印象が少なからずあったのだと思います。
翻って現在の日本では。
財務省理財局が学校法人「森友学園」に国有地を値引きして売却し、都合の悪いことが記述されている決裁文書を改ざんした問題が世間を揺さぶっています。
首相官邸や政治家からの働きかけ、首相自らの進退に言及する発言に対する財務省の忖度があったのではないかという見立てもあります。
真相は分かりませんが、私が思うことは、ただ一つです。
「改ざんに至るプロセスで、「こんなことは間違っている。私にはできない。」という強い拒絶の声が上がらなかったのか?」
影響力のある地位にいる誰か一人くらいは、絶対にこんなことは許されないと言って、強く拒絶できる人がいなかったのか、ということです。
赤信号みんなで渡れば怖くないと言いますが、誰か一人くらいは、「赤は渡ってはダメ」と言って欲しかったと思います。
私は、京セラ創業者である稲盛和夫氏が主催する経営塾に参加しています。
稲盛氏は、次のように言っています。
「人生も仕事も、人間として何が正しいかを判断基準とする。」
森友問題が罪に問われるかどうかは私には分かりません。
しかし、人間として正しくないことをしているとは感じます。
世論が納得していないのもそうした感情だと思います。
15年前のバンコクの彼がこのニュースを見て日本人に対して幻滅していたら残念でしかたありません。
新年度にあたり、私自身、「人間として何が正しいかを判断基準とする。」ということを再認識し徹底したいと思います。
きれい事と思われる方もいるかもしれませんが、この言葉は、京セラとKDDIを創り、JALを再建させた日本を代表する経営者の言葉です。
私は稲盛氏の言葉を支持します。
今日から3月に入りました。
年度末の会社も多いと思います。
当社も3月が年度末です。
悔いが残らないようにしっかりと仕事に取り組みたいと思います。
平昌オリンピックが閉会しました。
北朝鮮が特例で参加したり、アイスホッケー女子で南北合同チームが結成されて融和ムードを演出するなど、政治色が強い印象を受けました。
しかし、日本選手は大健闘しました。
日本は、金4、銀5、銅4の計13個のメダルを獲得し、メダル総数では過去最高を更新しました。
個人競技も団体競技でもメダルを獲得し、すばらしい結果と感動を残した選手たちに拍手を送りたいと思います。
個人的は、11月の大けがで休養し、ぶっつけ本番でのぞんだフィギュアスケートの羽生選手に注目していました。
仕事の合間に時間を作り、ショートプログラムとフリー、両日ともにリアルタイムで演技を見ました。
不安と重圧のなか、見事に金メダル。
技術はもちろん、精神力に感動しました。
4年に1度のオリンピック。
1つの演技、レースに4年間の成果を出すことは本当に難しいことだと思います。
オリンピックは技術や演技でも感動しますが、そうした4年間の努力が報われたあとのメダリストの試合後の言葉にも感動を受けます。
今回も、印象に残るメダリストの名言がたくさんありました。
私が印象に残った名言を挙げてみたいと思います。
【2018年平昌オリンピック メダリストたちの言葉】
<平野歩夢選手>
ノーボード 男子ハーフパイプ 銀メダル
・悔しさと同時に刺激を受けた。まだ、この先があるんだとメダルが教えてくれる。
・僕は滑り1つで周りを黙らせることにこだわっている。
<渡部暁斗選手>
ノルディック複合 個人ノーマルヒル 銀メダル
・メダルを取れたという喜びと安心感が半分、金メダルにたどり着けなかった悔しさが半分ある。
<小平奈緒選手>
スピードスケート 女子500m 金メダル
・すべて報われたような気持ちです。
<高木美帆選手>
スピードスケート 女子パシュート 金メダル
・自分たちがパシュートにかけてきた時間はどの国よりも長い。自信を持って挑んでいきたい。
<宇野昌磨選手>
フィギュアスケート 男子シングル 銀メダル
・完璧な演技をしたら1位になれると思ったが、1個目を失敗した時点で笑いが込み上げてきた。
・羽生結弦選手はあこがれ。日本一になることが世界で一番難しいと思うので、いつまでも追いかけたい。
<羽生結弦選手>
フィギュアスケート 男子シングル 金メダル
・僕はオリンピックを知っている(ショートプログラム終了後)
・勝たないと意味がない。何よりこれからの人生でずっとつきまとう結果なので、大事に大事に結果を取りに行きました。
これらの名言を見ると、
・結局は、結果を出さなくては意味がない。
・プロセスの途中で少し失敗しても前向きに頑張る。
・常に向上心を持たないと成長はしない。
・日常の努力が本番にのぞむときの自信になる。
・悔しいと思うことが大切。
・技術や技能にとことんこだわる。
こんなことを教えてくれているように思います。
メダリストだちの言葉は、私たちビジネスマンにとっても、「プロとしての姿勢」として学ぶべき部分がたくさんあると思います。
私自身も一つ一つの言葉を腑に落して、日常の仕事に生かしていきたいと思いました。
今日から2月に入りました。
毎日寒い日が続きますね。
東京は今晩から明朝にかけて雪の予報が出ています。
交通状況に気を付けたいと思います。
先日、政府が公的年金の受取り開始年齢について、受給者の選択で70歳超に先送りできる制度の検討に入ったとの報道に触れました。
つまり年金を75歳とか80歳から受取ることも可能となるということです。
80歳から年金ってすごいですね。
政府は同時に、高齢化の一層の進展に備え、定年延長など元気な高齢者がより働ける仕組みづくりも進める方針とのこと。
2020年中にも関連法改正案の国会提出を目指すといいます。
現在から将来に向かい、少子化・高齢化・長寿化の流れは加速します。
なので、年金受給は高くなり、受給水準は低下していく傾向になると思います。
私自身も現役世代の一人として危機感を持っています。
これからどうなっていくのでしょうか。
私のお客様や知人・親戚をみると、70歳を超えても働いている方も多いです。
ですが65歳で完全に引退されている方もいます。
企業も有能で価値のある人材であれば65歳でも70歳でも在籍していて欲しいと考えるでしょうが、そうでなければ働きたくても働く先がないというケースもあると思います。
高齢者の格差が広がっていくのかもしれません。
そうすると、高齢になっても会社や社会から求められる人材に自分がなっている必要があるのだと思います。
また、収入が減っても、労働収入以外に定期的に入ってくる収入源を持っていることも大切な備えだと思います。
そう考えた時、これからの生き方の備えは次のようなことだと私は考えます。
1.高齢になっても会社や社会から必要とされる人材となるため、専門知識・技能・コミュニケーション能力を高め続けること。
2.こつこつと確実にしかも収益性が見込める個人年金等の金融商品で私的な積立てを行い、高齢になってからの定期的な収入源を準備すること。
3.健康であること。
この3つのハイブリッド運用が人生100年時代を生きる秘訣だと考えます。
私の担当分野は、上記の2です。
特に20代から40代の世代には、必要性を訴え、積極的な情報提供をしていきたいと思っています。
キーワードは、「自助努力」。
会社や社会から何かを与えられるのではなく、自分自身が主体的に努力して将来に備える。
このような姿勢への心がけが今後ますます重要になってくるのだと思います。
「年金70歳超も選択肢」という話題に触れ、改めて気を引き締めているところです。
あけましておめでとうございます。
2018年がスタートしました。
お正月は長野にいる妹家族が帰省しました。
甥と姪が学校で書き初めの宿題が出たということで、指導しました。
小六の甥の課題は、「新たな決意」でした。
手本を書きながら、いい課題だなと思うと同時に、決意だけでは何も変わらないと自分を戒めました。
自分が変わるためには、決意に向かう「具体的な行動」しかありません。
大前研一氏は以下のようなことを言っています。
===
人間が変わる方法は3つしかない。
1番目は時間配分を変えること。
2番目は住む場所を変えること。
3番目はつきあう人を変えること。
この3つの要素でしか人間は変わらない。
最も無意味なのは「決意を新たにする」ことだ。
===
厳しい言葉ですが的を得ています。
今年の干支は戊戌(つちのえいぬ)。
過去の同じ干支は60年前の1958年(昭和33年)でした。
当時の出来事を調べてみました。
・皇太子・美智子様の婚約(初めての民間からの皇太子妃)
・東京タワーの完成(ラジオからテレビへ)
・プロ野球長嶋の巨人入団と川上の引退(主役交代)
・一万円札発行(紙幣の変化)
・チキンラーメン発売(料理の時間短縮)
・軽自動車スバル360の発売(車両需要の変化)
こうみると、今までの常識が変わるような「変化」の年だったのだと感じます。
歴史は繰りかえすと言います。
60年前の世相を踏襲するとすれば、今年のキーワードも「変化」になるかもしれません。
私自身も、今年のテーマを「はじまりの始まり」としました。
将来に向けて、成長と変化のはじまりの一年にしたいと思います。
まずは時間配分を変えることに挑戦し、具体的な行動をしていきます。
本年もよろしくお願いいたします。
先ほど、オフィスのカレンダーをめくりました。
残り1枚。
本日は12月1日。
今年も残り1ヶ月となりました。
悔いのないようにこの1ヶ月を過ごし、1年を締めくくりたいと思います。
先日、前職の「S社長を囲む会」を開催しました。
前職とは、私が22歳のとき、学校を卒業してはじめて社会人として就職した会社です。
S社長は32歳で起業され、2013年、70歳で引退されました。
引退されて4年強、現在75歳になられました。
このたび、有志の数名と企画し、約20名の現役・OBが集まりました。
集まったのは、S社長が直接採用した新卒の社員です。
社長も喜んでくれて、集まった同僚・先輩・後輩たちも楽しい時間を過ごしました。
私は28歳のときに退職しているので、退職してから17年も経っています。
それでも時間のギャップを全く感じず、昔と同じように過ごせました。
毎年、新卒採用を継続されたおかげで会社を通じてこれだけの縁をいただいたことに感謝するとともに、そういう縁を与える会社経営というのは尊いと感じました。
社長からのご挨拶のなかで、「現在は変革の時代。チャンスは大いにある。」とのメッセージをいただきました。
現在、社長は、都心に個人オフィスを構えていますが、趣味やスポーツを満喫し、大変充実した毎日を過ごされていると感じます。
38年間、オーナー経営者として、まさに粉骨砕身、常に緊張感をもって仕事に打ち込んだからこそ、今があるのだと思います。
私は45歳。
70歳まで25年もあります。
S社長を手本とし、誰にも負けない努力でこれからも仕事に打ち込みたいと思います。
社長挨拶のとき、私を含めた参加者全員が背筋をピンと伸ばし、真剣な眼差しで社長講話を聞いている姿が印象的でした。
時が経っても、現役・OB問わず、私たちにとっては、いつまでも社長は社長なんだなと実感しました。
社会人になってはじめて入った会社の社長が、このS社長で本当によかったと改めて感じています。
最後に撮った記念写真を大切にしたいと思います。
東京は秋の深まりを感じられる季節になりました。
今日から11月、今年もあと2カ月ですね。
私は、京セラ創業者の稲盛和夫氏が主催する盛和塾という経営塾に入っています。
塾には日本全国、その他海外にもあり、塾生は10,000人を超えています。
私はいろいろな経緯があって新潟塾に所属しています。
その新潟塾で「機関誌マラソン」という取り組みをしており、私も参加しています。
何かというと、盛和塾では機関誌を発行しており、その機関誌を読み、感想を書くというものです。
機関誌1号は平成4年に発行され、現在まで146冊が発行されています。
10人のチームを作り、毎週、1号ずつ読み、感想を書いてメールします。
1人ずつ必ず1冊ずつ読みます。
毎週日曜日の24時が締切で、締切を2回守れなかった場合、脱落となります。
私は6月からスタートし、5ヶ月が経過しました。
20冊読んで感想を書いたことになります。
今、私のかばんには常に機関誌が入っています。
そして主に電車移動のとき読み、気づきが強い部分にアンダーラインを引き、そこから5つを抜き出して感想を書く。
これを日課にしています。
ページ数が100ページ~200ページあるので、日課にしないと週一回の感想が書けません。
機関誌の内容は、稲盛塾長の講話、塾生の経営体験発表と稲盛塾長のアドバイスコメントが主です。
第1号は平成4年なので25年前ですが、今読んでも全く色あせることなくとても勉強になります。
時代が変わっても経営の本質は不変だということを改めて感じます。
また25年前から稲盛塾長の考え方が一貫していて、まったくぶれていないことにも感動します。
読んでいると、自分の甘さを痛感させられます。
強く思い、出来ると信じて、妥協することなく行動する。
結局はこれに尽きると感じます。
機関誌マラソンはあと2年半続きます。
読んで気づくだけでなく、感じたことを学んだことを実際の行動に落す。
そして昨日よりも少しでも前進する。
機関誌マラソンを完走したあと、自分と会社が発展していると信じ、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。
10月に入りました。
昨日、カレンダーをめくったら、残りがあと3枚しかないことに気づきました。
今年もあと3カ月ですね。
先日、お客様が都内のホスピスに入院しました。
ホスピスとは、「がん」などの終末期のケアを行う施設のことです。
主に痛みや苦しさを緩和させるケアを行います。
今まで一般の総合病院に入院されていましたが、病状を考慮して、より適したケアを受けられるホスピスに転院されました。
お客様のご家族が遠方ということもあり、ご本人とご家族の同意のもと、病院を訪ね、主治医と面談する機会をいただきました。
今後の緩和ケアプロセスや医療サポート体制などを聞き、病室にも入りましたが、全体のサポート体制の充実ぶりに感心しました。
病院というより、自宅で過ごすような感覚で、自宅に医療専門スタッフが常駐しているようなイメージです。
ご本人も全体の環境に大変満足されています。
それでいて、公的な健康保険の適用があり、それゆえに高額療養費の対象となるため、月の医療費は限定的です。
さらにご契約いただいている医療保険とがん保険の支払い対象になるため、お客様の実質的な経済的負担はほとんどないことも分かりました。
これには、ご本人もご家族も安心されていました。
ホスピスは、中世ヨーロッパで旅の巡礼者を宿泊させた小さな教会が由来となっているそうです。
そして旅人が病や健康上の不調で出発できなければ、そのままそこに置いてケアや看病したことから、看護施設全般をホスピスと呼ぶようになりました。
教会で看護にあたる聖職者の無私の献身と歓待を意味する「ホスピタリティ」、今日の病院を意味する「ホスピタル」も、元々はホスピスが語源になっています。
ホスピスには医師や看護師などの医療の専門家だけでなく、精神ケアを担当する宗教家や、散歩の付き添いや話し相手、お茶配りなどを担当するボランティアスタッフも従事しています。
私に細かな説明をしてくれたのもボランティアの女性でした。
こうしたボランティアの存在が、患者さんの快適性を後押ししてくれているのだと感じます。
人は、生まれてきて、やがて寿命を迎えます。
その天寿を全うする最終期にどう過ごすか。
これにはさまざまな価値観があると思いますが、ホスピスも有力な選択肢だと思いました。
ホスピスを語源にし、今日では、「おもてなし」とも訳される「ホスピタリティ」。
ホスピスというのは、人生の最終期における、究極の「おもてなし」だと感じました。
私はお客様と一生涯のお付き合いをすることを信条としています。
長きにわたりお付き合いしてきた大切なお客様です。
私もお客様を支える、おもてなしスタッフの一員として、尽力したいと思っています。
今日から9月です。
東京の8月は雨が多く、夏を実感することが少ないまま、秋の訪れを感じるような天候になっています。
ここ数年、老後のための資産形成に関するご相談が増えています。
その背景にあるのは、少子高齢化・長寿化社会を迎え、社会保障制度の公的年金だけでは老後の生活が不十分という不安からだと思います。
私自身も一般のお客様と同じ不安を感じている一人です。
そうした時代の流れを受けて、政府としても貯蓄から投資へという方針のもと、さまざまな新制度や取り組みをはじめています。
NISA(少額投資非課税制度)・iDeCo(個人型確定拠出年金)、そして来年からはじまる積立NISA(長期型NISA)などが代表的なものです。
また生命保険会社各社でも、米ドル建て年金受取型特殊養老保険・変額個人年金などが、老後の資産形成ニーズに該当する商品で、当社でも個人保険では売れ筋商品となっています。
しかし、選択肢が増えた分、それぞれの特徴をとらえることや、どれを選択してよいか分からないといった新たな課題が出てきていることも事実です。
そうしたなか、森金融庁長官の基調講演の資料を拝見する機会に恵まれました。
その講演のなかで、資産運用の世界を代表する思想家であるバートン・マルキールとチャールズ・エリスがその共著のなかで述べている、「個人が投資で成功するための秘訣」が紹介されていました。
端的で分かりやすく、本質をつくメッセージのため、ご紹介します。
一般の方々がこれから資産運用を検討するなかでご参考になればと思います。
<個人が投資で成功するための秘訣>
1.ゆっくりと、しかし確実にお金を貯める秘訣は再投資(複利)にあることを認識すること。
2.市場の値上がり、値下がりを気にかけず、一定額をこつこつと投資すること。
3.資産タイプの分散を出来るだけ図ること。
4.市場全体に投資するコストの低い「インデックスファンド」を選ぶこと。
※ 投資の大原則 (バートン・マルキール著・チャールズ・エリス著)より
これをもう少し分かりやすい表現にすると以下のようになります。
1.時間と複利を味方にすること。
2.ドルコスト平均法を活用すること。
3.分散投資を図ること。
4.投資コスト(手数料等)を意識して商品を選択すること。
どれも私が日々お客様へご案内していること、私自身が取り組んでいることとおおむね一致しています。
20年・30年先への資産形成。
少子化による社会保険料減収、高齢化長寿化による社会保障費増大。
国の収入が減り、支出が増えるという構造がますます加速していくなか、個人の自助努力による資産形成は今後ますます必要性が高まります。
私も当社も、老後の資産形成に関する情報提供はこれからも積極的にしていきたいと思っています。
そのためには私自身も情報収集を怠らず、正しい情報をタイムリーにお届けすることを心がけます。
幅広く商品やファンドを検討しながら、ご自身に合った資産形成の方法を見つけてくださいね。
本件についてご関心やご質問がある方はお気軽にお問い合わせください。
今日から8月ですね。
梅雨明けはしたものの、はっきりしない天気が続いています。
そんななか、夏の高校野球、東京都代表が東西ともに決まりました。
私の母校、佼成学園は、西東京でベスト8まで勝ち進みましたが、今年も甲子園への切符を手に入れることはできませんでした。
西東京は東海大菅生が優勝。
2強といわれた日大三と清宮選手擁する早実に勝っての優勝ですから、堂々と甲子園で戦い、全国優勝を目指して欲しいと思います。
今年の予選も応援に行きましたが、自分が高校生だたときのことが蘇り、本当に熱くなりました。
負けはしましたが、連戦、すばらしい試合をしてくれた後輩選手たちに感謝です。
そういえば、大阪の女性国会議員が浦和レッズのサポーターを批判して炎上していましたね。
ツイッターに投稿した記事をそのまま載せると、以下の通りです。
「サッカーの応援しているだけのくせに、なんかやってる気になってるのムカつく。他人に自分の人生乗っけてんじゃねえよ。」
私もある意味、現役選手たちに自分の人生というか夢を乗っけて応援しています。
自分が甲子園に行くという夢を実現できなかったので、今の選手たちに夢を託しているわけです。
そういう意味では、私も、この女性議員にとっては批判の対象となるのだと思います。
確かに直接自分に向けられた言葉ならば、言葉も汚いし、嫌な気分になります。
ただ、その批判に批判で返したり、相手の考え方が間違っていると議論することはないと思います。
この人とは、価値観や考え方が合わないと思って終わりです。
自分と考え方や思想が違う相手を敵と思うことって本当に危険だと思います。
敵の敵は味方となり、敵の味方は敵となってしまい、大きな争いの元になるからです。
ただ「自分とは違う」と思えばよいのだと感じます。
私にとっては、野球というスポーツを通じて、自分の夢を託せる野球部の存在がありがたいし、すばらしい仲間や先輩後輩と出会えたことはすばらしいことです。
先日、坂東玉三郎さんの講演を聞く機会がありました。
参加者の一人が、「文化にもグローバリズムが広がり、日本のよき文化が失われつつあることに懸念を感じている。どう思われますか?」と質問しました。
それに対して、玉三郎さんの回答が印象的でした。
「あなたがどう危機感を覚えようがかまわない。だけど、日本の文化こそがすばらしい!と声を大にして多数に向けて発信することは勧めない。まして他人に強要してはいけない。ただあなたが、「日本の文化はすばらしい」と思えばよい。」
私もまったく同感です。
昨今のマスコミやインターネットを通じた批判の応酬に触れて、価値観の主張が他人への強要や押しつけにならないように、自分自身も気を付けなければと改めて気づかされました。
都議選の開票結果が出ました。
私も、6月30日に期日前投票を済ませ、都民の一人として結果を見守りました。
すでに大きく報道されていますが、結果は以下の通りです。
都民ファーストの会が49議席を獲得して都議会第一党に。
公明党など小池知事を支持する勢力を含めた勢力は79議席で過半数に。
自民党は前回の59議席から大幅減の23議席で惨敗。
投票率は51.28%(前回比+7.78%)。
小池都知事は、約1年前の昨年7月に行われた都知事選の勢いそのままに都議選でも大勝利しました。
この都議選の結果を受け、小池知事は日本の最も影響力のある女性になったと言っても過言ではないと感じています。
今回の都議選を見ると、都民ファーストの会を選択したというより、自民党にNOを表明した有権者が多かったように感じます。
自民党勢力の国政レベルにおける不祥事疑惑などの影響もあったと思います。
が、既存勢力への拒否という視点では、イギリスのEU離脱やトランプ大統領の誕生ということにも共通する部分があるかもしれません。
国内を振り返れば、8年前、2009年9月の民主党による政権交代にも共通点を見いだすことができるように感じます。
都議選は国政にも大きな影響を及ぼすと言われています。
以下は、過去の都議選とその後の国政選挙の関係です。
2005年7月都議選 自民党50議席割れで大敗。その後、小泉内閣解散。2005年9月衆議院選挙で自民党圧勝。
2009年7月都議選 民主党54議席で都議会第一党に。自民党38議席で大敗。2009年9月衆議院選挙で民主党による政権交代。自民党は野党に。
これを見ると、自民党にとっては、都議選での敗北という逆境を、逆にチャンスとした事例と、逆境のまま埋没してしまった事例の両方があるのですね。
これは、当時の国のトップ、総理大臣(=自民党総裁)の決断力と行動力の差だったと感じます。
現在の衆議院の任期は2018年12月です。つまり、あと1年5カ月の間に、必ず、衆院選挙はあります。
私たちにとっても、再度、重要な選択を迫られる選挙となりそうですね。
それにしても、都民ファーストの会が立てた50人の候補者のうち、ほとんどが政治家経験のない新人です。
にも関わらず、50人中49人が当選というのは驚きです。
私の居住地、小金井市でも、現役の精神科医の候補者が当選しました。
ポピュリズム台頭への懸念も囁かれていますが、素人集団の候補者を率いて勝利した小池知事のリーダーシップは、企業経営においても勉強になる点が多々あると感じました。
いずれにしても、2020年の東京オリンピックは、小池都知事と今回選出された都議会議員で迎えることが決まりました。
これからの東京都行政と議会運営を見守りたいと思います。
今日から6月ですね。
6月は梅雨に入ると鬱陶しい日が続きますが、紫陽花が見頃になりますね。
私も今年は鎌倉の明月院に出かけて紫陽花を楽しみたいと思っています。
さて生命保険文化センターから平成28年度の生活保障に関する調査が発行されています。
現在の暮らし向きから老後に関することまで非常に幅広く調査されています。
そのなかでお客様からよく質問を受けるような関心が高いと思われる項目がいくつもありましたので抜粋してみました。
10年前と現在を比較した表を作成してみました。
10年前と比べて、現在はどのように変化したのでしょうか。
なかなか興味深いデータですのでよろしければご参照ください。
| 平成28年度 | 平成19年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 入院時の入院日数 | 19.1日 | 22.9日 | ↓ |
| 入院時の自己負担費用 | 22.1万円 | 30.1万円 | ↓ |
| 疾病入院 保障付生命保険の加入率 | 69.5% | 71.3% | → |
| 疾病入院加入日額 | 9,877円 | 10,221円 | → |
| がん保険等がん関連保障の加入率 | 37.8% | 31.2% | ↑ |
| 個人年金保険の加入率 | 21.4% | 21.0% | → |
| 生命保険加入率 | 81.0% | 79.9% | → |
| 生命保険加入金額(男性) | 1,793万円 | 2,382万円 | ↓ |
| 生命保険加入金額(女性) | 794万円 | 980万円 | ↓ |
| 介護保険関連保障の加入率 | 9.9% | 6.5% | ↑ |
| 年間払込保険料(生命保険全体) | 19.7万円 | 23.7万円 | ↓ |
※公益社団法人生命保険文化センター 「生活保障に関する調査」 より
まず目立つのは、がん保険と介護保険の加入率増加です。
介護保険分野は近年、各保険会社で商品開発が進んでいます。
高齢化社会が加速するなか、この分野の関心はますます高まるのだと思います。
日本人のがん罹患率は、男性は2人に1人、女性は2.5人に1人です。
これを考えると、個人的にはがん保険の加入率はもっと高くていいのかなと思います。
また、生命保険加入金額(死亡保険金)と年間払込保険料(掛け金)は減少しています。
この要因はいろいろなことが複合的に絡み合っているだと思いますが、あえて要因を類推すると、この10年間で、以下のような変化があったからでしょうか。
・男性の加入保険金額の減少要因⇒女性の経済的自立度向上と婚姻率の低下
・年間払込保険料の減少⇒若年層の所得低下と保険会社各社の保険料水準の低下
少し意外だったのは、生命保険・医療保険・個人年金の加入率が、この10年間、ほぼ横ばいであることです。
将来的な社会保険制度の給付水準が低下されることが予想されるなか、この分野の加入率が増加していてもよさそうですがそうでもないのですね。
保険見直しなどの一助となれば幸いです。
これ以外にも非常に多くのアンケート結果がレポートされています。
ご関心のある方は以下もご覧ください。
⇒ 公益社団法人生命保険文化センター 「生活保障に関する調査」
今日は5月1日です。
大型連休で今日もお休みを取られている方も多いかもしれません。
私も昨日は山梨の昇仙峡と金桜神社に行ってリフレッシュしてきました。
連休中ということもあり、今日は、いつもの仕事関連の話題とは違ったことを書いてみます。
実は私は、長く書道を学んでいます。
幼少の頃から教室に通い、高校の書道の先生が著名な先生で、その先生の影響で現在でも続けています。
そして2年前から、小金井市で書道教室を開催していて、現在では新潟でも教室をさせてもらっています。
これまで振り返ってみると、仕事をしながら書道を学ぶことで精神情緒のバランスと安定が図れたと感じています。
仕事は「論理」。
書道は「感性」。
一見、全く相乗効果を見いだせない2つのことが、実際には、それぞれを高められる結果となったような気がしています。
師は、書文化を広く広めること、門人の経済負担をできるかぎり軽くすること、この2つをポリシーにされていました。
なので私も、この2つを守り、門戸を広げるため大人も子供も初心者でも参加しやすくし、会費もできるだけ少額で実施しています。
教室では、大人は王義之などの中国古典を題材にした臨書、子供は専用機関誌を活用した教育書道を行っています。
誰でも参加できますのでご興味のある方はご参加ください。
遠方の場合には通信教室で対応します。
漢字は中国から輸入されました。
ひらがなは、漢字を元に日本人が作りました。
中国オリジナルの漢字を、日本人がそれを元にひらがなとして加工したのです。
そして現在、一般に書かれている文章は、漢字とかなが交じった文章です。
そうは言っても元は中国です。
「弘法も筆の誤り」で有名な空海(弘法大師)も唐時代の中国に渡り、書を学んできました。
今でも日本と中国の書道交流は盛んで、両国の書文化を通じた関係は比較的良好だと感じます。
お互いを尊重しているからです。
近隣諸国との政治的な軋轢が強まっています。
お互いを尊重するという文化交流は、緩和のヒントになると思っています。
<書道教室>
会費:大人500円 子供100円
小金井教室 5月21日(日) 6月18日(日) 7月30日(日)
新潟教室 5月24日(月) 6月28日(水) 7月26日(水)
ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
4月、新年度を迎えました。
都心の桜は満開。
まさに春爛漫、大変爽やかな季節となりました。
先日、公私ともにお世話になり、尊敬する経営者、「ばかうけ」で有名な栗山米菓の栗山社長が以下のような話をされていました。
新年度にあたり、以下、ご紹介するとともに、私自身の事業活動の縁(よすが)としたいと思います。
***
売上をあげることだけを優先したり、テクニックに走る営業マンは怖くて使えない。
お客様のことを考え「きれいな心」で仕事をする営業マンを育てたい。
***
お客様の役にたつこと、喜ぶことを、「きれいな心」で実践する。
結果、お客様から評価され、売上も利益もあがる。
そして夕方は早く帰り、家族との時間を大切にする。
そうすると家庭が円満になる。
家庭が円満になれば、気持ちに余裕ができて、仕事に集中でき、よりお客様のことを考えられるようになる。
その結果、仕事もますますうまくいく。
同社は毎年、成長発展され、好業績を継続しています。
そして社長自身がこれを実践されています。
だからこそ説得力があります。
企業や政治家、または役所などの不祥事をみるとき、いろいろな言い分はあるにしても、結局はこの「きれいな心」が抜け落ちてしまった結果だと感じます。
私自身も、きれいな心で仕事をすることを絶対に忘れないようにしたいと改めて感じています。
また「きれいな心」で仕事をしていれば、間違いはないと信じています。
当社は3月で10期目の決算が終了し、4月から11期目がはじまりました。
会社が10年継続できたことは、お客様をはじめ、多くの支援者や、当社業務をサポートしてくれた方々のおかげです。
本当にありがとうございます。
11期目からも「きれいな心」で仕事をすることをお約束します。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
今日から3月です。
春はもう、すぐそこ。
1ヶ月後には桜が咲きますね。楽しみです。
年度末の会社も多いと思います。
当社も3月が年度末です。
悔いの残らないように、また1ヶ月、頑張りたいと思います。
すでに報道でご存じの方も多いと思いますが、生命保険会社各社では、4月2日から保険料の値上げを予定しています。
これは、昨年2月からのマイナス金利政策により、長期金利が低迷し、生命保険会社の運用難が要因です。
お客様の大切な財産を守る生命保険会社は健全性の維持が必須のため、金融庁は標準利率を引き下げました。
これにともない、各生命保険会社では予定利率を引き下げ、保険料を値上げすることとなりました。
私たち販売代理店としても影響は大きく、4月以降の対策を考えていかなければいけません。
今回、各生命保険会社が一斉に値上げを予定しています。
この件に関し、お客様をはじめさまざまな方からお問い合わせをいただいています。
そのなかで、少しご認識の相違などを見受けられる点もあるため、重要と思われる点について少し解説しておきます。
以下の2点が重要なポイントです。
1.今回の値上げは4月2日以降の新規契約が対象です。既存契約については影響がありません。
2.すべての保険商品が値上げされるわけではありません。
<値上げ予定の商品と値上げ率>
終身保険・学資保険・年金保険等の貯蓄性の高い商品
値上げ率:10%~20%
※定期保険等の掛捨て商品も一部値上げ予定がありますが、数%程度と値上げ率はわずか。
<値上げしない保険商品>
医療保険・がん保険・収入保障保険等の掛捨てタイプの保障系商品
<保険会社によって対応が分かれる商品>
逓増定期保険等の一部の法人向け商品⇒値上げする会社としない会社があります。
なので、値上げが予定しているからと言って、必ずしも、3月中にあわてて契約や見直しをする必要はありません。
ご自身のニーズや比較検討をしっかりしてご契約することをお勧めします。
ただし、将来の資産形成を考えての終身保険や年金保険、お子様のための学資保険等について、契約するご意向を固められている場合には、3月中の契約の方が有利ではあります。
私たち保険代理店は、商品の価格決定権はありません。
経営しているコンビニの売れ筋商品が、10%~20%値上げされてしまうのと同じです。
このなかで、どのように事業を運営していくか。
しっかりと変化への対応をしていきたいと思います。
年が明けたと思ったら、あっという間に1ヶ月が経ち、今日から2月がはじまりました。
1月のトピックスといえば、やはり、トランプ大統領の就任だと思います。
やはり世界的なイベントなので、この件に関する感想と考えを書いてみます。
まず、マスメディアの予想はあてにならないということ。
英国のEU離脱に続き、米国大統領の選挙も、多くのマスメディアの予測が外れたと言えます。
また選挙期間中、トランプ大統領が過激な発言を繰り返しましたが、就任後は落ち着き、現実には実行できないだろうという予測も外れました。
善くも悪くも、トランプ大統領は自らの公約を就任から10日余りで次々に実行しています。
メキシコ国境の壁建設計画、TPP離脱、難民やイスラム圏市民の入国制限、そしてこれを批判した司法省トップの解任。
まるで中小企業のオーナー経営者が、鶴の一声で会社の大方針を転換していくかのように。
国内企業の法人税減税、輸入関税の引き上げなどもこれらに続くとみるのが自然だと思います。
2000年以上も昔、古代ローマの実質的な初代皇帝であるユリウス・カエサルは以下のように言っています。
「人間ならば誰にでも、現実のすべてが見えるわけではない。多くの人は、見たいと思う現実しか見ていない」
まさに多くのマスメディアや私たちは、「見たいと思う現実」で予測しましたが、本当の現実は違ったのでした。
この言葉は実に多くのことを示唆してくれていると感じます。
見たいと思う現実ではなく、見なくてはならない現実を認識し、受け止め、主体的に対応する。
私たち自身がこんな姿勢を心がけることが今後ますます重要になってくると感じています。
私の仕事に関連した、「見なくてはならない現実」の一つに、社会保障制度の水準低下への懸念があります。
少子高齢化、長寿化による、医療費や給付年金の増大により、これは避け通れない現実だと思っています。
客観的な事実を検証し、自助努力の重要性をお客様へ正しく伝えていくことが当社と私の使命だと考えています。
新年明けましておめでとうございます!
2017年、平成29年がスタートしました。
本年もよろしくお願いいたします。
生命保険の仕事をしていると、多くのお客様の入院や手術に関わります。
そして、医療技術の日進月歩の進歩に感心することも多いです。
昨年もそれを実感する喜ばしい事例がありました。
お役に立つ方もいらっしゃると思い、情報提供させていただきます。
70代女性のお客様です。
10年前に保険契約をいただき、そのときは健康そのものでした。
しかし、3年前、C型肝炎に感染していることが判明。
30年前に善意で行った献血が原因である可能性が高いことも分かりました。
長い歳月の潜伏期間を経て、感染が顕在化したのでした。
その後、肝機能を改善するためのお薬を定期的に注射する対処療法で治療を続けていましたが、経過は芳しくありませんでした。
しかし、昨年、9月、C型肝炎の特効薬が国内で発売されたことを知ります。
その薬の名称は、「ハーボニー」。
C型肝炎ウイルスの除去について、100%の著効率の薬です。
この薬を12週間、一日一錠の錠剤を飲むだけで、C型肝炎ウイルスが除去できると言われています。
さらに、本来一錠8万円、12週間で約720万円かかる医療費が、医療費助成の制度を活用することで、患者負担は月に1万円~2万円ですみます。
実際、このお客様は12月に10日間入院をして、検査やこの薬を飲みはじめましたが、退院したときに病院で支払った医療費は6,000円だったと聞いています。
別に医療保険に加入しているので、入院給付金を受取ることができ、費用がかからないばかりかプラスになります。
すでに退院し、あとは残り9週間くらい、薬を飲み続けるだけです。
それで完治できる可能性が非常に高いです。
幸い副作用も出ず、快適な生活を送られています。
私はこのお客様と接していて、以下の2つのことを学びました。
・諦めなければ道は開けるということ。
・過去を嘆かず、未来を思う大切さ。
献血で感染した可能性が高いことが分かっても、恨んだり、嘆いたり、一切されませんでした。
過去を嘆いても変わらないことを知っているからです。
そして諦めずそのとき受けられる治療を続け、明るく未来を描き続けました。
その結果、今回の新薬での治療を受けられたのだと思います。
これは、医療にかぎらず、会社経営でも日常生活でも通じることだと思います。
今回もお客様を通じて、すばらしい学びと気付きをいただきました。
C型肝炎ウイルスの感染者は、日本人に約200万人いると推計されています。
この情報が少しでもお役に立てばうれしく思います。
健康は本当に尊いですね。
今年一年、みなさまにとって、明るく過ごせる年となるように願っています。
今日から12月。
今年も残り1ヶ月、悔いのない行動で、よい一年の締めくくりとしたいと思います。
先日、ピロリ菌の除菌治療を受診し、除菌が完了しました。
ある方の勧めでピロリ菌感染の検査をし、陽性だったため、除菌の治療を受診しました。
ピロリ菌というのは、胃に生息する細菌で、胃がんをはじめ、胃腸系疾患の原因となるものです。
日本人の約50%が感染していると言われていて、年齢が高くなるほど、感染率も高くなります。
そして日本人の感染率は先進諸国のなかでは最も高く、この原因は水道水や井戸水の摂取という説もあります。
欧米では水道水をそのまま飲みませんが、日本の場合、水質がよいため水道水を飲むことも多く、水のよさが結果的に感染率を高めているという皮肉でもあります。
また、ピロリ菌が陽性であることが分かっており、除菌していない状態で生命保険に申込むと、胃および十二指腸の病気は一定期間保障しないという条件がつく場合が多いです。
このことは、保険会社として、ピロリ菌が胃や十二指腸の疾患の原因となるリスクを統計的に認知していると言えます。
若いうちに除菌しておくほど、将来の胃腸系疾患のリスクが低減されると言われています。
特に20代から40代の世代には検査されることをお勧めします。
ピロリ菌検査から除菌までの流れは以下の通りです。
1.定期健康診断のオプションでピロリ菌検査を実施
2.陽性と判明
3.一週間の投薬(錠剤の飲み薬)
4.投薬終了から3カ月後、除菌できているかの検査(呼気検査)
5.さらに一週間後、除菌結果判明。
全体期間は約4カ月、費用は自由診療で約2万円です。
除菌後、明らかに体調がよくなり、体質が改善したような気がします。
投薬期間だけお酒を抜かないといけない意外は特に不便や負担感はありません。
関心のある方は検査をしてみてくださいね。
朝晩はすっかり肌寒くなり、秋の訪れを感じる毎日となりました。
今日から11月。
今年も残り2カ月となりました。
10月26日、小泉進次郎氏が主導する自民党の小委員会で、雇用・年金・医療介護についての新たな提言がありました。
このなかで私は、医療介護分野の、「健康ゴールド免許」に注目しました。
これは、非喫煙者や健康診断を定期受診するなど、自身の健康管理に積極的に取り組む人に対して、医療費の自己負担を低減する制度です。
具体的には、現状の3割負担から2割負担に引き下げるとのこと。
このような取り組みについて、私は賛成します。
こうした仕組みがあることで私たちの健康に対する関心が増し、長い目でみれば医療費の抑制につながるのではないでしょうか。
民間の生命保険では、顧客の健康リスクにおうじて保険料率を変えるという仕組みは、すでに始まっています。
その一例を以下にご紹介します。
<保険料が安くなる例>
・非喫煙者だと保険料が最大30%割り引かれる死亡保険
・契約後、入院や手術をしないか、あっても軽微な入院のみの場合には、5年ごとに保険料が割り引かれる医療保険
逆に既往症等により保険料が割高になる場合もあります。
このように生命保険分野では、リスク細分化を実施することで顧客に対して契約の公平性を保とうとしています。
またリスク応分の保険料をご負担いただくことで、将来の保険金支払いに対し安定性と安全性を高めています。
そしてこのリスク細分化の傾向はますます加速しています。
リスク細分化による保険料率の増減は、各保険会社の差別化ポイントにもなっていて、競争原理が働くことで、商品開発を活発化するインセンティブにもなっているからです。
公的な社会保障制度も、このような民間の取り組みを大いに参考にして欲しいと思います。
私たちは、まずは、自分の健康維持や増進について自助努力が大切です。
それには、よく働く、バランスのとれた食事をする、適度な運動をする、十分な睡眠をとる、感性的な悩みをしない、ことです。
それでも、病気になったり事故にあったりする場合もあります。
そんなときは、困った人を社会全体で手を差し伸べて助ける。
それを可能にする相互扶助のインフラが物心両面で整っている。
将来もそんな社会であって欲しいですね。
10月に入りました。
東京の9月は雨が多かったですね。
今月は、天気に恵まれて、スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋を満喫できるような清々しい1カ月になるといいですね。
政府は9月26日、年金機能強化法改正案を閣議決定しました。
これは、従来、国民年金と厚生年金を合わせて25年間だった年金受給資格期間を10年間に短縮するものです。
つまり、10年以上、年金保険料を支払っていれば、わずかでも老後に年金が受取れる制度です。
これによって、年金を受け取れる高齢者が増えます。
私はこれはこれで良い改正だと思います。
私自身、現在44歳で、22歳から年金保険料を支払っていますから、すでに受給権は得たことになります。
しかし、少子化、長寿化、高齢化社会の本質的な問題解決は、65歳以降も働いて所得を得る人が増えることだと思っています。
現在、65歳から年金を受取れますが、65歳の人の平均余命はざっと90歳。
今や「人生80年」ではなく、「人生90年」の時代が到来しています。
65歳から25年間も年金を受取る世代が増え続ける一方で、それを支える現役世帯の人数は減るわけですから、年金制度が危ぶまれるのは当然です。
私は、生涯現役を目指したいと思います。
例えば80代でも所得を得て、税金を納める。
一定以上の所得のため年金は受取らない。
毎日忙しく仕事をして、よい生活習慣を持続させて、健康を維持して、医療費も使わない。
こんな人生を送りたいと思っています。
私はこのような人生に生きがいを感じます。
そしてそれは、結果として社会貢献にもなると思っています。
それを実現できる「働き方」をこれからも考えていきたいと思います。
みなさまはどのようにお考えですか?
私が、このような価値観を持つようになったのはある人との出会いがきっかけです。
田中真澄という方です。
現在80歳になっても、現役でバリバリ仕事をしています。
その田中真澄氏が久しぶりに講演をされます。
私は過去5回聴いていますが、聴くたびに新たな希望と気づきをもらっています。
もしご興味あれば以下をご覧ください。
今日から9月がスタートしました。
台風も過ぎ、朝晩は秋の訪れを思わせるような爽やかな風を感じるようになりました。
先月は、リオ・オリンピックの15日間、本当に盛り上がりました。
日本が獲得したメダルは、金12、銀8、銅21の合計41個。
合計メダル数は過去最高とのこと。
閉幕から少し時間は経ちましたが、メダルを獲得した選手や競技を振り返ると、今でも感動がよみがってきます。
陸上男子4×100mリレーの銀メダルのシーンは10回以上繰り返し観てしまいました。
本当にすばらしいスポーツの祭典でした。
今回、各国の選手のなかには、残念なことに、大会前、大会中を通じて、不正もありました。
ドーピング問題、虚偽の強盗被害証言、その他不適切行為など。
しかし日本人選手にはそのような不正行為はありませんでした。
私はこれを誇りに思います。
大会前に代表候補選手が違法賭博行為の発覚により処分を受けましたが、これも水際のコンプライアンス体制がしっかりしていたとも思えます。
また卓球では、水谷準選手がシングルスで銅メダルを獲得し、日本人初の卓球シングルスでのオリンピックメダリストとなりました。
この卓球で、各国選手が使用するラケットラバーが物議をよびました。
ラバーの裏面に塗布されるブースターと呼ばれる補助剤です。
裏面にこの補助剤を塗布すると、ラバーの反発力が強化され、スピード、威力が増し、ボールコントロールも安定するといいます。
使うと試合は圧倒的に有利になります。
しかし、この補助剤は、国際卓球連盟が使用を禁止しています。
つまり、違法ラバーです。
ところが、現実には、検査体制の甘さもあり、各国の多くの選手がこの違法ラバーを使用していると言います。
水谷選手は、この違法ラバーを一切使用しませんでした。
不正が横行する環境に屈せず、正々堂々、フェアプレーで試合にのぞみ、そして見事に銅メダルを獲得。
れこそが私たちが学ぶスポーツマンシップだと思います。
ビジネスでも、儲けを優先することで不正を行なう企業があります。
しかし、そんな企業は長続きしません。
人として何が正しいかを判断基準とし、誰にも負けない努力で勝利をつかむ。
その重要性をオリンピック選手から学ぶことができました。
4年後はいよいよ東京オリンピック。
日本人にふさわしい、フェアプレーのオリンピックを目指して欲しいと思います。
私自身も、4年後の東京オリンピックを心から楽しめるように、毎日を全力で過ごしたいと思います。
8月に入りました。
東京もやっと梅雨明けし、これから夏本番です。
昨日の都知事選の結果がでました。
政党の推薦を受けずに出馬した小池百合子氏が290万票を獲得して圧勝。
初の東京都知事が誕生しました。
小池氏は、舛添前都知事の辞任の直後から出馬の意向を示し、その後、政党組織の反対を押し切って出馬。
ご本人も「崖から飛び降りる覚悟」と表現したように、まさに退路を断っての選挙戦でした。
その終始一貫した主体性や覚悟、ぶれない姿勢が有権者の心を掴んだのだと思います。
また今回の選挙では、インターネットやSNSの普及で、個人のパワーが組織に十分に対抗できる環境になってきているとも感じました。
この点は、政治の世界だけでなく、ビジネス界でも、個人事業や中小企業にとってはチャンスが広がっているのだと思います。
それにしても、女性の活躍が目覚しいです。
秋のアメリカ大統領選挙では、女性初の大統領誕生が現実味を帯びてきています。
当社のお客様でも女性の起業者が増えました。
日本はこれから人口が減ります。
そのなかで国の経済生産性を高めるには、女性の活躍が不可欠です。
そのためには、女性の産前産後の勤務環境や職場復帰、待機児童の問題など、女性がより経済参画しやすい環境づくりは急務です。
そういう意味では首都東京の知事に女性が就任されたことは有意義だと思います。
今週末にはリオ五輪が開幕し、その後は一気に東京五輪へのムードが高まることでしょう。
新都知事には、4年間、東京の顔としてしっかりと舵取りをしていただきたいと思います。
7月になりました。
早いもので今年も今日から後半がはじまりました。
先日、イギリスで、EUからの「離脱」か「残留」かを問う、国民投票が実施されました。
結果は、「離脱」。
事前の予測は「残留」ということもあり、結果を受けてからのイギリス国内世論や世界の金融マーケットは大騒ぎとなりました。
面白半分で「離脱」に投票した若者から、まさか「離脱」になるとは思わなかった、結果に後悔している、投票をやり直したいなどと後悔の声も聞こえてきました。
現状に対する不満から、外部環境が変われば、自分自身の境遇も変わると思い、安易に変化を求めた結果なのかもしれません。
やはり、今の境遇の原因を自分自身に向けて、境遇を変えるためには自分自身を変えなくてはならない。
このことは万国共通の原理原則なのだと思います。
国民投票は私たち日本人にとっても他人事ではありません。
日本国憲法には国民投票について以下のように規定しています。
第九六条 【憲法改正の手続、その公布】
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
つまり、衆議院・参議院それぞれで2/3以上の賛成があれば、憲法改正についての国民投票は可能となります。
現在の自公連立与党の衆参両議院の勢力をみると、国民投票の実現可能性は低くないと思います。
もし日本で国民投票が実施された場合、自分の一票に責任と自覚を持たなければいけないと改めて感じます。
一票は国を変える力がある。
イギリスの国民投票をみて強く感じました。
7月10日に参議院選挙があります。
この選挙も重要な選挙です。
私自身も一人の有権者として、しっかりとした投票行動を取りたいと思っています。
今日から6月がスタートしました。
一年の半分を迎え、気を引き締めて今月も取り組みたいと思います。
5月27日に米国のオバマ大統領が被爆地広島を訪れました。
国内世論はおおむねオバマ大統領の訪問とスピーチを高く評価しました。
特に私は、被爆者の方々や広島市民が「謝罪」の声を大にせず、紳士的な態度で大統領を迎えたことに対して心から敬意を表したいと思います。
こういう姿勢は日本人の持つ気質であり、誇りに思います。
私は過去に、戦争の本質を知ろうと、書籍を読んだり資料館を訪問したりしました。
その経験を通じ不勉強ながらも感じたことがあります。
それは、かつての敵国に対して、「恨み」や「憎しみ」のようなものを感じないこと。
70年前、命をかけて戦った先輩方は、「恨み」や「憎しみ」も洗い流してくれたように思います。
そして未来に希望を向けたからこそ、その後の戦後復興や高度経済成長が実現できたのだと思います。
私たちが今、平和な暮らしができるのは、そうした先輩方の存在があったからです。
オバマ大統領と被爆者の方との抱擁をみたとき、謝罪の言葉はなくても、思いは十分に伝わったと感じました。
過去と他人は変えられない。
未来と自分は変えられる。
これは国も会社も個人も同じです。
これからも平和な日常が続くといいですね。
新年度がはじまったかと思ったら、もう5月。
大型連休でお休み中の方も多いかと思います。
お車を運転される方は安全運転でお過ごしください。
三菱自動車の燃費不正問題がクローズアップされていますね。
同社は2000年と2004年にリコール隠しの不正をしており、燃費データの不正については、1990年代から行なっているとの報道もあり、消費者の一人として落胆しています。
最近、大手企業の不正問題が目に付きます。
こうした問題を目にして、私なりに、「お客様目線」について考えてみました。
「お客様目線」という言葉は聞きなれた言葉になっています。
しかし、実践出来ているかというと、疑問です。
私は、お客様というのは、実際にモノを使用したり、直接サービスを受ける、消費者だと考えています。
売ってくれる代理店であったり、社内の上司であったり、株主ではありません。
会社組織が誰に目を向けるか?
これがぶれてしまうと「お客様目線」もぶれてしまうのだと思います。
小さな子供が、母親が目を離した隙に転ぶと泣きます。
これは、転んだことを気付いて欲しい気持ちと、痛みを知って欲しい気持ちからだと思います。
母親が、たいして痛くはないはずだと思っても、子供の気持ちになって、
心から「痛かったね」と思って接してあげれば子供は泣き止むのだと思います。
モノやサービスの提供者である企業からみれば、消費者は私も含めて子供のようなものです。
燃費データを騙すことなんて簡単なのでしょう。
知識や情報などに圧倒的な差があるからです。
少しでも燃料費を軽減したい、環境に優しい車に乗りたいと思って、公表された燃費データを信じて三菱自動車の車を買ったお客様がいます。
そのお客様にとって、この不正はすごく痛いことです。
企業が痛いのではなく、お客様が痛いのです。
お客様の立場になって、会社全体がこのお客様の痛みを理解できるか。
これが信用復活の鍵となるのだと思います。
お客様から「ありがとう」と言ってもらえるモノやサービスを提供する。
お客様から評価されないかぎり企業の存続はない。
何をすればお客様に喜んでもらえるか。
この視点を貫くことでしか、「お客様目線」にはなれないと感じました。
当社も私も、本当の意味での、「お客様目線」をもっと磨かなければならないと改めて気を引き締めました。
本日は4月1日。
本日から新年度がはじまる会社も多いかと思います。
当社も、本日から節目となる第10期目がはじまりました。
東京は桜が満開となり、まさに春爛漫です。
先日、お世話になっている会社の研修室を訪問する機会がありました。
広い研修室のテーブルには、一人ひとりの氏名が記載された資料が置いてありました。
聞くと、本日開催される入社式の準備資料だそうです。
数えてみると40数名。
初々しい新入社員があの研修室で入社式にのぞむことを思うと、私自身も身が引き締まる思いです。
私にとって4月ははじまりの月です。
子どもの頃は入学式、新学期が4月。
社会人になってからも、新卒で入った会社も、転職した保険会社も、入社式は4月であり新年度でした。
そして独立して作った当社も3月決算。
ゆえに4月が新年度となります。
昨日までの良いことも悪いことも、全部、リセット。
私にとっては、すべてを0にしてまたはじまるのが4月1日です。
ビジネスマンにとってのお正月といってもいい日です。
私は、新年度にあたり、以下の言葉を思い出しています。
「人生は今日が始まり。昨日まではリハーサル。今日から本番。」
過去7,000回の講演と、90冊を超える著書を出版されている、田中真澄氏の言葉です。
80歳になる今も現役でパワフルに仕事をされています。
昨日までに区切りをつけて、今日からが始まりと強く意識して、また一年間、頑張ります。
今年度も一年間、宜しくお願いいたします。
今日は3月1日。
年度末の会社も多いと思います。
当社も今月が決算ですので、悔いの残らないような1ヶ月を送りたいと思います。
日銀のマイナス金利政策を受けた保険会社の動きが相次いでいます。
保険会社各社では、一部の貯蓄性商品について、予定利率改定による保険料引き上げ、または販売停止、前払い割引の縮小などの対応を急ピッチで進めています。
すでに販売停止になっている商品もありますが、4月以降からの改定という商品もあります。
この対応は、日銀のマイナス金利導入により、長期金利が下がったことに起因します。
今日は、「長期金利が下がるとなぜ保険料が上がるのか?」ということについて解説してみます。
保険会社は、死亡率・予定利率・事業費率の3つの要素で保険料を決めています。
今回の長期金利低下は、このうちの「予定利率」が関係しています。
保険会社は預かった保険料を国債などで運用しています。
この将来にわたる保険会社としての「運用の利回り予測」を予定利率と言います。
※預金等の利率や利回りとは違う点に注意
元本100円を金利5%で10年運用すると105円(単利の場合)。
もし金利が3%に下がったとして、10年後に上記と同じ105円にしなくてはならない場合、102円の元本が必要になります(105円/1.03)。
この元本を保険料と考えると分かりやすいかと思います。
<10年後に105円にするための必要元本>
金利(予定利率)5%⇒元本(保険料)100円
金利(予定利率)3%⇒元本(保険料)102円
この場合、予定利率が2%下がったことで、保険料は2円上がったことになります。
つまり、
予定利率 高 ⇒ 保険料 低
予定利率 低 ⇒ 保険料 高
こういう関係が成り立ちます。
非常に簡略化した論理ですが、これが予定利率と保険料の関係です。
今回、日銀のマイナス金利導入⇒長期金利低下⇒保険会社の予定利率低下⇒保険料UP、という流れになっています。
欧州では、マイナス金利を現在の-0.3%から、さらに下げるような市場予測もあるようです。
日銀の追加政策がどうなるかは不明ですが、しばらくは、歴史的な超低金利の傾向は続くでしょう。
3月中は現行の予定利率を維持する保険会社もあります。
貯蓄性の高い保険商品をお考えの場合には、情報収集を早めにされたほうがよいかもしれません。
保険会社や商品改定の動向についてご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。
1月もあっという間に過ぎ、今日から2月がはじまりました。
1月29日、日銀は、マイナス金利政策の導入を決めました。
これは日本では史上初のことです。
事前の市場予測もされていないサプライズだったので、国内を含む世界の金融市場ですぐに反応しました。
私自身、言葉や理論は知っていましたが、現実に導入されたことは驚きました。
本当にいろいろな金融政策があるんですね。
今回のマイナス金利政策は、民間銀行が日銀に預ける当座預金の一部に0.1%の金利を課すものです。
これは2月16日からとのこと。
通常は、お金を預けると金利を受け取れますが、逆に金利を払うことになります。
だから、民間銀行は、余ったお金を預けると損失になってしまうので、
株を買ったり、企業へ融資する方向にお金を流す行動に移すだろうと日銀は思惑しているのです。
また、これにより、金利がさらに低下し、円が売られ、外貨が買われることで、円安効果も狙っています。
・市中にお金が出回ることでインフレに。
・さらに消費や消費が喚起されることで景気UP。
・円安による輸出増で企業業績UP。
このような効果も狙っているのですね。
結果はどうなるか分かりませんが、私は、日銀のチャレンジ精神とデフレ脱却・景気回復への強い意志力を感じます。
京セラ創業者の稲盛和夫氏が作った京セラフィロソフィーの第44項は、「チャレンジ精神をもつ」です。
そのなかに次の一文があります。
「人はえてして変化を好まず、現状を守ろうとしがちです。しかし新しいことや困難なのことにチャレンジせず、現状に甘んじることは、すでに退歩が始まっていることを意味します。」
今回の日銀のチャレンジが、世界金融マーケットの混乱を収束させるきっかけになればよいと願っています。
私自身も、変化することを恐れず、困難に直面したときこそ、チャレンジする攻めの精神を持ちたいと思います。
新年明けましておめでとうございます!
2016年がはじまりました。
今日から仕事初めの方も多いと思います。
本年も宜しくお願いいたします。
今年は申年。
干支は、十干が丙、十二支が申の「丙申(ひのえさる)」です。
干支は10と12の最小公倍数なので、常に60年に一度の周期で同じ干支になります。
前回の丙申は60年前の1956年でした。
60年前はどのような年だったのでしょうか。
1956年というと戦後11年目の年です。
その年の主な出来事は以下の通りです。
・好景気が続き、経済白書に、「もはや戦後ではない」と掲載された。
・国際連合に加盟し、国際社会の一員となった。
あの敗戦から11年後にこのような力強いメッセージが発進されていたことに驚きました。
戦後復興を支えた先輩たちから現在を見れば、
「バブル崩壊から20年も経って何をモタモタやってる!」と叱責されるかもしれません。
今年が60年前と同じように、「もはやデフレではない」とか「もはや不況ではない」となればいいですね。
今年は、7月に参議院選挙、8月にリオ五輪があります。
株価を重視する安倍政権を考えると、参議院選挙を控えた前半は株価が好調なのかなとも思います。
またリオ五輪が終わると、一気に2020年の東京五輪に意識が向かい、国全体の気分が高揚し、本格的な好景気がくるかもなとか思ったりしています。
とはいってもマクロ環境は、当社のような小さな会社にはほとんど関係なく、関係あるのは常に「自らの具体的な行動」しかないと、気を引き締めているところです。
今年も、「良いことしか考えない」と心がけ、明るく前向きに過ごしていきます。
今年一年がみなさまにとってもよい年であることを祈念いたします。
本日は12月1日。
早いもので今年もあと1ヶ月となりました。
残り1枚になったカレンダーをみて、悔いの残らない1ヶ月を過ごし、1年の締めくくりを有意義にしたいと思っています。
私は、元旦に、先祖の菩提寺へ出かけお墓参りをし、その後、神社で初詣の参拝をしています。
クリスマスシーズンになればイルミネーションを楽しみ、人並みにパーティーにも参加したりします。
また山に登ればご来光に手を合わせ、街中に神社を見つければお賽銭を入れてお参りすることもあります。
さらに、友人知人の結婚式に呼ばれ、式場が教会であれば、神父さんまたは牧師さんの指示に従い、他の参列者と一緒に賛美歌を合唱します。
こういう確固たる宗教感がない人間は欧米や一神教の国々や人々から不信に思われるそうですね。
仏教、神教、キリスト教などいろいろな宗教の行事に参加したりすることは、信念がない人間で信用できないとなるのでしょうか。
しかし、日本では、私のように行動する人は少なくありません。
宗教をカルチャー(文化)やイベントとして捉える傾向にもあるのかもしれません。
日本では古来から八百万(やおよろず)の神がいる国と信じられてきて、
いろいろな神様や信仰が共存できる土壌があるのだと思います。
それは、互いの「違い」を認め、協調することを意味しているだと思います。
考え方や宗教が違っても、相手が悪ではないからです。
フランスのテロや欧米諸国のその後の反撃をみたときに、多神教であるがゆえに、他者との違いを受け容れやすい、日本人の役割もあるのではないかと感じました。
いつか戦争や争いのない世界になればと心から願います。
私自身は、明朗愛和の精神を心がけたいと思います。
11月に入りました。
今日の東京は冷たい小雨交じりの天気で、秋というより初冬を思わせる寒い朝を迎えました。
季節の変わり目で体調を崩されている方も多いようです。
体調管理に気をつけながら、また新たな1ヵ月をお過ごしください。
先日、お客様企業のある社長が雑談で次のようなことを話されました。
「担当営業の対応が悪すぎたので、その会社との取引きを止めた。」
一担当営業の問題で会社全体の取引きを停止するのは厳し過ぎるのではという向きもあると思いますが、「一事が万事だから」というのがその理由でした。
つまり、一担当者の姿勢は、会社全体の体質を表していると判断されたのでした。
横浜市のマンション1棟が傾いたことで発覚した、旭化成建材の杭打ちデータ改ざん問題。
この問題が収拾せず、ますます混迷しています。
発覚当初、同一の現場責任者の案件で他の不正も見つかり、会社側もマスコミも、この一人の責任者の問題のように示唆しました。
しかし、調査を進めていくうちに、この責任者が関与しない案件での不正が複数見つかり、会社ぐるみの問題である可能性が濃厚となってきました。
まさに「一事が万事」だったのでした。
会社がいくらルールを定めても、実際に運用する役職員のモラルがないと、意味がありません。
京セラ創業者の稲盛和夫氏は、人生(仕事)を成功させるための方程式として次のような数式を表しています。
人生(仕事)の結果=考え方×熱意×能力
そして、熱意と能力は0からプラスしかないが、考え方にはマイナスもあると説いています。
つまり考え方がマイナスだとどんなに熱意や能力があっても結果がマイナスになってしまう。
むしろ熱意や能力が高いほど、考え方によって、マイナスも大きくなってしまうと言っています。
まず大切なことは、「考え方」であり、これは会社も個人も同じですね。
私自身も社会に生きる人間の一人として肝に銘じたいと思います。
本日から10月がスタートしました。
下半期のスタートにあたり、心機一転、新鮮な気持ちで仕事に取り組みたいと思います。
私の本業は生命保険の代理店事業です。
その傍ら、文化活動として長く書道を習っています。
きっかけは、高校のときに師である田岡正堂先生と出会い、以来、ずっと続けています。
田岡先生は2年前、79歳でご逝去されましたが、日展審査員を経て日展評議員となり、日本を代表する書家の一人として活躍されました。
現在、私の師は田岡先生の跡を引き継がれた近藤北濤先生(現日大豊山女子中学高校校長)です。
私は、現在、近藤先生の指導を受けながら、毎日書道会会員・創玄書道会審査会員・鷗友書道会理事という立場で書活動をしています。
実は、先月、9月6日(日)に私主催でお習字教室をはじめて開催しました。
地域で懇意にしているご家族と友人、知人、私の家族など、本当に身近な間柄だけでのお習字教室ですが、大変有意義な時間となりました。
大人も子供も一緒で、小学2年と4年のお子様も参加されました。
テキストは、大人が古典臨書(王義之の蘭亭序)、子供は鷗友書道会発行の「書」の題材から。
私が手本を書き、約2時間、みなさん真剣にお習字をされました。
田岡先生は、自ら教員として教壇に立ち、弟子の多くを教員に育て、教育の場で書道の普及活動に大きく貢献されました。
私も微力ながら、師に習ったことをこれから少しずつ伝えていきたいと思っています。
本日から9月に入りました。
東京は、8月前半の猛暑が嘘のように、涼しい日々が続いています。
スーパーには秋刀魚がならび、秋の到来を感じる季節になりました。
先月の8月は私にとって、印象深い月となりました。
実は、8月上旬、私宛に、日本骨髄バンクから通知が届きました。
白血病などで苦しんでいる患者さんへの、骨髄または末梢血幹細胞提供についてのご案内です。
私は、4年半前の2011年2月にドナー登録をしました。
4年半を経て、私のHLA型(白血球の型)と適合する患者さんが現れ、私が提供者の一人として選ばれたのです。
私の体が人の役に立つ。場合によっては命を救うこともできるかもしれない。
そんな思いを胸に、即座にコーディネートを希望し、健康告知等の書類を返送しました。
しかし、その10日後、骨髄バンクからの連絡は残念なものでした。
なんと、私の健康上の問題で、骨髄等の提供はできず、コーディネートは進められないとのこと。
つまり、候補者から外されてしまいました。
最大の理由は、「腰痛」です。
実は、7月にふとした動作から腰を痛め、その後、整骨院に4度通院しました。
もう痛みはなくなりましたが、まだ通院中です。
この腰痛、骨髄を抽出するための手術をした際、腰痛を悪化させる原因になるそうです。
そのため、安全をみて、今回、私は断わられました。
また、インプラントの2次手術と、親知らずの抜歯が直近で控えていることも理由の一部だったかもしれません。
私は、2年間の保留となりました。
2年後以降、また適合する患者さんが現れれば提供者の候補に選ばれるかもしれません。
そのときまで、健康管理に努めたいと思っています。
と同時に、今回のプロセスを体験して、しっかりした仕組みになっていると感じました。
日本の骨髄移植医療は安心できると思いました。
ところで、血液型というと、A型、B型、O型、AB型と分かれていますが、これは赤血球の型です。
赤血球は4種類プラスRHの+と-しかありません。
だから同じ血液型を探すのは比較的簡単で輸血なども普及しています。
しかし、白血球の型は、数万種類あると言われています。
数万分の一の確率でしか、適合者は現れないのが現実です。
骨髄移植医療の難しさはここにあるわけですね。
この問題を改善するには、ドナー登録者の数を増やすことしかありません。
ドナー登録は、全国の献血センターで2mlの採決だけで簡単にできます。
私は、少しでも多くの方がドナー登録することで、一人でも多くの患者さんが助かることを願っています。
ご興味ある方は、以下、日本骨髄バンクのサイトをご覧ください。
日本骨髄バンク8月に入りました。
夏本番。
毎日暑い日が続きますが、今年も夏を楽しみたいと思います。
夏といえば高校野球。
6日に甲子園大会が開幕。
本日3日午後に組み合わせ抽選会です。
東京在住の私にとって、今年の注目は、何と言っても早実の清宮幸太郎選手。
すでにマスコミでも注目されているのでご存知の方も多いと思います。
中学のシニア時代から注目され、高校では春の大会でデビュー。
春の大会が3月から始まるため、まだ入学していない清宮は当初ベンチに入れず。
しかし学校はベンチ入り選手の枠を空けて待ち、入学即、背番号を与え、入学3日後に春の大会でスタメン。
そしてすぐヒットを打ち、その後の試合では特大ホームランを打ちました。
そのまま夏の予選を迎え、西東京大会に出場。
夏の予選は20打数10安打と期待通りの活躍をして、見事、甲子園の切符を手に入れました。
1年生、はじめの夏から甲子園に行けたことも、彼の運を感じます。
1年生からスラッガーとしてこれだけ注目された選手は、あの清原以来ではないでしょうか。
是非、甲子園で大活躍して欲しいですね。
私の母校は残念ながらベスト16で終わってしまいました。
また来年に期待です。
ところで、母校の野球部コーチなどによると、グランド内の気温は昔より高くなっているようです。
昔は練習中に水を飲むことは禁止されていましたが、今では、むしろ積極的に飲ませているそうです。
それも水やお茶では熱中症予防には不十分で、専用のスポーツドリンクを飲ませているそうです。
東京の夏は、もう根性論で何とかなるようなレベルではないのでしょうね。
2020年の東京オリンピックでは競技場やエンブレムの問題で揺れていますが、実際、開催期間中は、海外選手たちの熱中症対策を考えるべきでしょう。
せっかくオリンピックを開催したのに、選手が暑さでバタバタ倒れて、それをみた外国人に、「日本には行きたくない」と思われたら元も子もありませんから。
みなさまも熱中症に気をつけてください。
あと、水の事故も増えているようですね。
特に小さなお子様がいらっしゃるかたは、海や川、プールでは十分に気をつけてください。
本日は、7月1日。
2015年も折り返し地点を過ぎ、今日から後半戦となりました。
先日、勇心会という勉強会で講演をさせていただきました。
会社のNO.2以下を中心とした若手ビジネスマンが集まる勉強会です。
与えられたテーマは、「心に羅針盤を持つ」。
羅針盤=判断基準 です。
講演前に今までの経験を振り返り、私の羅針盤は以下の通りとしました。
「人間として何が正しいかを判断基準とする」
これは稲盛和夫氏の箴言でもあります。
決断を迫られたとき、迷ったとき、人間として正しいと思う方を選択する。
これを判断基準とすれば大きな間違いは起こらないと改めて考えました。
しかし、「何が正しいか」を見極めることは簡単ではありません。
正しいと思ったことが、逆に悪いことかもしれません。
それを磨くのは人間関係だと思います。
家族であり、お客様であり、仕事上のパートナーであり。
結局は、日々の人間関係のなかで、倫理感や道徳感、価値感が磨かれるのだと思います。
そうしたなかで、「何が正しいか」を育んでいくのではないでしょうか。
ダイヤモンドはダイヤモンドでしか磨けないように、人も人でしか磨かれないのではないでしょうか。
そうなると、「どんな人と付き合うか」が重要ですね。
「人は鏡」と言います。
自分を磨き、よい人との縁を大切にして、「人間として何が正しいか」という判断基準をしっかりと持ちたいものです。
本日から6月がスタート。
早いもので今月で一年の半分が終了します。
5月は、鹿児島の口永良部島新岳の噴火、小笠原沖M8.1の地震など、自然災害が目立ちました。
犠牲者がでなかったことは幸いでしたが、国内ではどこにいても油断はできず、私自身も備えは十分にしておこうと気持ちを改めました。
その一方で、経済は好調のようです。
特に株価は好調でちょっとトピックスを抜きだすと以下のようなことが挙げられます。
・株価11日間連続上昇 27年ぶり
・5月の上げ幅 21年ぶり
・東証一部時価総額過去最高を更新 25年ぶり
もちろん、株価やその他のマクロ的な経済指標が、私を含めた個人の家計や会社の業績に必ずしも比例するわけではありません。
しかし、何となくでも「景気がよくなっているんだな」と感じることができると、気持ちは前向きにはなれます。
私は、あまり難しいことを考えず、ただ単純に、「景気がよくなっている、今後、もっとよくなる。」と思うようにしています。
そして、そのよい流れに乗り遅れないように、日々、できること、やるべきことを全力で頑張ることが大切だと信じています。
京セラ創業者の稲盛和夫氏の言葉に以下のような一文があります。
「楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する」
プランニングは現実的に悲観的にするが、いざ実行するときは、楽観的に行動する。
言い換えれば、悲観的な実行や行動は避けるべきということでもあります。
「病は気から」「景気」。
やはり気持ちの持ちようが大切なのだと思います。
よい指標は素直に受け止めて、日々、楽観的に行動していきたいですね。
みなさまにとっても今月もよい一ヶ月となることを願っています。
今日は5月1日。
連休に入っている方も多いと思います。
初夏を思わせるような天候が続きますが、連休中も天気がいいようです。
お出かけされる方は休日をお楽しみください。
先日、春の高校野球、東京大会が終了しました。
今回、母校、佼成学園は準優勝。
4年ぶりに関東大会進出となりました。
私は、準々決勝の帝京高校戦と準決勝の東海大菅生高校戦を観戦しに行きました。
球場は神宮第二。
帝京とは、6-1。
菅生とは、8-5。
帝京は私が野球部にいた頃から強豪で、私の1つ上の世代は、のちにプロに行った吉岡という選手がいて、甲子園で優勝しています。
また菅生は先日の甲子園センバツ大会に出場しており、西東京の強豪です。
この2校に勝ったことは、私にとっては大変な快事でした。
しかし、決勝は日大三高と対戦し、4-25という屈辱的な大差で敗戦してしまいました。
残念ですが、夏に雪辱を果たし、是非、甲子園を実現して欲しいと思います。
日大三高戦を観戦した先輩OBが次のように言っていました。
「試合は大差で負けた。しかし、礼儀やマナーでは負けていなかった。
母校の選手のスポーツマンシップ溢れる振る舞いはすばらしかった。」
高校野球も学校教育の一環です。
勝つことも大切ですが、もっと高校生としてスポーツマンとして大切なことがある。
大差で負けても腐らず、先輩OBにこのように思わせる後輩たちを誇りに思います。
これからも「謙虚にして驕らず」、夏に向けて頑張って欲しいですね。
本日は4月1日。
本日から新年度がはじまる会社も多いかと思います。
当社も、本日から第9期目がはじまりました。
東京は桜が満開となり、まさに春爛漫。
私は一年のなかで4月が一番好きです。
子どもの頃からずっと4月がはじまりの月だったからです。
子どもの頃は入学式、新学期が4月。
社会人になってからも、新卒で入った会社も、転職した保険会社も、入社式は4月であり新年度でした。
そして独立して作った当社も3月決算。
ゆえに4月が新年度となります。
昨日までの良いことも悪いことも、全部、リセット。
私にとっては、すべてを0にしてまたはじまるのが4月1日です。
ビジネスマンにとってのお正月といってもいい日です。
私の机の横には、稲盛和夫氏の箴言集を綴った日めくりカレンダーがあります。
本日1日のカレンダーには次のように書かれています。
===
「新しい計画を実現する」
「新しき計画の成就は、ただ不屈不撓の一心にあり。
さらばひたむきにただ想え。気高く強く一筋に」
===
後段は中村天風氏の言葉からの引用です。
一年の計は元旦にあり。
ビジネスマンの計は4月1日にあり。
私も本日、今年度の目標を立てようと思います。
今年度も一年間、宜しくお願いいたします。
3月となりました。
今月が年度末の会社も多いかと思います。
当社も3月決算です。
悔いを残さないようにこの1ヶ月を取り組みたいと思います。
イギリスのウィリアム王子が初来日され、2月26日から昨日3月1日まで滞在されました。
キャサリン夫人は第二子を妊娠されているとのことで、ご夫婦そろっての来日は叶いませんでしたが、私たち日本人にとっては明るい話題になりました。
王子はあのダイアナ妃のご子息ということで注目を集めました。
ダイアナ妃が初来日されたのは1986年、今から約30年前。
私はまだ14歳でしたが、あのときの大フィーバーは子どもながらに印象的でした。
今回、ウィリアム王子は、宮城県や福島県など、東日本大震災の被災地を訪問されたとのこと。
ご自身も幼い頃に大切なお母様を亡くされ、その悲しみを乗り越えた経験がある王子。
被災されたり、大切なご家族を亡くされた被災地の方々にとっては、大きな励みになったのではないでしょうか。
今月、3月11日で大震災から丸4年が経過します。
東京にいるとあのときの記憶が薄れがちになってしまいます。
しかし、被災地の方々はまだまだ厳しい現実と向き合っています。
私たちは、自分ができることをして、被災地に貢献したいと思っています。
できることと言えば、売上げを最大限に伸ばし、経費を最小限に抑え、利益を出し、1円でも多く納税することだと思っています。
そんな想いを強く抱きながら、また1ヶ月、頑張ります。
1月があっという間に過ぎ去り、2月を迎えました。
イスラム過激化組織「イスラム国」(IS)による、日本人拘束事件は、最悪の結果となってしまいました。
湯川遥菜さんに続き、昨日の朝の報道で、後藤健二さんも殺害されたとのこと。
私は、このたびの非道で残虐な行為について、日本人の一人として激しい怒りを覚えました。
本当に許されないことだと思います。
お二人のご冥福を心からお祈りするとともに、ご家族のみなさまのご心痛、心からお見舞い申し上げます。
私たちは、この事件とどう向き合えばよいのでしょうか。
このメルマガを書くにあたり私なりの意見を考えましたが、全くまとまりませんでした。
でも、「報復は報復でしか返ってこない」。
私たち日本人は、毅然として怒りを抑え、報復以外の手段でテロと向き合うしかないのだと思います。
テログループが信じること。
欧米人が信じること。
日本人が信じること。
これらはみな違います。
私は違いがあってよいと思います。
ただ、お互いに違いを認め合うこと、寛容性が大切だと感じます。
しかしその寛容性が全く通じない相手も世界にはたくさんいる。
これだけはしっかり認識すべきです。
日本人はよく宗教がないと言われます。
クリスマスを祝い、正月には神社を参拝し、お寺にいってお墓参りをする。
山に登り太陽が昇れば手を合わせ、田舎道にたまたま神社があればお賽銭を入れる。
私も多くの日本人と同様に、まったく抵抗感なく、こんな日常を送っています。
こういうのを多神教と言うのだそうです。
1つの神しか信じない、キリスト教やイスラム教に比べれば、寛容性が高いのかもしれません。
一神教で世界人口の多数を占める現代の国際社会において、違いを認めることができる多神教の日本が果たすべき役割は大きいとも言えます。
しかしそんなことは世界には通用しないのかもしれません。
今回の事件は悲しみとともに、いろいろなことを考えさせられました。
また、塩野七生著文春文庫「日本人へ 国家と歴史篇」222ページの次の一文が頭から離れません。
「中東に攻めこんで勝ったヨーロッパ人は、後にも先にもアレクサンダー大王一人である。」
みなさまはどのようにお感じになりましたか。
あけましておめでとうございます!
当社は本日より業務開始です。
今年も宜しくお願いいたします。
今年は未年ですね。
未は羊。
祥を連想される中国の吉祥動物の1つだそうです。
また群れをなすことから「家族の安泰」という意味もあるそうです。
ところで10干12支を組み合わせた干支は、乙未(きのとひつじ)。
10と12の最小公倍数は60なので、同じ干支は60年に一度しか巡ってきません。
ゆえに生まれた年の干支と同じ干支になるのが60歳のときで、暦が一巡するので「還暦」というのでした。
では60年前の今年と同じ干支、乙未の年はどんな年だったのか調べてみました。
60年前は昭和30年(1955年)。
この年の日本経済は好調でした。
昭和29年12月から昭和32年6月まで神武景気を迎え、日本経済は戦前を上回りました。
そして翌年昭和31年には、「もはや戦後ではない」と経済白書に記されたのでした。
こう振り返ると、乙未の年は、けっこういい年のような気がしますね。
今年は「もはや不況ではない」とか「もはやデフレではない」などのフレーズが登場するかもしれません。
良い一年になるといいですね。









